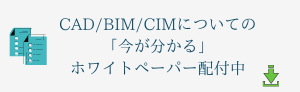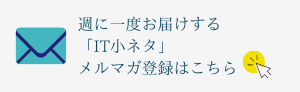FLSとは?3Dスキャンの点群データを扱うための基礎知識と活用ガイド
1. はじめに
近年、3Dスキャン技術を活用した「点群データ」が、建設・土木・製造・文化財保存など、さまざまな分野で注目を集めています。従来の作業を効率化し、現場の状況をより正確に把握できる手段として、その重要性は年々高まっています。
ただし、点群データはファイル容量が大きく、専門的な処理が必要になるため、初心者にとっては少しハードルの高い技術に感じられるかもしれません。特に、「どのファイル形式を使えばよいのか?」「FLSって何?」「どうやって点群を可視化・編集するの?」といった疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、FARO社の3Dレーザースキャナーで取得される「FLSファイル形式」に焦点を当て、点群データの基礎知識から活用方法までをわかりやすく解説します。FLSとは何か、なぜ使われるのか、そして他の形式との違いや変換方法まで、順を追って丁寧にご紹介します。
さらに、FLSファイルを扱う上で知っておきたい主要ツール(FARO SCENE、Autodesk ReCap、CloudCompareなど)や、建設・BIM・文化財保存での活用例、データ容量の管理方法、精度確保のポイントといった実務的な話題にも触れていきます。
初心者の方から、これから本格的に点群活用を考えている方まで、幅広い層の方にとって「FLSとは何か」がしっかりと理解でき、実務や学習への第一歩を踏み出せるような内容を目指しています。
2. FLSとは?基本の理解から始めよう
引用:https://www.faro.com/ja-JP/Resource-Library/Article/understanding-laser-scanners
FLSとは、FARO社が提供する3Dレーザースキャナーで取得された点群データを、独自のファイル形式で保存したものです。FLSファイルは、スキャンの位置情報、反射強度、カラー情報などを高精度で記録できる点が特長で、建設現場や構造物の記録、文化財の保存など、幅広い用途で利用されています。
まず、点群データとは何かを簡単に説明しましょう。点群データは、物体や空間の表面を多数の「点」で構成して3次元的に記録したデータのことで、それぞれの点にはX・Y・Zの座標や、色、反射強度などの情報が付加されています。つまり、点群は3Dスキャンによって取得された、空間そのものの「立体的なコピー」とも言えるのです。
FLS形式の点群データは、FARO社の純正ソフトウェアであるFARO SCENEを使うことで、効率よく処理・編集ができるよう設計されています。スキャンデータの読み込みから、位置合わせ(レジストレーション)、ノイズ除去、点群のフィルタリングなど、多くの処理を高速かつ直感的に行うことが可能です。
しかし一方で、FLSはFARO社独自の形式であるため、他社製のCADソフトや点群処理ツールで直接利用することが難しい場合があります。そのため、FLSを活用するには、用途に応じて汎用的な形式(例:E57やLAS)への変換が必要になることが多いのです。たとえば、Autodesk ReCapやRevitなどで点群を扱うには、一度FLSからE57に変換する手順を挟むのが一般的です。
こうした知識を持っておくことで、FLSと他形式を目的に応じて使い分けたり、複数のツールやプロジェクトに対応できるようになります。まずは、FLS形式の持つ特性や役割をしっかりと理解することが、点群データを扱ううえでの大切な第一歩となります。
次の小見出しでは、FLSファイルの具体的な特徴や、他の点群形式との違いについて、初めての方にもわかりやすい言葉で紹介していきます。実務での導入やスキルアップを目指す際の参考にしていただければ幸いです。
2.1. FLSファイルの定義と特徴
FLSファイル形式は、FARO社製の3Dレーザースキャナーでスキャンした点群データを保存するための、専用のファイル形式です。この形式には、スキャン時の位置情報や各点のカラー情報、反射強度といったさまざまな属性が含まれており、スキャナーが取得したデータを忠実に保持できる仕組みになっています。
たとえば、FLSファイル内には、レーザーが物体表面からどれくらい反射されたかを示す「強度情報」も含まれており、これによって後の解析や視覚化の際に、物体の材質やノイズの入りやすい箇所を判断しやすくなります。こうした情報があることで、点群データをただの「点の集まり」として扱うのではなく、意味のある構造として解釈しやすくなるのです。
また、FLS形式はFARO純正のソフトウェア「FARO SCENE」での利用に最適化されており、大容量データでもスムーズに読み込み・表示・編集が行えるように設計されています。レジストレーションやノイズ除去、フィルタリング処理などがスムーズに行える点は、実務において大きなメリットとなります。
ただし、FLSはプロプライエタリ(独自仕様)形式であるため、他社製のCADや点群処理ソフトウェアではそのまま読み込めないこともあります。たとえば、BIMソフトや他の3Dモデリング環境で点群を扱いたい場合、FLSをE57やLASといった汎用形式に変換する必要があります。そうすることで、他のソフトウェアとの互換性が保たれ、より柔軟にデータを活用できるようになります。
つまり、FLS形式はFARO製品と連携する環境では非常に高い処理効率と機能性を発揮しますが、異なる環境で点群を扱うには、変換や中間処理が必要になるという点を理解しておくことが大切です。
2.2. 他の点群形式(E57やLASなど)との違い
点群データのファイル形式にはさまざまな種類がありますが、代表的な汎用形式として知られているのが「E57」や「LAS」といった形式です。これらの形式はFLSと異なり、特定メーカーに依存しない標準仕様であるため、ソフトウェア間の互換性が高いという利点があります。
たとえば、E57はASTM(米国材料試験協会)が策定した国際標準規格(E2807)に基づいており、複数のメーカーのスキャナーから出力される点群や関連データを共通のフォーマットで保存できるよう設計されています。構造が統一されているため、異なる機種で取得した点群データもE57に変換すれば同じプラットフォーム上で扱いやすくなります。
LAS形式は、主に航空測量や地形モデルの分野で広く使用されてきた歴史があります。オープンな仕様として提供されており、座標や反射強度、高度といった情報を効率的に保持できるため、GIS(地理情報システム)などとの連携にも適しています。近年では地上型スキャナーからのデータもLASに変換して利用されることが増えています。
一方、FLS形式はFARO社が自社製スキャナーのために最適化して設計したファイル形式です。スキャンデータの忠実な保持や、純正ソフトでの高速処理を目的としているため、他形式よりもメーカー特化型といえるでしょう。データ変換せずに最大限の処理パフォーマンスを得られる点では非常に優れていますが、オープンな環境での運用や他社製ツールとの連携には、やはり変換作業が必要です。
このように、FLS、E57、LASにはそれぞれ異なる特徴と用途があります。点群データをどの環境で使いたいのか、どれだけの互換性が必要なのかを考慮し、それぞれの形式を適切に使い分けることが、効果的な点群活用の鍵になります。
3. FLSファイルを扱うために必要なツール
FLSファイルを実際に開いて編集・変換を行うには、専用の点群処理ツールが必要です。中でも、FARO社が提供する純正ソフト「FARO SCENE」は、FLSファイルの表示・加工において最もスムーズで高機能な環境を提供してくれる代表的なツールです。FLS形式で記録されたスキャンデータを効率的に読み込み、不要なデータの削除や位置合わせ、セグメンテーション(領域の分類)など、さまざまな処理が可能です。
また、FARO SCENEだけでなく、Autodesk社の「ReCap」や、オープンソースの「CloudCompare」といった他の点群ツールと組み合わせて活用するケースも増えています。FLSファイルをそのままでは読み込めない場合でも、一度E57などの汎用形式に変換することで、他のソフトで活用できるようになります。
このように、使用するソフトウェアによって操作の流れや処理精度、出力可能な形式が異なってくるため、作業目的に応じて最適なツールを選定することが非常に重要です。たとえば、FLSを扱う初期段階ではFARO SCENEを中心に学び、BIMやGISへの連携を考える段階ではReCapやCloudCompareにシフトしていくと、段階的にスキルを広げやすくなります。
以下の小見出しでは、それぞれのツールの特徴や使い方のポイントを具体的に紹介します。どのツールを選ぶかは、自社のプロジェクト規模や目的、スタッフのスキルレベル、そしてソフトウェアのライセンス形態などにもよって異なります。最終的には、FLSファイルをスムーズに可視化し、必要に応じたデータ変換を行いながら業務に活かすことが目的です。まずは基本的なツールの理解から始めて、徐々に応用力を身につけていきましょう。
3.1. FARO SCENEの基本機能と使い方
FARO SCENEは、FARO社製のレーザースキャナーで取得したFLSファイルを扱うための、公式ソフトウェアです。スキャンデータを読み込むだけでなく、位置合わせ(レジストレーション)やノイズ除去、セグメンテーションなど、点群処理に欠かせない多彩な機能を備えています。
まずFLSファイルを読み込むと、複数のスキャンデータの位置を自動または手動で調整する「レジストレーション」が行えます。これは、スキャンが重なり合う領域の整合性を取るための作業で、正確な3Dモデルを生成する上で不可欠な工程です。また、点群の中に含まれる不要な情報(ノイズ)を取り除くフィルタリング機能も用意されており、これによりデータの品質が向上します。
さらに、FARO SCENEには壁や床といった主要な平面を自動的に検出して分類する機能があり、点群の構造を把握しやすくなっています。必要な箇所だけを抽出して部分的にメッシュ生成を行うこともでき、3Dモデリング作業にもつなげやすくなっています。こうした機能により、3Dスキャンした現場データを視覚的に確認しながら効率よく処理を進めることが可能です。
ただし、点群データは非常に大容量になることが多いため、快適に作業を進めるには高性能なパソコン環境が求められます。特に、GPU性能やメモリ容量はFARO SCENEの操作性に大きく影響するため、あらかじめPCのスペックを確認しておくとよいでしょう。また、スキャンデータのバックアップや保存先の選定など、データ管理面にも注意が必要です。
FARO SCENEは、初心者でも操作ガイドやチュートリアルを活用すれば比較的スムーズに扱えるようになるため、FARO製スキャナーを導入したばかりの方にもおすすめです。まずはこのソフトに慣れることで、FLS点群データの扱いに自信を持てるようになるでしょう。
3.2. その他の対応ソフト(ReCap、CloudCompareなど)
FLSファイルを直接開けるのはFARO SCENEが中心ですが、他のツールでもFLSデータを活用することは可能です。その際には、FARO SCENEなどを使って一度E57やLASなどの汎用形式に変換し、その後目的に応じたソフトウェアで読み込むという流れになります。
Autodesk ReCapは、点群データとBIMの連携を前提とした設計ソフトで、特にRevitやNavisworksといったAutodesk製品との親和性が高いことが特長です。たとえば、建築や土木の現場で取得した点群をReCapに読み込み、Revitで作成した3Dモデルと重ね合わせて設計の整合性を確認するといった使い方が一般的です。設計段階での空間把握や施工の計画において、非常に有効な手段となります。
一方で、CloudCompareはオープンソースの無料ソフトでありながら、点群データの可視化・編集・解析といった基本機能を網羅しています。ノイズ除去や断面の切り出し、点群同士の比較分析など、さまざまな用途に柔軟に対応できるのが魅力です。研究用途や学習用としても非常に人気があり、軽量なツールとして多くの現場で活用されています。
さらに、土木や建築以外にも、GIS(地理情報システム)や文化財保存、検査分野など、さまざまな分野で点群データを活用するためには、対応ソフトの柔軟性が重要になります。FLSファイルを汎用形式に変換しておくことで、こうした多様な分野への展開がしやすくなります。
このように、FARO SCENEだけでなく、ReCapやCloudCompareなどの外部ツールを適切に使い分けることで、FLSデータの活用範囲は大きく広がります。プロジェクトの規模や目的に応じて、柔軟なワークフローを構築していきましょう。
4. FLS点群データの活用シーン
FLS形式で取得された点群データは、さまざまな業界で幅広く応用できる可能性を秘めています。高精度な3Dスキャンにより、現場の状況を短時間で立体的に把握できるため、計画立案から施工、記録・保存まで、あらゆるプロセスに役立てることができます。
点群データの大きな強みは、従来の2D図面では見落とされがちな空間の微細な形状や寸法を、3次元で詳細に記録できる点にあります。これにより、建設・土木をはじめとする分野では、設計精度の向上や工事の手戻り防止につながる重要な判断材料として活用が進んでいます。一方で、データ容量の大きさや処理の複雑さを考慮すると、活用には適切なソフトの選定やフロー構築が欠かせません。
ここでは、FLS点群データをどのような業務シナリオで活用できるのかについて、代表的なケースをいくつか紹介します。現実の作業に当てはめながら、「どこで使えるか」「どんな効果が期待できるか」をイメージしやすくすることを目的としています。
4.1. 建設・土木分野における活用シナリオ
建設・土木業界では、FLS点群データを活用することで、業務全体の流れに大きな変化がもたらされることが期待されます。以下のようなシナリオが考えられます。
たとえば、プロジェクトの初期段階で現場をFAROスキャナーでスキャンし、地形や既存構造物の状況を点群として記録。そのデータをもとに、設計担当者が建物の配置や高さを検討し、より現実的なプランニングを進めることができます。
施工段階では、工程ごとに現場の状況をスキャンし、設計データと照合。進捗確認や出来形の比較、誤差のチェックが効率よく行えるようになります。現場の変化を定期的に可視化することで、関係者間での情報共有もスムーズになり、意思決定のスピードアップにつながります。
さらに、改修や増築といった場面でも、FLS点群データが活躍します。既存建物の正確な寸法を事前に把握し、それに基づいて新しい設備や構造物を設計すれば、図面との不一致を防ぎ、工事の段取りも明確になります。
このように、FLS形式で取得した点群データは、計画・施工・検査といった工程ごとに活用できるだけでなく、業務の透明性と品質を高める手段としても有効です。導入初期は操作や管理に学習が必要ですが、ワークフローに組み込むことで、着実な効果が期待できます。
4.2. BIM・デジタルアーカイブへの応用シナリオ
FLS点群データは、BIM(Building Information Modeling)やデジタルアーカイブの分野でも、今後の業務変革を支える重要なリソースとなり得ます。以下のようなシナリオが代表的です。
まず、既存施設の維持管理や更新計画を立てる場面では、FLSで取得した点群データをBIMモデルのベースとして取り込みます。実際の寸法や空間構成を忠実に反映した3Dモデルを作成することで、干渉チェックや改修設計のシミュレーションがより現実的かつ効率的に進められます。
また、公共施設やインフラの統合管理においても、点群を活用したBIMとの連携は有効です。例えば、維持管理記録をBIMに紐づけ、設備更新時の判断材料にしたり、将来の災害リスク評価にも役立てることができます。
一方、文化財や歴史的建造物の保存においては、FLS点群データによる高精度なスキャンが、後世への「デジタル記録」として活用されます。損傷箇所の進行状況を定期的に記録したり、将来的な修復設計の下地とすることができるほか、教育・展示・研究目的で3Dデータを活用することも可能です。
このようなシナリオでは、FLSデータが単なる図面や写真に代わる「空間情報のアーカイブ」として機能し、未来への資産価値を持つデータとして活躍します。BIMやアーカイブと連携することで、点群の利用価値はさらに高まり、多様な現場ニーズに応えることができるようになります。
5. FLSファイルを扱う際の注意点とTIPS
FLSファイルを活用する上で、機能やメリットに注目しがちですが、実際の運用では「容量の大きさ」と「精度の管理」に特に注意が必要です。点群データは非常に情報量が多いため、取り扱いを誤ると作業の効率が落ちたり、重要な情報を失ってしまうリスクもあります。特に初心者の場合、知らないうちに作業負荷が高まっていたり、精度のズレに気づかないまま進めてしまうこともあるので、事前の理解と対策が重要です。
たとえば、1つの現場で取得したFLSファイルが数十GBを超えることは珍しくありません。処理や保存を適切に行わないと、作業中にフリーズしてしまったり、最悪の場合はデータが破損するリスクもあります。また、精度の面では、スキャナーの設置位置や基準点の測量精度がそのまま最終データの正確性に直結するため、撮影時の計画と管理体制が重要になります。
ここでは、FLS点群データを実務で扱う上で押さえておきたい「容量管理」と「精度管理」に関する実践的なTIPSを紹介します。普段の作業の中で少し意識を変えるだけで、データの安定性や作業効率が大きく向上します。点群データの扱いにまだ慣れていない方も、以下の内容を参考に、トラブルを未然に防ぎながらFLSを活用していきましょう。
5.1. 容量が大きい!管理と保存の工夫
FLSファイルは、スキャン範囲が広がるほど急激にデータ量が増えていく傾向があります。特に高密度・高精度なスキャンを行った場合、ファイルサイズが数GBから数十GBに達することもあり、扱いには工夫が必要です。こうした大容量ファイルを安全かつ効率的に運用するためには、ストレージの選定とデータ保存のルール作りがカギになります。
まず、日常的な作業で使用するストレージとしては、HDDよりもアクセス速度の速いSSD(ソリッドステートドライブ)がおすすめです。FLSファイルの読み込みや表示処理にはかなりのディスク性能が求められるため、SSDに保存することで作業全体がスムーズになります。ただし、SSDは容量あたりの価格が高いため、長期保存には大容量HDDや外部クラウドストレージを活用するのが現実的です。
また、頻繁に使う作業用データと、アーカイブ目的の保存データを分けて管理することで、ストレージの効率的な運用が可能になります。作業終了後には定期的なバックアップも欠かせません。重要な点群データが誤って削除されたり、破損した場合に備えて、冗長性を持たせた保管体制を整えておくと安心です。
さらに、容量圧縮についても検討しましょう。点群データはZIPなどの圧縮形式で保管することも可能ですが、使用頻度が高いファイルには非圧縮のままアクセスできるようにしておくのが理想です。圧縮ファイルは展開に時間がかかるため、作業効率を優先するなら、使用目的に応じて「圧縮するか・しないか」を選ぶようにしましょう。
最終的には、プロジェクトの開始時から終了後のアーカイブまでを含めたデータ管理体制を構築することが大切です。点群データは長期にわたって保管・再利用されるケースも多いため、使いやすさと安全性のバランスをとった保存環境を整えることが、安定した活用につながります。
5.2. 精度・位置情報に注意!正確な活用のために
FLSファイルを正しく活用するためには、「精度」と「位置情報」の管理が欠かせません。3Dレーザースキャナーは非常に高精度な計測が可能な反面、その正確性はスキャナーの設置方法や基準点の取得状況に大きく左右されます。わずかなズレが最終的な設計や分析結果に大きな影響を与えるため、精度管理には特に注意を払う必要があります。
たとえば、現場で複数のスキャンを行う場合、それぞれのスキャナー設置位置が正確に計測されていないと、複数の点群を統合(レジストレーション)する際に誤差が蓄積し、最終的に不正確な3Dモデルとなってしまう恐れがあります。施工現場や構造物の高さ・傾きなどを評価する際には、数ミリの誤差でも無視できないケースがあるため、スキャン計画は慎重に立てるべきです。
このようなズレを防ぐためには、まず測量基準点の精度をしっかり確保し、スキャナーと座標系の整合性を保つことが重要です。特に公共工事や測量業務では、国土地理院が定めた平面直角座標系などと照らし合わせた測定が求められることもあります。広範囲をスキャンする場合や高低差のある現場では、複数地点でオーバーラップさせながらスキャナーを設置し、統合時のズレを最小限に抑える工夫も必要です。
また、FARO SCENEなどのソフトウェアには、統合誤差の確認や標準偏差の表示といった機能も備わっているため、作業中に精度を確認しながら進めることが可能です。こうしたチェック機能を活用すれば、後から問題が発覚するのを防ぎ、作業の信頼性を高めることができます。
精度管理は、FLS点群データを設計や検証に活かすうえでの土台となるものです。プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、こうした基本的な注意点を守ることが成果の質を大きく左右します。正確な位置情報の取得と、点群同士の整合性を意識した作業を心がけましょう。
6. まとめ:FLSの理解が点群活用の第一歩
この記事では、FARO社の3Dレーザースキャナーで取得される「FLSファイル形式」について、点群データの基本からツール選定、活用方法、注意点までを幅広くご紹介してきました。
FLSファイルは、スキャン位置、反射強度、カラー情報などを高精度に保持できる点で優れたフォーマットです。FARO SCENEを使えば、読み込みや統合、ノイズ除去といった処理もスムーズに行えます。ただし、FLSはFARO独自の形式であるため、他のソフトで扱うにはE57やLASなどの汎用形式に変換する必要があります。
その一方で、FLSデータをReCapやCloudCompareといった外部ツールに取り込むことで、BIMとの連携や点群比較、デジタルアーカイブなど、活用の幅が一気に広がります。実際、建設現場での出来形管理や文化財保存、施設管理といった多様な分野で、FLS点群データは着実に存在感を高めています。
また、FLSファイルは容量が大きく、精度や位置情報の管理も重要です。だからこそ、データ保存やバックアップ、スキャン精度の確保といった基本を押さえておくことが、トラブルを防ぎ、安定した活用につながります。
点群データに初めて触れる方も、まずはFLSという形式を理解し、FARO SCENEなどを使って3D空間を可視化してみることで、「空間を記録し、活用する」という技術の可能性を実感できるはずです。そこから、目的に応じてツールを使い分けたり、BIMやGISと組み合わせてみたりと、応用の幅はどんどん広がっていくでしょう。
FLS点群データは、単なるファイル形式の一つではなく、これからの空間情報活用を支える重要な基盤のひとつです。ぜひ本記事をきっかけに、点群データの扱い方を学び、業務や研究、プロジェクトの質をさらに高めていってください。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
FARO® SCENE 3D点群データソフトウェア|FARO
https://www.faro.com/ja-JP/Products/Software/SCENE-Software
Home – FARO®ナレッジベース
https://ja-knowledge.faro.com/
Autodesk ReCap Pro ソフトウェア | ReCap Pro 2026 正規品の価格と購入
https://www.autodesk.com/jp/products/recap/overview
CloudCompare – Open Source project
E2807 3D画像データ交換標準仕様、バージョン1.0(英語)