ソリッドキャムでできるコンター加工とは?初心者向けにやさしく解説
1. はじめに
ソリッドキャム(SolidCAM)は、設計データからツールパスを作成し、シミュレーションで確認してNCコードを出力できる統合型CAMです。SOLIDWORKSと同じ環境で操作できるため、プロ向けながらも画面構成や操作手順がわかりやすく、初めてCAMに触れる方でも学びを進めやすいのが特長です。主なユーザーはCAMプログラマや加工技術者ですが、設計と製造をつなぎたい設計者・工業デザイナーにも有用です。
本記事のテーマはコンター(輪郭)加工。外形仕上げや金型の輪郭、ポケット外周の仕上げなど、製品の見た目と寸法精度を左右する重要な工程です。SolidCAMには、2.5Dの「Profile」、3D仕上げの「Contour/Constant Z」など、輪郭系のストラテジが揃っており、用途に応じた使い分けが可能です。
この記事では、機械加工に不慣れな方でも理解しやすいように、コンター加工の基本概念→SolidCAMでの操作の流れ→よく使う設定→つまずきやすいポイントと解決策の順にやさしく解説します。読み終えるころには、まずは2Dコンターから安全に試し、シミュレーションで確認しながら実務へ活かせる土台が身につくはずです。
2. ソリッドキャム(SolidCAM)の基本理解

SolidCAMは、CADで設計したデータからツールパスを自動生成し、その動作をシミュレーションで確認したうえでNCコードを出力できる効率的なCAMソフトです。設計と加工を一つの環境で完結できる統合型の仕組みを備えており、操作画面は直感的でわかりやすく、初心者にとっても取り組みやすい点が魅力です。
さらに、金型や複雑形状の部品加工にも対応しているため、外形仕上げやポケットの外周仕上げといった多彩な加工に利用できます。これにより、設計データを基にツールパス生成からシミュレーション、NCコード出力までを一貫して実行できるため、高精度な仕上がりと加工効率の向上を同時に実現できます。
2.1. SolidCAMとは何か?
SolidCAMは、製造業の現場で広く利用されているCAMソフトで、CADデータと直接連携しながら工具や加工パラメータを設定できるのが特長です。プロ仕様でありながらユーザーインターフェースがシンプルで、一度作成した加工工程を別の部品に応用しやすい柔軟性も備えています。そのため、熟練者はもちろん、学習中のユーザーにとっても扱いやすい環境といえるでしょう。
また、SolidWorksとの連携機能により、設計段階での変更がそのまま自動的に加工データへ反映されるため、再プログラムの手間を大幅に削減できます。設計変更が多い開発プロセスでも効率的に対応できるのは大きなメリットです。
さらに、切削シミュレーション機能が標準搭載されており、実際の加工動作を視覚的に確認できます。これによって工具干渉や段差の発生を事前に検出でき、作業の安全性と精度を高めることが可能です。初心者から上級者まで幅広く活用できる点が、SolidCAMの強みといえるでしょう。
2.2. SolidCAMの主な機能と利点
最初の大きな利点は、豊富な加工モードに対応していることです。フェースミル、ドリル、ポケット加工などの基本的な切削に加えて、2Dコンターや3Dコンターといった輪郭加工も幅広くサポートしており、単純な外形仕上げから複雑な曲面の加工まで柔軟に対応できます。
また、加工パラメータ設定ではウィザードやテンプレートを利用できるため、加工深さやステップオーバーといった数値を段階的に学びながら設定できます。仕上げ代や工具補正などの細かい条件も用意されているため、初心者が失敗を避けつつ実践的な知識を身につけやすい点も魅力です。
さらに、NCコード出力までの一連の流れがシステム内で統合されているため、モデル選択からツールパス生成、シミュレーション確認までをスムーズに進められます。結果として学習コストを抑えながら、実際の製造現場で即活用できる効率的なワークフローを実現できるのが、SolidCAMの大きな強みといえるでしょう。
3. コンター加工の基礎知識
コンター加工とは、製品の輪郭に沿って工具を移動させ、外形や内形を正確に削り出す加工手法のことです。製品の外周はもちろん、溝の側壁や段差の仕上げにも活用できるため、幅広い場面で利用されるのが特徴です。
さらに、CADデータ上で定義された曲線や複雑な形状を正確にツールパスへ反映できるため、金型の輪郭加工や筐体部品の側面加工などにも多用されます。初心者にとっては、いくつかの基本用語や考え方を理解するだけで、すぐに実践へ移行できるのもコンター加工の魅力といえるでしょう。
3.1. コンター加工とは?
「コンター加工」という名称は、英語の Contour(輪郭) に由来します。文字通り、製品の輪郭に沿って工具を走らせ、設計通りの形状に切削していく加工方式です。工作の現場では、2次元の外形加工から複雑な曲面を含む3次元加工まで、幅広い範囲で利用されています。
この加工で重要になるのが輪郭線を正確にトレースするためのツールパス生成です。SolidCAMでは、ツールパスを自動生成する豊富な機能が備わっており、初心者でも迷わず段取りを組み立てられるよう工夫されています。
また、外形仕上げで製品の外観品質が問われる部品では、コンター加工の精度が仕上がりに直結します。工作機械の性能と組み合わせることで、最終的なクオリティを高められるため、コンター加工の基礎を理解しておくことは非常に重要です。
3.2. コンター加工の主な用途
代表的な活用例としては、金型の輪郭加工、部品の外形仕上げ、そしてポケットの外周仕上げが挙げられます。金型加工では曲線や複雑形状が多く登場するため、コンター加工によって滑らかな輪郭を再現できる点が大きな利点です。
また、外形仕上げでは製品の枠組みを正確に整えるため、見た目の美しさや寸法精度に直接影響します。ポケット外周仕上げの場合は、内側に掘り込んだくぼみの側面をきれいに仕上げるのに適しています。
このように、コンター加工は最終的な仕上がりを左右する重要な工程です。SolidCAMのシミュレーション機能を活用すれば、実際の切削イメージを事前に確認しながら、最適な加工手順を組み立てることが可能になります。
3.3. 2Dと3Dコンター加工の違い
2Dコンター加工は、主にXY平面上での外周や内周の輪郭を削るのが特徴です。板状の部品や単純な外形仕上げ、ポケットの側壁加工などに適しており、初心者でも操作しやすい加工方法といえます。SolidCAMでは工具設定画面から簡単に始められる点も利点です。
一方、3Dコンター加工(HSMのContourやConstant Z仕上げなど)は、Z方向の動きを組み合わせて曲面や段差を仕上げるのに用いられます。複雑な立体形状や金型加工に対応でき、滑らかな表面を得たい場合に最適です。ただし、加工深さやパラメータの設定を細かく調整する必要があるため、より繊細な操作が求められます。
どちらを選ぶかは、製品設計や求められる精度によって変わります。SolidCAMは2Dと3Dの両方に対応しており、モードを簡単に切り替えて多様な加工に適用可能です。なお、2.5Dの外形加工は「Profile」、3D仕上げは「Contour」や「Zレベル」などの名称で提供されており、用途に応じた使い分けができます。
4. ソリッドキャムでのコンター加工の流れ
SolidCAMでコンター加工を行う際は、一般的に「モデルの読み込み」から始まり、「工具設定」「加工条件の入力」「ツールパス生成」「シミュレーション確認」という一連の手順を踏みます。特に初心者にとっては、流れを順序立てて理解し、実際に操作しながら確かめることが学習効果を高めるポイントです。
ここでは、加工準備からモード選択、ツールパスの作成、そしてシミュレーションによる検証までのプロセスを順を追って解説します。手順が整理されていれば、初めての作業でも迷いが少なく、安心して実践に取り組めるようになります。
4.1. 加工準備:モデルと工具の選択
最初のステップは、加工対象となるCADデータをSolidCAMに読み込むことです。SolidWorksなどで作成した3Dモデルを直接読み込めるため、余計な変換作業は不要です。さらに、必要に応じて座標系や加工原点を設定し、基準点を正しく決めておきます。モデル選択が不完全だと正しいツールパスが生成されないため、データ確認を丁寧に行うことが大切です。
続いて工具の設定を行います。エンドミルやボールエンドミルなど、対象となる形状に適した工具を登録し、工具径や工具長を正しく入力します。ここでのミスは干渉や段差の発生につながるため、注意が必要です。
また、素材の種類や硬度によって適切な回転数や送り速度が異なります。メーカーが推奨する切削条件を参考にしながらパラメータを設定しておくと、後の工程でのトラブルを防ぎやすくなります。こうした事前準備がスムーズなツールパス生成と高品質な仕上がりに直結します。
4.2. コンター加工モードの選択と設定
次に行うのは加工モードの選択です。SolidCAMの画面には、2Dコンター、3Dコンター、さらには多軸加工まで選択できる項目が整理されています。初心者の場合は、まず2Dコンターを選び、外形仕上げやポケット外周の仕上げといった基本的な加工から取り組むのがわかりやすいでしょう。
設定する項目には、加工深さ、ステップオーバー、残し代といった基本的なパラメータが含まれます。例えば、加工深さを大きくしすぎると工具に過度な負担がかかり、浅すぎると加工時間が無駄に長くなります。バランスを意識して数値を設定することが重要です。
さらに、切削の開始位置や退出方法を制御する「リードイン/リードアウト」の設定も欠かせません。SolidCAMでは各パラメータにラベルと解説が付属しており、初心者でも理解しやすい仕様になっています。条件を比較しながら最適な設定を選べる点は大きな利点です。
4.3. ツールパスの生成とシミュレーション
すべての条件を入力し終えたら、ツールパスを生成します。SolidCAMが自動的に切削経路を計算し、画面上にわかりやすい軌跡として表示します。もし誤って別の輪郭を選択していると、工具が想定外の動きをするため、生成後には必ずプレビューで経路を確認しましょう。
続いてシミュレーションを実行し、工具の動作をアニメーションで確認します。これにより、実際の切削がどのように進むかを視覚的に把握でき、干渉や段差の有無を事前に検出できます。問題がなければ、NCコードを出力し、実機での加工に移行します。
特に初心者の場合は、少しの条件変更であっても必ずシミュレーションを回す習慣をつけることが大切です。事前に動作を検証しておけば、予期せぬトラブルを大幅に減らし、安全かつ効率的な加工が実現できます。
5. コンター加工でよく使うパラメータ
コンター加工には多くのパラメータが存在しますが、特に重要なのは「加工深さ」「ステップオーバー」、そして仕上げに大きく関わる「残し代」と「工具補正」です。これらを適切に設定できないと、工具への負担増大や加工時間の無駄、仕上がり精度の低下につながってしまいます。
ここでは、初心者でも必ず押さえておきたい主要なパラメータについて、理論面と実務面の両方から解説します。基本を理解すれば、効率よく加工しながら高精度な仕上がりを実現するためのバランスを取りやすくなるでしょう。
5.1. 加工深さとステップオーバー
加工深さとは、Z方向にどのくらいの厚みを一度に切削するかを示す値で、コンター加工の負荷を大きく左右します。通常は工具径や素材の硬さを考慮し、無理のない深さに設定するのが基本です。特に硬質素材を加工する場合は、一度に深く削らず、数回に分けて段階的に切り込むことで、工具寿命を延ばし、仕上がり品質を安定させられます。
ステップオーバーは、工具がX-Y平面上でどの程度の幅を重ねながら進むかを決める値です。大きめに設定すると加工時間は短縮できますが、切削抵抗が増え表面が粗くなるリスクがあります。逆に小さすぎると表面はきれいになりますが加工時間が極端に延びてしまいます。したがって、効率と品質の両立を考えた最適値を探すことが重要です。
実際の現場では、工具補正や素材の特性を考慮して深さとステップオーバーを調整します。SolidCAMでは、よく使う条件をテンプレートとして保存・再利用できるため、一度確立した加工条件を次のプロジェクトに効率的に適用できます。さらに、「iMachining」のTechnology Wizardを使えば、素材や工具の情報から最適な切削条件を自動で提案してくれるため、初心者でも安心して設定が行えます。
5.2. 残し代と工具補正の理解
残し代とは、仕上げ加工のために意図的に残しておく素材の厚みを指します。サイド面や底面に0.1〜数ミリ程度設定することが多く、荒加工の後にわずかに残しておくことで、仕上げ時にきれいな表面を得やすくなります。特にコンター加工では外周の精度が重要となるため、残し代の設定は仕上がりを左右する大切な要素です。
一方、工具補正とは、実際の工具径とプログラムで指定した工具径の差を補正するための仕組みです。右補正や左補正を選択して工具経路を微調整することで、図面通りの寸法精度を確保できます。SolidCAMではツールパスのオフセット計算に加え、NC側での半径補正(例:G41/G42)を利用することも可能です。ただし、工具の摩耗やメーカーごとの工具差は考慮して設定を見直す必要があります。
これらのパラメータを正しく理解し、状況に応じて調整できれば、加工の精度と効率の両方を高められます。残し代と工具補正は、見た目の美しさと寸法精度を守るための基本条件ともいえるため、初心者のうちから確実に身につけておくことが重要です。
6. つまずきやすいポイントと解決策
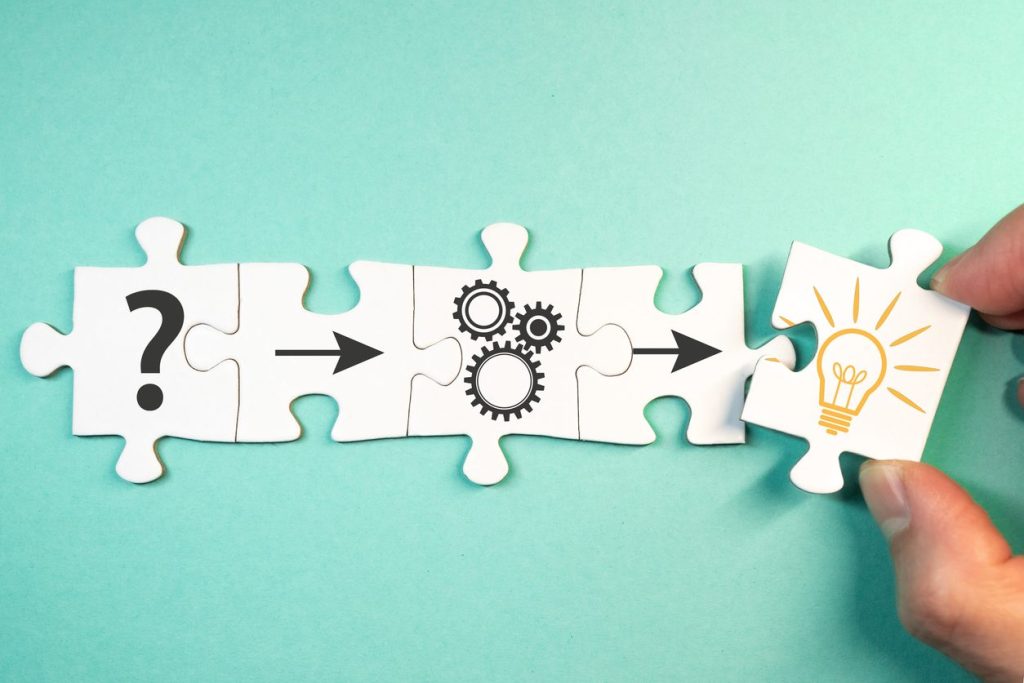
コンター加工は比較的取り組みやすい方法ですが、実際に操作してみると「ツールパスがうまく作れない」「工具が干渉する」といった思わぬ問題に直面することがあります。これらのトラブルは、加工深さの設定やスケッチの不備など、基本的な要素が原因であることが多いです。
ただし、SolidCAMには分かりやすいエラーメッセージやシミュレーション機能が搭載されているため、落ち着いて確認すれば大きな失敗を防ぐことができます。ここでは、初心者がつまずきやすい典型的なケースと、その解決策を解説します。
6.1. ツールパス生成の問題点と対処法
よくあるトラブルのひとつが、ツールパスが生成されない、あるいは期待していた外周を削ってくれないといったケースです。原因の多くは、モデルの輪郭が完全に閉じていなかったり、スケッチが不完全なままチェーンを認識していることにあります。
この場合は、まずSolidWorks側でスケッチを再確認し、輪郭がしっかり結合されているかをチェックします。同時に、不要な線分や重複線が残っていないかも確認することが重要です。SolidCAM側ではチェーン定義をやり直し、明確に外形を指定することでツールパスが正しく作成されやすくなります。
また、素材や工具パラメータに適さない設定が原因で、ツールパス生成時にエラーが出る場合もあります。特に深さや送り速度を過大に設定すると異常停止につながるため、最初は控えめな値でツールパスを作成し、徐々に最適化していくのがおすすめです。
6.2. 工具の干渉と段差の問題解決
工具干渉とは、ツールパスが材料以外の部分に触れてしまう現象で、最悪の場合は機械の故障やワークの破損を引き起こすリスクがあります。特に3Dコンター加工のように形状が複雑な場合に発生しやすいため、SolidCAMに搭載されている干渉チェック機能を必ず利用して検証することが大切です。
また、「段差の問題」と呼ばれる現象も初心者がよく直面するトラブルです。これは、本来平滑であるべき面に段状の痕跡が残ってしまうもので、ステップオーバーの設定不足や工具補正の不備、Z方向の切り込みが不均等であることが原因となります。原因を見極めるには、加工シミュレーションを再生し、ツールの動きを細かく観察するのが効果的です。
解決策としては、まずステップオーバーを適切な値に調整し、切削層の重なり具合をきちんと管理することが有効です。さらに、工具干渉を避けるためには、2Dコンター加工では工具径補正を正しく設定し、3Dコンター加工ではSolidCAMの干渉検出機能を活用して事前に確認することが欠かせません。これらの対応を徹底することで、トラブルを大幅に減らし、安定した加工を実現できます。
7. コンター加工のメリット
コンター加工は、製品の外観や機能に直結する輪郭部分を高精度に仕上げられるため、幅広い製造現場で欠かせない工程となっています。SolidCAMと組み合わせることで、初心者でも短期間で操作を理解し、実務に取り入れることが可能です。
ここからは、コンター加工の具体的なメリットとして「作業効率の向上と自動化」と「高精度な仕上がりと失敗リスクの低減」という2つの観点から解説し、初心者が抱きやすい疑問や不安を解消していきます。
7.1. 作業効率の向上と自動化
コンター加工は形状が複雑に見えても、輪郭線を正しく定義できれば、CAMソフトが自動生成するツールパスを活用して短時間で仕上げることが可能です。特に複数の部品を同時に扱う場合、SolidCAMに搭載されている工程テンプレート(Process Template)といった自動化機能を利用することで、類似形状の部品をまとめて効率的に設定できます。
さらに、ツールパス生成にかかる手間が少なく済むため、加工実行までの段取り時間を大幅に削減できます。初心者向けのチュートリアルで基本操作を習得し、自分で設計した部品を素早く仕上げられるようになれば、社内での提案やクライアントへの提示もスムーズに進められるでしょう。
また、コンター加工の工程を標準化し、工具や加工条件をテンプレートとして保存しておけば、新人や別の担当者でも一定の品質を維持したまま作業できます。その結果、作業効率の向上だけでなく、総合的なコストパフォーマンスの改善にもつながります。
7.2. 高精度な仕上がりと失敗リスクの低減
コンター加工は、製品の最終形状を決める重要な仕上げ工程です。工具の動きを細かく制御することで、寸法精度の高い切削が実現でき、外観品質の向上にも直結します。SolidCAMのシミュレーション機能を適切に活用すれば、段差の発生や削り残しといった不具合を事前に確認でき、実加工前にリスクを回避できます。
失敗を防ぐためには、干渉検出(Collision Control)の利用が有効です。特に多軸加工では衝突回避設定を組み込めるため、複雑なツールパスを手動で計算する必要がなく、初心者でも安心して加工に挑戦できます。
さらに、仕上げ代をあえて少し残しておき、最終段階で微量の素材だけを削る方法を取れば、表面粗さの改善や美しい仕上がりが得られます。これにより、量産前の試作や新しい製品開発の立ち上げにおいてもスムーズに進行でき、高品質な部品を短期間で提供できるようになるのです。
8. まとめ
本記事では、コンター加工の基本概念からSolidCAMを使った具体的な手順、さらに初心者がつまずきやすいポイントとその解決策までを幅広く解説してきました。内容をひととおり理解すれば、初心者の工業デザイナーやエンジニアであっても、適切にモデルを選択しツールパスを生成するだけで、外形仕上げや金型輪郭加工といった代表的な作業を問題なくこなせるようになるはずです。
最初の一歩としては、自分の業務に合ったシンプルな2Dコンター加工から始めるのがおすすめです。そのうえで慣れてきたら、より高度な3Dコンター加工へとステップアップしていきましょう。加工深さやステップオーバー、工具補正といった主要なパラメータを少しずつ調整し、必ずシミュレーションで結果を確認する習慣をつければ、知識が経験として定着していきます。
こうした段階的な学習と実践を積み重ねることで、SolidCAMをフルに活用できるようになり、加工効率の向上と製品精度の両立を実現できるでしょう。今日から小さなステップを踏み出し、自分の設計と製造に役立ててみてください。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
ホーム – SolidCAM
SOLIDWORKS CAM | SOLIDWORKS












