Civil 3Dで扱うDMデータとは?CIM対応に必須の基本と活用法をやさしく解説
1. はじめに|Civil 3DとDMデータの関係を理解しよう
近年、土木設計の分野では「DMデータ」という言葉を耳にする機会が増えています。
DMデータとは、設計に必要な形状や属性情報を立体的にまとめた3D設計モデルのことを指し、国土交通省が推進するCIM(Construction Information Modeling)でも重要な要素として位置づけられています。
これまでの2D図面中心の設計では、平面・縦断・横断を個別に管理していましたが、DMデータを用いることで、一つの3Dモデルに全ての情報を集約できます。その結果、干渉チェックや設計変更への対応がスムーズになり、設計品質と作業効率の両方を高めることが可能です。
こうした3D設計の流れの中心にあるのが、Autodesk社のCivil 3Dです。
Civil 3Dを使えば、道路や河川、構造物などのDMデータを効率的に作成できるだけでなく、CIM対応の納品データとしても活用できます。3Dモデルによる設計の「見える化」は、合意形成や施工段階での情報共有にも大きな力を発揮します。
本記事では、DMデータの基本概念からその役割、そしてCivil 3DでDMデータをどのように作成・活用するかまでを、初心者にもわかりやすく解説します。CIM対応や3D設計の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、「DMデータ」という呼称は実務で広く使われていますが、国土交通省の公式文書では「3次元モデル成果物」または「設計モデル(Design Model)」と表記されています。本記事では理解を優先し、「DMデータ」という用語で統一しています。
2. DMデータとは?基本概念と役割をやさしく解説
2.1. DMデータの定義とは何か?
DMデータとは「Design Model(デザインモデル)」の略で、土木設計における形状データに加え、属性やメタデータなどの情報を一体化した3D設計成果物を指します。
国土交通省がCIM(Construction Information Modeling)の普及を進めるなかで、DMデータの標準化も進展しており、道路の線形、橋梁、河川構造物など、さまざまな要素を一つのモデルに統合できる点が特長です。
このDMデータを活用することで、従来の2D図面では表現しきれなかった法面の勾配や土量、構造形式、材料情報なども、1つの3Dモデルに付与することができます。
たとえば、車道・歩道の幅員、横断勾配、側溝形状といった要素を立体的に管理でき、設計変更が発生した際も関連データを自動的に更新できます。
DMデータは単なるCADモデルではなく、土木設計の精度を高めるための「情報を結びつける新しい設計モデル」といえます。これにより、設計・施工・維持管理の各段階で一貫した情報活用が可能になります。
2.2. DMデータの国交省における位置づけ
国土交通省では2012年からCIMの試行導入を開始し、2023年度からは「BIM/CIMの原則適用」が全ての工種に拡大されました。
これは「全ての設計を3次元化する」という意味ではなく、発注者が定める活用目的に応じて、必要な範囲で3次元モデル(3次元モデル成果物)を作成・活用するという方針を示しています。
背景には、設計から施工、維持管理までを通じて効率化と品質向上を図る目的があります。2D図面では把握しづらかった干渉箇所の検出や工程管理が、3Dモデルを用いることで事前に確認できるようになり、手戻りの防止や設計精度の向上につながっています。
さらに、国交省が公開している「設計成果の3次元モデル化要領(案)」では、モデルに付与すべき属性情報の種類やデータ構成が具体的に示されています。これに準拠して作成すれば、発注者による検査や納品がスムーズに進み、設計内容のトレーサビリティ(履歴の把握)も確保できます。
また、DMデータの対象は地形や線形だけではなく、道路に付随する構造物モデル(例:箱型カルバート、橋台、擁壁など)にも広がっています。こうした複合構造物の3Dモデル化において、Civil 3Dは重要な役割を果たしています。
2.3. 3D設計とBIM/CIMにおけるDMデータの重要性
3D設計の目的は、単に図面を立体的に見せることではありません。
BIMやCIMが目指しているのは、すべての設計情報を一つの3Dモデルに統合し、関係者全員が同じデータをもとに判断できる環境を整えることです。DMデータはその中心に位置し、計画から施工、維持管理までのプロセスをシームレスにつなぐ「情報のハブ」となります。
DMデータをしっかり構築しておけば、施工計画や積算精度の向上、工程の可視化が容易になります。
モデル内で寸法や数量を直接確認できるため、設計変更時にも自動更新が可能で、再作図や数量再計算の手間を大幅に削減できます。
このように、DMデータは土木分野における情報共有の効率化と設計品質の向上を支える基盤といえるでしょう。
Civil 3Dは、このDMデータを体系的に作成・管理し、他ツールとも連携できるプラットフォーム的存在として活用されています。
2.4. 2D図面とDMデータの違い
従来の2D図面は、設計情報を平面・縦断・横断など個別の図面で表現しており、全体像を直感的に把握するのが難しいという課題がありました。
一方、DMデータを用いると、1つの3Dモデルでこれらの情報を統合でき、地形の起伏や法面勾配、構造物の配置関係を立体的に把握できます。
また、近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れの中で、合意形成やプレゼンテーションの段階から3Dモデルを活用するケースも増えています。DMデータはそのまま可視化ツールやシミュレーションツールに転用でき、関係者間の理解を深めやすい点も大きなメリットです。
このように、2D図面では見落としがちな要素をDMデータで補完することで、設計の精度や説明力が飛躍的に高まります。
2Dから3Dへの移行は、もはや選択肢ではなく、これからの土木設計における新たな標準となりつつあります。
3. Civil 3Dで扱うDMデータの構成要素
3.1. 代表的なDMデータの例とその作成方法
Civil 3Dでは、DMデータとしてさまざまな要素を作成できます。中でも最も基本となるのが地形モデルです。
これは「TINサーフェス(Triangulated Irregular Network)」と呼ばれる三角形メッシュ構造を用いて、地形の起伏や標高の変化を正確に再現するものです。
このTINサーフェスは、点群データや測量データをもとに自動的に生成されます。大量の観測点を取り込み、Civil 3Dが三角形を相互に接続して一体の地形モデルを構築します。
完成した地形モデルを活用すれば、高さ情報をもとにした設計計画の検討や、土量計算・断面図の自動作成などが容易になります。
さらに、道路や河川といった線形要素のアラインメント(中心線)、縦断方向のプロファイル(縦断線形)、そしてこれらをもとに構築されるコリドーモデル(道路本体の3Dモデル)を組み合わせることで、Civil 3Dでは一連のDMデータを体系的に作り上げることができます。
これらの要素が連動することで、3D設計の精度が高まり、変更にも柔軟に対応できるデータ構造が完成します。
3.2. 重要なメタデータと属性情報
DMデータの真価は、形状の3D化だけではなく、設計意図や仕様を正確に伝える属性情報(メタデータ)をどれだけ付与できるかにあります。
たとえば道路設計モデルでは、幅員、路肩の種類、舗装材料、勾配、安全施設の仕様など、多様な情報をメタデータとして登録します。
Civil 3Dでは、各オブジェクトに対して「Property Set(プロパティセット)」を設定でき、設計者が意図する情報をオブジェクト単位で紐付けることが可能です。
こうして登録した属性情報は、設計段階だけでなく、施工計画や維持管理フェーズでも活用できるため、長期的なデータ資産として機能します。
このように属性情報をしっかり整備することで、たとえば「撤去対象の構造物」と「存置すべき施設」を一覧で把握したり、数量積算を自動で行ったりすることもできます。
DMデータは単なる3D形状の集合体ではなく、土木設計に関する情報を網羅的に格納する“デジタル設計帳票”とも言える存在です。
3.3. サポートされるファイル形式の概要
Civil 3Dで作成したDMデータを納品成果物として活用するためには、ファイル形式の理解と選定が欠かせません。代表的な形式には、DWG、LandXML、IFCなどがあります。
DWG形式はCivil 3Dのネイティブデータ形式であり、設計モデルを完全な状態で保持できます。ただし、他のソフトウェアで開く場合、Civil 3D特有のオブジェクトが正しく表示されないことがあるため、LandXMLやIFC形式に変換して共有するケースが多く見られます。
LandXML形式は特に道路や河川分野で広く利用されており、アラインメント(中心線)、プロファイル(縦断線形)、TINサーフェス(地形モデル)などの情報交換に最適です。
一方、IFC(Industry Foundation Classes)形式は、BIM/CIMの国際標準規格として定められており、土木構造物を含む「IFC 4.3」規格が整備されています。
Civil 3Dでは、「IFC 4.3 Import and Export Extension for Civil 3D」(Civil 3D 2022以降対応)を追加インストールすることで、IFCファイルのエクスポートおよびインポートが可能になります。
この拡張機能は、Autodesk公式サイトまたはAutodesk Accountから入手できます。
これらのファイル形式を適切に使い分けることで、Revit、InfraWorks、Navisworksなどの他のBIM/CIMソフトとのデータ連携がスムーズになり、3D設計データの共有性・再利用性を大幅に高めることができます。
4. Civil 3DでDMデータを作成する基本ステップ
4.1. 初期データの取り込みとサーフェス作成
最初のステップは、設計対象となる現況地形を正確に把握することです。そのために、点群データや測量結果をCivil 3Dに取り込む作業から始めます。
ただし、LAS形式の点群データはCivil 3Dに直接読み込むことができません。まずはAutodesk ReCapを使用して、RCP(プロジェクトファイル)またはRCS(スキャンファイル)形式に変換し、そのファイルをCivil 3Dにリンクまたは読み込みます。
ReCapで事前にノイズ除去や不要点の削除を行っておくと、サーフェス生成時の精度が安定します。変換段階でデータを整理しておくことで、後の作業がスムーズに進みます。
Civil 3D上でTINサーフェス(Triangulated Irregular Network)を作成したら、標高や斜面を色分け表示して地形の凹凸や勾配を可視化し、地形特性を確認しましょう。
サーフェス作成時には、座標系や単位系の設定にも注意が必要です。国交省案件では「JGD2011」や公共座標系の指定がある場合が多いため、最初にプロジェクト全体の基準を統一しておくことが重要です。後から修正するのは手間がかかるため、初期段階で明確に定義しておくのが賢明です。
この段階でDMデータの基礎となる地形モデルをしっかり整えることで、後続工程の整合性が高まり、コリドーモデル作成時に法面や標高を正確に算出できます。結果として、設計品質全体の向上にもつながります。
4.2. アラインメントとプロファイルの設計
地形モデルが整ったら、次に道路や河川の中心線にあたるアラインメント(水平線形)を作成します。Civil 3Dでは、曲線半径や直線区間の長さなどを設計基準に沿って設定でき、精密な線形設計が可能です。さらに、同時にプロファイル(縦断線形)を作成して、起伏のある地形に合わせた縦断勾配や縦曲線を決定します。
この工程は、後のコリドーモデルの精度を大きく左右する重要なステップです。パラメータの入力は正確に行い、法規的な条件や車両走行の安全性、排水計画などを十分に考慮しながら設定します。国交省の「道路設計要領」や関連ガイドラインがある場合は、それに準拠した線形設計を行うことが求められます。
アラインメントとプロファイルが完成したら、各断面の法面勾配、車線幅、路肩幅などの属性情報を関連付けて保存しておくと便利です。こうしておけば、設計変更が発生した場合にもCivil 3Dが自動で再計算し、図面や数量の再作成を効率化できます。
4.3. コリドーモデルの生成と属性設定
アラインメントとプロファイルが完成したら、次にそれらを基にコリドーモデル(Corridor Model)を生成します。コリドーモデルとは、道路や河川、堤防などの断面構造を3D空間で再現する設計モデルで、車道部・路肩部・法面などをひとまとまりにした「アセンブリ(Assembly)」を組み合わせて構築します。
たとえば道路設計の場合、アセンブリ内で車線、縁石、排水溝、法面などを個別のパーツとして設定し、横断勾配や幅員を入力します。Civil 3Dはこれらの情報をもとに、地形・アラインメント・プロファイルに合わせて自動的に3Dコリドーモデルを生成します。
完成したコリドーモデルには、部材名称、材質、施工仕様、構造区分などの属性情報を追加しておきます。これにより、設計変更時の追跡性(トレーサビリティ)が確保でき、施工計画や維持管理フェーズでのデータ活用が容易になります。
DMデータに豊富な属性を持たせておくことで、後のCIM連携や数量算出にもスムーズに対応できるようになります。
4.4. 最終出力:フォーマットと座標系の設定
モデルの構築が完了したら、最後に納品用データの出力(エクスポート)を行います。一般的に使用される形式は、LandXMLやIFCといった中立フォーマットです。LandXMLは道路・河川分野でのDMデータ交換に多く利用され、IFCはBIMソフトとの連携に適しています。
出力時には、座標系と単位系の設定確認が非常に重要です。Civil 3D内で統一されていても、受け取る側の環境が異なると、位置ズレやスケールの誤差が発生することがあります。たとえばメートルとフィートの単位違いや、楕円体定義(JGD2011、WGS84など)の相違でモデルが正しく配置されない事例も少なくありません。
そのため、出力前にマニュアルや発注者指定の規格を確認し、正しい設定でエクスポートを行いましょう。
こうした細部のチェックを徹底することで、納品データの整合性と信頼性を保ち、国交省や発注者による検査をスムーズに通過できます。
5. DMデータ活用で広がるCivil 3Dの可能性
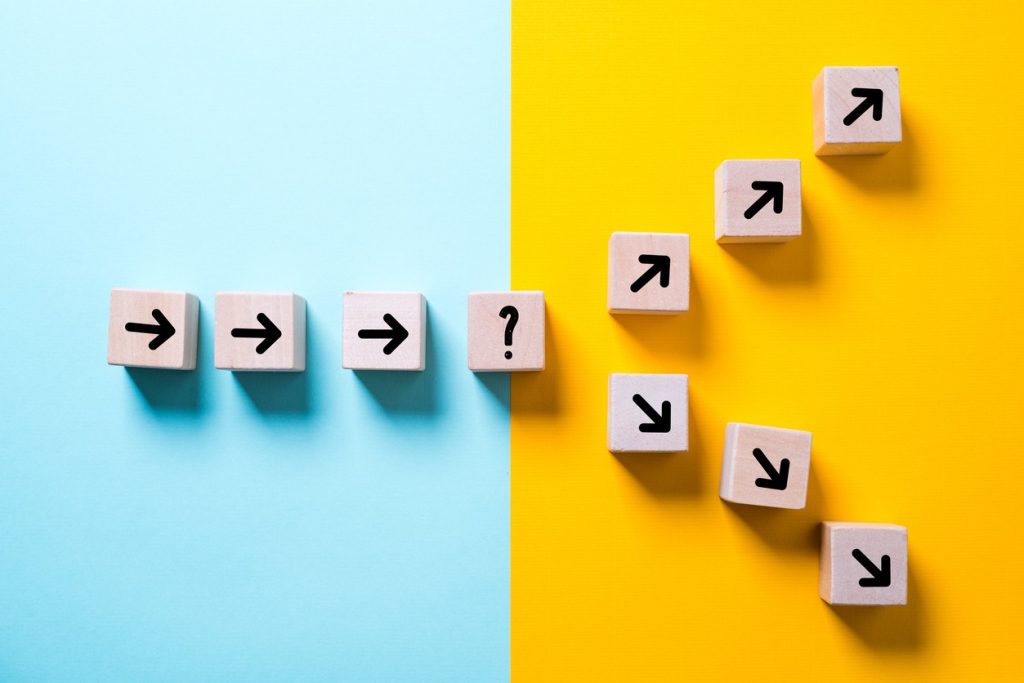
5.1. 他ツールとの連携とそのメリット
Civil 3Dで作成したDMデータは、InfraWorks、Navisworks、RevitなどのAutodesk製ツールとシームレスに連携できます。これにより、土木設計から建築・設備設計、そして施工計画まで、同一データをもとにした一貫したワークフローを実現できます。
また、他のAutodesk製品や他社製ビューアでDWGファイルを開く場合は、「Civil 3D Object Enabler」をインストールしておくのがおすすめです。これにより、Civil 3D特有のオブジェクト(コリドー、サーフェス、パイプネットワークなど)を正しく表示できます。
たとえば、InfraWorksにDMデータを取り込むと、広域の地形や都市計画レベルのCIMモデルと統合し、リアルタイムに3D可視化が可能になります。こうした可視化機能を活用すれば、合意形成やプレゼンテーション時に関係者の理解を深めやすくなります。
さらに、Navisworksでは干渉チェックや工程シミュレーションを行うことができます。建築・設備モデルと重ね合わせて確認すれば、設計段階で構造物の干渉を発見でき、施工時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
また、RevitやBIM 360(Autodesk Construction Cloud)と連携すれば、建築・設備分野との情報共有がよりスムーズになります。DMデータを中心に、関係者全員が同じ情報をリアルタイムで共有できるため、情報共有の効率化とプロジェクト全体の品質向上が期待できます。
5.2. 設計変更の自動更新とトレーサビリティ
DMデータの大きな強みは、設計変更への自動対応と履歴管理の容易さにあります。たとえば、アラインメントの一部を修正すると、Civil 3Dが自動的にコリドーモデルを再計算し、それに基づく断面図や数量も自動で更新します。これにより、手動修正によるミスを減らし、大幅な作業時間短縮が可能になります。
さらに、DMデータはトレーサビリティ(履歴管理)の確保にも役立ちます。誰が、いつ、どの部分を変更したのかをデータ上で一元管理できるため、工程の振り返りや監査対応、発注者への説明資料としても有効です。
CIMの目的は、設計から施工、維持管理までをデータでつなぐことにあります。そのため、DMデータが持つ「自動更新」や「履歴保持」の機能は、CIMを運用するうえで欠かせない要素です。
実際の現場では、発注者や施工業者から「勾配を少し変えてほしい」「構造物の位置を調整したい」といった要望が頻繁に発生します。DMデータを活用すれば、モデル全体を作り直すことなく部分的な変更が反映されるため、スピーディかつ高品質な設計対応が可能になります。
5.3. 施工計画と合意形成への応用
DMデータは、施工計画の立案にも非常に有効です。数量算出や資機材搬入計画、仮設構造物の検討などを3Dモデル上で行うことで、現場の実態に近いシミュレーションが可能になります。これにより、工期短縮やコスト削減だけでなく、建設機械の稼働範囲確認や安全管理にも大きく貢献します。
また、DMデータは合意形成の場面でも力を発揮します。従来の2D図面では理解しにくかった工事の完成形や施工範囲を、3Dモデルで直感的に示せるため、地元住民や行政との協議がスムーズになります。これにより、説明会での誤解を防ぎ、トラブルの未然防止にもつながります。
さらに、施工完了後には、実際の施工内容や変更点をDMデータへ反映することで、維持管理段階にも正確な情報を引き継ぐことが可能です。設計から施工、維持管理へと一貫して情報を活用できるこの仕組みこそ、CIMの本質といえるでしょう。
Civil 3Dは、こうした一連のプロセスの基盤として、DMデータの作成・共有・更新を支える中心的なツールです。土木設計のDX化が進む今、Civil 3DとDMデータの活用は、次世代のインフラ設計を担うための大きな鍵となります。
6. 実務で注意すべきDMデータ作成のポイント
6.1. モデル精度とLODの設定
DMデータは多くの情報を統合できる反面、どこまで詳細にモデル化するかを慎重に見極める必要があります。LOD(Level of Detail または Level of Development)を適切に設定し、設計段階では形状や位置の精度を重視し、施工段階では数量や属性情報の精度を高めるといった使い分けが重要です。
過剰に詳細な3Dモデルを作成すると、PCの動作が重くなり、作業効率が落ちるリスクがあります。必要十分な情報に留め、目的に合った精度を維持することが実務的な運用の基本です。
また、国交省のガイドラインや発注仕様を確認し、橋梁・河川・道路など構造物の種類に応じて最適なLODを設定しましょう。たとえば、設計段階では通り芯や主要断面をモデル化し、施工段階では補強筋やボルト、コネクタ位置などを段階的に追加する、といった方法が効果的です。
LODは一度決めたら終わりではなく、設計進行に合わせて更新していくことが理想です。無駄な精度向上を避けつつ、必要な情報を的確に反映させる――これがCivil 3Dを使ったDMデータ作成を効率化するコツです。
6.2. レイヤー整理と不要要素の削除
Civil 3Dで作業を重ねるうちに、試行錯誤の過程でレイヤー数が増えたり、不要なオブジェクトが残ったりすることがあります。これを放置すると、モデル全体が煩雑化し、動作の遅延や納品時の不整合につながる恐れがあります。
そこで、定期的にレイヤーやオブジェクトを整理・清掃する習慣をつけましょう。削除前には必ずバックアップを取り、古いコリドーモデルや一時データは「アーカイブ領域」に移動して管理するのがおすすめです。こうした整理ルールをチーム全体で共有しておくと、作業の再現性や品質が向上します。
また、国交省案件などの納品では、レイヤー名やオブジェクト名をわかりやすく統一しておくことも重要です。構造や要素が整理された状態であれば、発注者側の確認や検査もスムーズに進み、情報共有効率化にもつながります。DMデータの品質を維持するうえで、地味ながら最も効果的な工程のひとつです。
6.3. 納品前の最終チェックリスト
DMデータを納品する前には、いくつかの重要なチェック項目を必ず確認しておきましょう。まず、座標系や単位設定が正しいかを再確認します。特にLandXMLやIFC形式へエクスポートした後は、ビューワーで開いて形状や属性が正しく保持されているか、必ず目視で検証します。
さらに、ファイル命名規則やフォルダ構成が発注者指定に沿っているかも見落とせません。アラインメントや構造物モデルなどを別ファイルで納品する場合は、仕分けや命名を厳密に行い、不要なテンポラリファイルを含めないよう注意します。納品仕様書をもとに、どの要素をどの精度で含めるかを再確認することが大切です。
このような最終チェックを体系化しておくと、検査段階での修正依頼を最小限に抑えられ、納品の信頼性も向上します。DMデータが正確で整備されていれば、後続の設計変更や維持管理フェーズにもスムーズに引き継げます。最後まで丁寧な確認を怠らないことが、品質の高い3D成果物を納める第一歩です。
7. まとめ|Civil 3DとDMデータで変わる設計のワークフロー
DMデータは、3D設計モデルに形状だけでなく属性情報やメタデータを組み込むことで、土木設計のあらゆる工程を効率化できる革新的な成果物です。
Autodesk Civil 3Dを使いこなせば、こうしたDMデータを容易に作成でき、CIM対応をより確実かつ実践的に実現することが可能です。
たとえば、DMデータを活用することで設計変更が自動的に反映され、数量計算や断面図の再生成もスムーズに行えます。これにより、作業時間の短縮とミスの防止が同時に達成され、設計品質の向上にも直結します。さらに、Civil 3DのデータをInfraWorksやRevit、Navisworksなどの他ツールと連携させれば、関係者間で同一の情報を共有しながら意思決定を進めることができ、合意形成の迅速化や施工管理の精度向上にもつながります。
今後は、従来の2D図面に加えて3次元モデルを成果物として納品する案件が標準化していくと見込まれています。
国土交通省をはじめとする多くの発注機関では、2D図面と3Dモデルを併用しつつ、活用目的に応じて3次元モデル成果物(DMデータ)の仕様を段階的に整備しています。
これからの土木設計では、DMデータの整備・活用が業務効率化だけでなく、チーム全体の情報共有・品質管理の要となります。
Civil 3Dを軸にDMデータを積極的に活用することで、BIM/CIMのワークフローの中心に立ち、新しい時代の設計スタイルをリードする存在を目指してみてください。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
Autodesk Civil 3D 2025 | Civil 3D ソフトウェア の価格と購入












