CADの試験と資格の種類まとめ|初心者でもわかる比較ガイド
1. はじめに:CAD資格の重要性と本ガイドの目的
CAD(コンピューター支援設計)は、建築や製造をはじめとする幅広い分野で欠かせない技術となっています。近年は設計現場の効率化やデジタル化が進み、CADスキルを客観的に証明できる「資格」の需要も高まっています。
資格を持つことは、就職や転職活動において有利になるだけでなく、実務での信頼性を示す大きな武器にもなります。企業側から見ても、明確な指標があることでスキルレベルを把握しやすく、安心して仕事を任せやすくなるのです。
本記事では、CAD資格の基本から主要な試験の種類、2D/3Dそれぞれのポイントまでをわかりやすく解説します。特にこれからCADを学びたい初心者の方や、建築・製造分野への転職を考えている方にとって、資格選びの具体的なヒントが得られる内容です。
読み進めていただくことで、自分に合った試験を見極め、スキルアップやキャリア形成に役立てられるようになるはずです。本ガイドを参考に、資格取得を次のステップにつなげてみてください。
2. CAD資格の基本概念
CAD資格とは、初心者からプロフェッショナルまで幅広い層を対象に、試験や認定制度を通してスキルを証明する仕組みの総称です。
ここでは、CADスキルを示すうえで欠かせない「公的資格」と「民間資格」の違い、さらに2D CADと3D CADの基本的な役割について解説し、学習や試験準備の理解を深めていきましょう。
公的資格は国や関連団体が認定する資格を指しますが、CAD分野では民間資格が中心となっています。扱う範囲や目的はそれぞれ異なり、選び方を工夫することが大切です。CADの公的資格は数が少ない一方で、民間資格はソフトウェアや業界ごとに広く実施されているため、自分の目的に合わせた選択が求められます。
また、2D CADは平面図や基本的な構造の作図に用いられ、3D CADは立体モデルの設計や干渉チェックなど実務に直結する機能を担います。どの資格を目指すかは、志望業界や作図スタイルによって変わるため、比較しながら方向性を定めることが重要です。
2.1. CADとは何か?
CADとは「Computer-Aided Design」の略で、コンピューターを使って設計や製図を行う技術を意味します。建築図面の作成や製造業での部品設計、インテリアデザインなど、幅広い分野で活用されています。
手書き製図に比べ、CADは正確性や修正のしやすさが格段に向上します。初心者にとっては、まず作図の基本概念を理解することが学習の第一歩となります。
さらに、専門学校や通信講座といった教育機関の充実により、独学でも基本操作を習得することが可能です。これが将来的に就職や転職(CAD就職・CAD転職)で大きな強みになるケースも少なくありません。
CAD学習を進めるうえで特に重要なのは「正確性」と「効率性」です。この二つを身につけた人材は企業から高く評価されるため、資格取得が評価の基準となる理由もここにあります。
2.2. 公的資格と民間資格の違い
公的資格は国家試験や自治体関連の資格を指し、建築士のように法律で位置づけられているものもあります。しかしCAD分野では、民間団体やメーカーが主催する資格が主流で、多彩な試験が存在します。
建築CAD検定やCAD利用技術者試験といった民間資格は、特定分野でのスキルを示す証明として活用され、業界のニーズに対応しやすい点が特徴です。公的資格が限られている分、民間資格が企業から評価されるケースは多くあります。
ただし、資格の評価は知名度や実務性によって異なるため、自分が目指す業界や職種でどの程度認知されているかを事前に確認しておくことが大切です。また、CADそのものを対象にした国家資格は少ないものの、「機械・プラント製図技能士(技能検定)」といった製図系国家資格はCADスキルと親和性が高く、将来的に挑戦する価値があります。
特に建築分野を志す場合は、資格の認定団体や試験範囲を確認したうえで対策を進めることが望ましいでしょう。
2.3. 2D CADと3D CADの基本
2D CADは平面的な作図に用いられ、建築図や機械部品の図面、寸法表示などの基礎に役立ちます。基礎スキルを習得するには、まず2D CADをしっかり操作できるようになることが不可欠です。
一方で3D CADは立体モデルを扱い、部品同士の干渉や組み立てのシミュレーションなど、実務に直結する高度な機能を備えています。製造や機械設計の分野では3D CADの利用が主流であり、SolidWorks認定試験やFusion 360試験などがよく知られています。
2Dと3Dの違いを理解しておくと、自分のキャリアプランを立てる際に大きな助けとなります。将来的に3D CADを専門的に使いたい場合も、まず2Dで基礎を固めてから段階的に移行するのが一般的です。
それぞれの資格試験には異なる対策ポイントがあるため、学習計画や試験選びの段階から「2Dか3Dか」を意識して準備を進めることが成功への近道となります。
3. 主要なCAD資格の紹介と比較
ここからは、代表的なCAD資格を順に取り上げ、その特徴や難易度、合格のポイントを詳しく見ていきます。CAD試験情報を集めても「どの資格が自分に合うのか」と迷う方は多いですが、業界視点と初心者視点の両方から整理して理解すれば、意外と選びやすくなります。
本セクションでは、CAD利用技術者試験、建築CAD検定、Autodesk認定資格、SolidWorks認定試験、そしてその他の注目資格に焦点を当てます。試験内容の違いを理解することは、自分が進みたい業界でどの程度有利になるかを判断する重要な材料となるでしょう。
各資格は、基本操作を中心とした入門レベルから、実務経験を前提とする高度なレベルまで幅広く用意されています。独学で挑戦できる試験もあれば、専門的な指導を受けたほうが合格に近づく試験もあります。自分のキャリア段階や目的に照らし合わせながら、ここで紹介する資格を比較検討してみてください。
では、それぞれの試験の内容を具体的に確認していきましょう。
3.1. CAD利用技術者試験の概要と特徴
CAD利用技術者試験は、CAD民間資格の中でも特に知名度が高い試験です。2D CADと3D CADの両方に対応しており、2Dは「基礎・2級・1級(機械/建築/トレース)」の3段階構成、3Dは「2級・準1級・1級」という体系で運用されています。
2級は初心者向けで、基本的な作図スキルや操作知識に加え、製図ルールなども問われます。1級になると、より高度な知識や正確な作図スピードが求められます。さらに3D試験では、三次元モデリングや投影図の理解などが評価されるため、機械設計を志す方にとっても有効です。
出題は理論問題と実技問題の組み合わせで構成され、過去問演習や練習ソフトを使った学習が合格の近道となります。独学でも挑戦は可能ですが、専門学校やスクールを利用すると効率的に準備できます。
また、CAD利用技術者試験(2D/3D)は厚生労働省の「教育訓練給付金制度」の対象に指定されており、受講料の一部が戻る仕組みがあります(主催:一般社団法人コンピュータ教育振興協会)。ただし、給付対象は資格そのものではなく、厚労省が指定した講座の受講である点に注意が必要です。最新の指定状況は各講座や厚労省公式サイトで確認しましょう。
合格後は幅広い業界でスキルをアピールでき、建築や製造分野への転職活動でも強みとなります。キャリアアップを目指す人にとって、非常に実用性の高い資格です。
3.2. 建築CAD検定試験の詳細
建築CAD検定は、その名の通り建築分野に特化した試験で、平面図・断面図・立面図といった建築特有の図面作成能力が問われます。建築事務所や設計会社で評価されやすい資格の一つです。
試験区分は4級・3級・2級・准1級に分かれており、最上位は准1級です(1級は公式に未実施)。級が上がるにつれて難易度も上昇します。初心者はまず3級から挑戦し、基本的な建築図面のルールや操作を身につけ、次に2級や准1級を目指す流れが一般的です。
学習の際は、Jw_cadやAutoCADなど主要なソフトを使うケースが多く、同時に建築用語や法規知識も必要になります。特に寸法ルールや投影法といった基礎理論を理解しておくことで、効率的に学習を進められます。
建築分野でのキャリアを志す人にとって、この資格は信頼性を高め、転職や社内評価の向上に直結する武器となるでしょう。
3.3. Autodesk認定資格の解説
AutoCADをはじめとするAutodesk製品は世界中で利用されており、Autodesk認定資格を取得することで国際的なスキル証明が可能になります。日本では主に「オートデスク認定ユーザー(ACU)」試験が提供されており、AutoCAD/Revit/Fusion 360などを対象に、各50分の試験が実施されています。
その中でもACU(AutoCAD)やFusion 360試験は、設計やモデリングの基礎スキルを証明できる資格として人気です。一方、上位レベルの「Professional」試験はグローバルで展開されていますが、国内での実施は限定的です。
Fusion 360試験では主に3Dモデリングの基本操作が出題されます。Fusion 360は設計から解析・製造までをカバーする統合型ソフトであるため、この資格を取得すれば幅広いワークフローを意識したスキルの証明につながります。製造業だけでなく建築やプロダクトデザイン分野でも導入が進んでおり、汎用性の高さも魅力です。
これらの資格を取得すると、海外企業や国際的なプロジェクトに携わりやすくなり、グローバルキャリアを目指す人にも有効な選択肢となります。
3.4. SolidWorks認定試験の概要
SolidWorks認定試験は、機械系の3D設計で多く用いられるソフト「SolidWorks」のスキルを証明するものです。CSWA(Certified SolidWorks Associate)やCSWP(Certified SolidWorks Professional)といったレベル別試験があり、実務に直結したモデリングやアセンブリ技術が求められます。
試験では実際の部品をモデリングしたり、寸法を変更して不具合を見つけたりといった課題が出題されます。3D CADに慣れている人でも短時間で正確に解答する必要があるため、日頃からの練習が欠かせません。
製造業や自動車関連の大手企業でSolidWorksを利用している場合、CSWPなど上位資格を持っていると高く評価されます。機械設計を専門にしたい人にとって、非常に価値のある資格です。
独学でも挑戦は可能ですが、公式ガイドブックや模擬問題を活用することが推奨されます。必要に応じて通信講座やスクールを利用すると、効率よく合格に近づけるでしょう。
3.5. その他の注目CAD資格
ここまで紹介した以外にも、業種やソフトによって注目すべき資格は数多くあります。例えば、CATIAの認定資格は航空機や自動車分野での利用が多く、導入企業では高い評価を得られます。
また、Jw_cadを用いた検定や、3Dプリント関連のソフトに特化した資格なども存在し、特定の業界や業務で必要とされるケースがあります。自分の進みたい方向性や関わりたいプロジェクトに合わせて調べてみると、最適な資格に出会えるでしょう。
さらに、BIM(Building Information Modeling)に関する資格も近年注目を集めています。BIMは単なるCADの延長ではなく、3Dモデルに属性情報や工程・コスト管理を統合する仕組みで、建物全体をデジタルに管理できる技術です。BIM資格を取得することで、より高度な設計・施工プロセスに対応できる人材として評価されやすくなります。
このように、CAD資格にはそれぞれの分野に特化した特徴があります。将来のキャリアビジョンに応じて必要な資格を選び、段階的に取得していくことで、長期的なキャリア形成につなげることができます。
4. CAD資格の選び方:目的と業界に合わせて
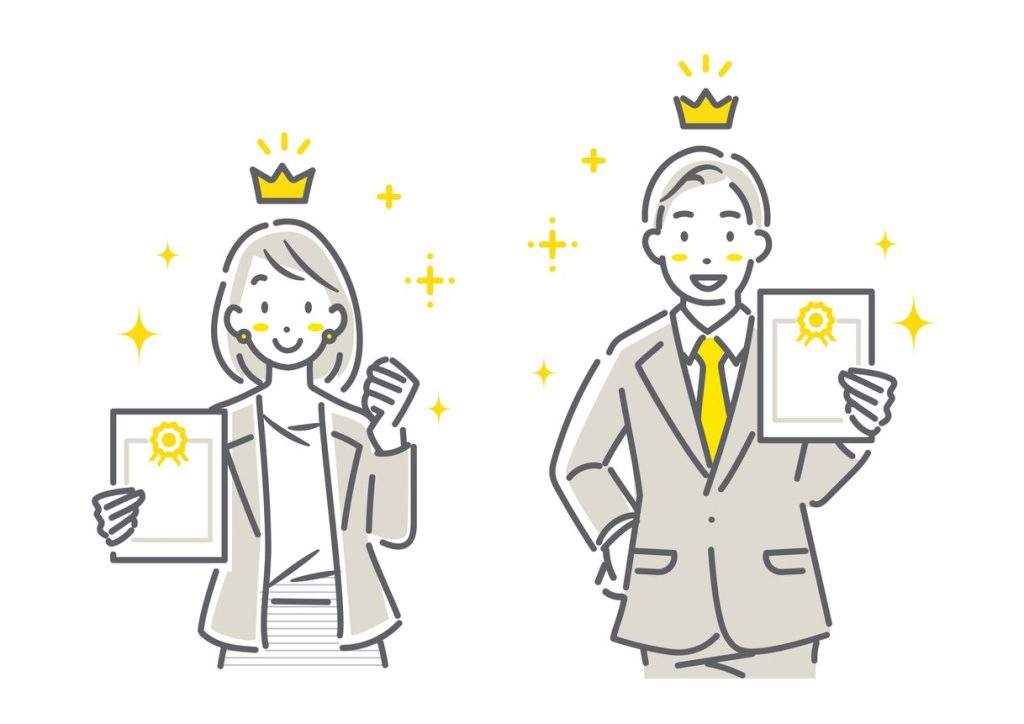
CAD資格にはそれぞれ特色があり、どれを選ぶかで学べる内容や評価のされ方が変わってきます。そのため「自分に合った資格はどれか」で迷う方は多いでしょう。ここでは、建築業界、製造・機械設計業界、そして初心者向けという3つの観点から、それぞれに適した資格を紹介します。
特に初心者や異業種からの転職を考えている方は、まず汎用性の高い資格を取得することが効果的です。基礎力をしっかりと証明してから、徐々に専門分野にステップアップする流れを意識すると無理なく進められます。
また、業界ごとに求められるCADスキルのレベルや使用ソフトが異なるため、志望企業がどのソフトを使っているのかを事前に調べることも欠かせません。
以下の3つのセクションを参考に、自分の目的や業界に合わせて試験選びを検討してみましょう。
4.1. 建築業界向けの資格ガイド
建築分野を目指すなら、まずは建築CAD検定試験が代表的な選択肢です。この試験では住宅やビルの平面図・立面図を正確に描く力が求められ、とりわけ空間把握力や法規的な寸法ルールへの理解が重視されます。
さらに、CAD利用技術者試験の2級や1級を取得すれば、建築以外の分野も含めた幅広い2D CADスキルを証明できます。これにより、転職活動の際に柔軟性や応用力をアピールできるのが利点です。
また、Autodesk系のAutoCAD認定資格は建築事務所で導入されていることが多く、国際的にも通用するソフトの操作スキルを証明できるため強い武器となります。特に外資系のプロジェクトを目指す方には大きなアピールポイントになるでしょう。
資格の持つ価値は、実際に図面を扱う現場でこそ実感できます。資格そのものが転職活動の決め手となる場合もありますが、実務知識や応用力と組み合わせることで、より高い評価を得やすくなります。
4.2. 製造・機械設計業界のおすすめ資格
製造や機械設計の分野に進みたい方には、3D CADのスキルが特に重視されます。代表的なのは3次元CAD利用技術者試験やSolidWorks認定試験で、CSWA(基礎)やCSWP(上級)を取得すれば、モデリングやアセンブリ設計に対応できる実力を示すことができます。
Fusion 360試験も注目すべき資格のひとつです。Fusion 360は設計から解析・製造までをカバーする統合型ソフトであり、この試験に合格すれば製造プロセス全体を意識したスキルを証明できます。部品単位の設計だけでなく、製品全体を見通せる力を養いたい人には特に適しています。
一般的には2D CADから学び、3Dへ進む流れが王道ですが、先に3D CADを学び2Dとの違いを理解する方法もあります。自分の学びやすいスタイルや、志望企業がどのソフトを扱っているかを基準に方向性を決めるとよいでしょう。
この業界では、初心者であっても資格取得への意欲を示すことで、未経験からCAD関連職に就職・転職できるケースも少なくありません。
4.3. 初心者向け:基礎から始めるCAD資格
CAD初心者の方におすすめなのは、CAD利用技術者試験の2級や建築CAD検定の3級です。いずれも難易度が比較的低く、基本操作や図面作成の基礎を学ぶには最適な入り口となります。
また、操作がシンプルなJw_cadを活用して独学で図面制作に挑戦するのも有効です。Jw_cadは無償ソフトのため、コストをかけずに学習環境を整えられるというメリットがあります。
学習の際は、CAD学習ガイドやオンライン講座、専門書籍などを活用し、反復練習で基礎を固めましょう。作図そのものだけでなく、レイヤーの使い分けや寸法設定といった実務で必須となる操作も体系的に理解しておくと実践力につながります。
まず基礎資格を取得することで自信がつき、次の段階として上位資格やソフトウェア別の認定試験に挑戦しやすくなります。段階を踏んで学んでいくことが、最終的に確実なスキルアップにつながるのです。
5. 効果的な学習方法と資格試験の準備
CAD資格に合格するためには、計画的な試験準備と継続的な学習方法が欠かせません。学習に使える時間や予算、さらには学習スタイルは人それぞれ異なります。そのため、独学で取り組むのか、スクールに通うのか、あるいは通信講座を活用するのかを最初に検討することが重要です。
ここでは3つの学習アプローチを紹介します。自分に合った方法を選び、過去問演習や実習の質を高めていけば、効率よく合格への道を切り開けます。試験の難易度にかかわらず、出題傾向をしっかり把握したうえで学習を進めれば、短期間でも合格レベルに到達することが可能です。
それでは、以下の3つのセクションを手がかりに、具体的な学習戦略を考えていきましょう。
5.1. 独学での学習戦略
独学の最大のメリットは、自分のペースで進められる点です。必要に応じて書籍やオンライン教材を活用し、通勤前の朝時間や帰宅後などの隙間時間を利用して作図練習を重ねることができます。
市販されている対策本や過去問題集は、試験の出題傾向をつかむために最適です。たとえば、CAD利用技術者試験の演習問題を解きながら、模擬図面を繰り返し描く方法は効果的です。
独学のデメリットは、疑問点をすぐに解決できないことですが、近年はCAD専門のオンラインフォーラムやSNSを活用すれば、多くの情報やアドバイスを得やすくなっています。
自己管理が得意で、学習の目的が明確な人にとっては、費用を抑えながら効率的に合格を目指せる方法といえるでしょう。
5.2. スクールやオンライン講座の活用
CADスクールやオンライン講座を利用する利点は、体系的なカリキュラムと講師からのサポートを受けられる点です。短期間で集中的に学習したい場合や、初心者が基礎を確実に固めたい場合に向いています。
通学制スクールでは、同じ目標を持つ仲間と情報交換できるため、モチベーションを維持しやすいのが魅力です。CAD専門学校では、実際の機材を使った演習もあり、実務に近い学び方ができるのも大きなメリットです。
一方で、オンライン講座は自宅や職場からでも学べるため、働きながら学習を進めたい人に適しています。録画された講義を繰り返し視聴できる講座であれば、苦手な操作を集中的に復習できるのも強みです。
ただし、費用は独学より高くなる場合が多いため、予算と時間のバランスを考えながら選ぶことが大切です。
5.3. 実務経験を組み合わせた学習
最も効果的な学習法は、資格対策と並行して実務経験を積むことです。実際の仕事でCADを使う機会があれば、習得した知識や技術をその場で試せるため、試験勉強にも直結します。
例えば、製図ルールを実際のプロジェクトで体験すれば、知識が定着しやすくなり、学習効率も向上します。試験選びの際にも、普段の業務で使用しているソフトに対応した資格を選べば、取得後すぐに実務で活かせる点が大きなメリットです。
まだ実務経験がない場合でも、インターンやアルバイトを通じてCAD業務に触れる機会を探すのは有効です。現場で必要とされるスピード感や応用力を養うことで、本番の試験にも自信を持って臨めるでしょう。
最終的には、資格取得にとどまらず、実務経験や応用力を組み合わせることで、企業やプロジェクトから高い評価を受けられる総合的なスキルを身につけることができます。
6. CAD資格取得後のキャリア展望
CAD資格の取得はゴールではなく、そこからどのようにスキルを広げていくかがキャリア形成のカギとなります。資格をきっかけに就職や転職が有利になるだけでなく、給与や担当プロジェクトの範囲など、働き方そのものに大きな影響を与える可能性があります。
ここでは、資格取得後に広がるキャリアの可能性と、実際に企業がどのように評価しているのかを紹介します。資格を「どう活かすか」のイメージを持つことが、次のステップに進むための指針となるでしょう。
特に建築分野や製造分野でキャリアを積む場合、CAD操作だけでなく他の設計ソフトとの連携や応用力を身につけることで、より高い評価を得られるようになります。次の2つの小見出しでは、資格が開くキャリアの扉と、職場での評価のされ方を具体的に掘り下げます。
6.1. 資格が開くキャリアの扉
一度CAD資格を取得すると、キャリアの節目で大きなアドバンテージとなります。たとえば、新しいプロジェクトのリーダーを任命する際や、より専門性の高い設計業務を担当させる際に、「CADスキルを客観的に証明できる」という事実が強い武器になります。
建築CAD検定やCAD利用技術者試験の上位級は、図面管理にとどまらず、チーム内外の調整や共同作業で力を発揮します。建築分野では法規や設計知識と組み合わせて使う場面が多く、製造分野では部品同士の干渉確認や質量計算といった実務力が求められるのが特徴です。
さらに、資格取得後にBIMのような新しい技術を学ぶことで、企業からの評価は一段と高まります。長期的に見れば、幅広い業務をカバーできる人材として活躍の場を広げることができるでしょう。そのためにも、資格取得の段階で自分の強みを整理し、どの分野で発信していくかを明確にすることが大切です。
6.2. 資格取得の影響と職場での評価
資格を持っているからといって、すぐに即戦力になるとは限りません。しかし「CAD資格を持っている」という事実は、確かなメリットをもたらします。例えば、図面を正確に扱える人材が少ない職場では、CAD操作ができるだけで大きな信頼を得られるでしょう。
また、転職活動においても資格は大きな後押しとなります。採用担当者は、CAD資格を持つ応募者を「基礎スキルが保証されている人材」と評価し、書類選考の段階で優先的に声をかけることがあります。これは、企業側にとって採用リスクを軽減できる大きな要素です。
ただし、資格だけでは複雑な設計や高度な提案をこなすのは難しいのも事実です。現場ではCAD資格に加え、コミュニケーション能力、設計知識、法規の理解などが欠かせません。
つまり資格はあくまで出発点であり、その上に実務経験や専門知識を積み重ねることで、初めて総合的な力を発揮できるのです。
7. まとめとFAQ
ここまで、CAD資格の重要性や代表的な試験の特徴、学習方法から資格取得後のキャリア展望までを幅広く解説してきました。特に、建築分野への転職を考えている方にとっては「建築CAD検定試験」が有力な選択肢となり、さらにCAD利用技術者試験やAutodesk認定資格を組み合わせれば、スキルの幅を広げることができます。
資格取得はゴールではなく、その後の実務でどう活かすかが本当の価値を決めます。早い段階で「自分に合った試験はどれか」を見極め、多角的にキャリア形成へとつなげていきましょう。
最後に、資格選びのアドバイスと、よくある質問への回答をまとめました。スキルアップや転職活動を進める上で不安に感じる点があれば、ぜひ参考にしてください。ここからさらに前進するためのヒントになれば幸いです。
7.1. CAD資格選びの最終アドバイス
まずは、自分が目指すキャリアの方向性を明確にすることが大切です。建築業界で働きたいのか、機械設計に進みたいのか、あるいは幅広いCADスキルを身につけたいのかによって、最適な資格は変わります。
CAD試験選びの基本は「業界ニーズ」と「自分の専門領域」の交差点を見つけることです。建築業界を志望するなら建築CAD検定やAutoCAD認定資格が有効ですし、製造業界であれば3次元CAD利用技術者試験やSolidWorks認定試験が有力です。使用するソフトや作図環境を踏まえて検討するのがポイントです。
また、初心者の方はまず基礎を固める意味で、CAD利用技術者試験の2級や建築CAD検定の3級に挑戦すると良いでしょう。その後、経験を積みながら上位資格やソフトウェアごとの認定試験に進むことで、着実にスキルを伸ばしていけます。
資格はあくまで出発点にすぎません。学習と並行して実務経験を積み、自分の得意分野を明確にしていくことが、次のステップにつながる最も確実な方法です。
7.2. よくある質問とその回答
Q1: CAD初心者でも独学で合格できますか?
A1: 十分に可能です。無償のCADソフトや市販の問題集を活用し、日常的に作図練習を続ければ合格への道は開けます。疑問点があればオンラインフォーラムなどで質問すると、効率的に学べるでしょう。
Q2: 建築CAD検定とCAD利用技術者試験のどちらを優先すべきでしょうか?
A2: 建築業界を強く志望するなら建築CAD検定を優先するのがおすすめです。一方で、幅広い業界で通用する基礎力を証明したいならCAD利用技術者試験が有効です。最終的には、自分の将来の方向性に合わせて選びましょう。
Q3: 資格を取っても実務力につながるのでしょうか?
A3: 資格は基礎スキルの証明にあたります。実務力を高めるには現場経験が欠かせませんが、資格を持っていることで採用や配属の際に優先されるケースは多くあります。
Q4: 2D CADから学ぶべきか、3D CADから始めるべきか迷っています。
A4: 一般的には、まず2D CADで図面構成や寸法設定の基礎を身につけ、そこから3Dに進む流れが多いです。ただし、製造業など3Dが主流の業界を志望する場合は、最初から3Dに取り組む方法も選択肢のひとつです。
大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!
❶大手ゼネコンのBIM活用事例
❷BIMを活かすためのツール紹介
❸DXレポートについて
❹建設業界におけるDX

<参考文献>
CAD利用技術者試験 – ACSP 一般社団法人コンピュータ教育振興協会
【建築CAD検定試験】AACL-(社)全国建築CAD連盟
公式 CAD トレーニング・認定 | Autodesk
https://www.autodesk.com/jp/training
SOLIDWORKS認定プログラム | SOLIDWORKS
https://www.solidworks.com/ja/solidworks-certification-program












