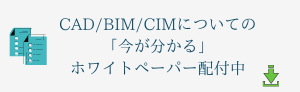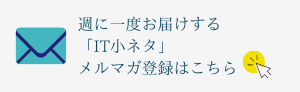SolidWorks CAMは無償でここまでできる!実務での活用術5選
1. はじめに
生産工程を効率化したいという要望は、製造業に携わる多くの設計者や技術者にとって切実な課題です。特に中小規模の企業では、限られたリソースで高品位の製品を市場に出す必要があります。そのためには、設計段階から製造プロセスを統合し、コストを抑えながら短納期に対応できる体制を整えることが大切です。
SolidWorks CAMは、そうしたニーズに応える製造支援ツールとして注目を集めています。2.5軸加工に特化した機能を無償で利用できる「SolidWorks CAM Standard」は、CADとの統合のもと、設計から製造までのプロセスを一貫して管理できます。たとえば、Feature Recognition(フィーチャー認識)機能や自動ツールパス生成が実装されており、穴あけ加工やポケット加工の工程が容易になります。
無償という響きは魅力的ですが、実際どの程度まで使いこなせるのか疑わしいと感じる方もいます。そこで本記事では、SolidWorks CAMの仕組みや強み、そして無償版で実際にどこまでできるのかを解説しながら、実務の現場で役立つ具体的な活用術を紹介していきます。中学生の方でも理解しやすいよう、専門用語は丁寧に言い換えつつ解説します。
大切なのは、新しいツールを導入することで得られる効果と、その使いこなし方を具体的にイメージできることです。SolidWorks CAMの導入を検討している設計者や製造現場の方々が、この記事を通じてより多くのヒントを得て、業務効率化やコストダウンを実現していただければ幸いです。
2. SolidWorks CAMの基本と特徴
SolidWorks CAMは、3D CADソフトで知られるSolidWorksと統合されたCAM(コンピュータ支援製造)システムです。特徴的なのは、設計データを直接参照して加工工程を定義できるため、「設計から製造」までの一貫したワークフローを構築しやすい点です。さらに、CADとの強固な連携により、モデル変更時には自動でツールパスを再生成するなど、スムーズな加工データの更新が可能です。
CAMWorksというベース技術を採用している点は信頼性の裏付けとなります。CAMWorksは製造業 CAD/CAM分野で高い評価を受けており、Feature Recognitionや公差ベース加工といった先進機能を多数搭載しています。こうした機能を利用すれば、複数の穴あけ加工を一括して自動化するなど、短い時間で手間を省くワークフローを実現できます。
それでは、SolidWorks CAMの特性についてさらに詳しく見ていきましょう。まずは、SolidWorks CAM全体の概要と、主要機能の背景。そして、それらを支えるCAMWorksベースの技術がもたらすメリットについて掘り下げます。
初めてCAMシステムに触れる方にもわかるよう、複雑な専門用語はなるべく平易な言葉でかみくだいて解説します。
2.1. SolidWorks CAMとは?基本概要
SolidWorks CAMは、SolidWorks StandardやSolidWorks Professional、SolidWorks Premiumなどのライセンスに付随して利用できるCAM機能です。特にSolidWorks 2018以降では、サブスクリプション契約中のユーザーが無償版のSolidWorks CAM Standardをアクティブに利用できます。
この無償版SolidWorks CAMは、2.5軸加工に特化しており、フライス加工や穴あけ加工の自動化など、基本的な製造プロセスをカバーするのに十分な機能を備えています。CAD画面上でツールパスを確認しながら作業できるため、設計段階でミスを減らし、製造現場の効率化を狙えます。
一方で、3軸ミーリングや旋盤加工(ターニング)、高度なポストプロセッサによる制御などは有償のSolidWorks CAM Professional版や上位のCAMソフトウェアで対応していくことが一般的です。ただし、2.5軸を中心とした多くの加工は、SolidWorks CAM Standardでも十分にカバーできることが多いです。
こうした点から、まずは小規模の加工や試作品の製作に取り組む中小企業や教育機関にとって、無償で使えるメリットは大変大きいといえるでしょう。
2.2. 主要機能:Feature Recognitionから公差ベース加工まで
SolidWorks CAMはCAMWorksのFeature Recognition機能を搭載しており、3Dモデル上にある加工すべき部分(穴、ポケットなど)を自動で見つけ出してくれます。これによってNCデータを作成する時間が大幅に短縮されます。
さらに、公差ベース加工と呼ばれる仕組みにも対応しています。これは設計段階で設定した寸法公差情報(サイズのばらつきをどの程度まで許容するか)をそのままCAM工程に組み込み、粗加工と仕上げ加工などを自動判定させることを指します。従来は図面を見ながらこれらの設定を手動で行う必要がありましたが、SolidWorks CAMを使えば設計データをそのまま活かし、自動化を促進できます。
Feature Recognitionと公差ベース加工を組み合わせると、穴あけ加工の自動化やポケット加工のプロセス標準化が一気に進みます。特に中小企業の設計者にとっては、単純作業を減らし、熟練不足の状態でも安定した加工を実現する手立てになります。
このように無償版の機能でも製造現場 効率化を図るためのさまざまなツールが揃っている点は大きな強みといえるでしょう。
2.3. 信頼のCAMWorksベース技術
CAMWorksは、世界的に多くのユーザーに利用されているCamソリューションであり、SolidWorksと長期間にわたり提携してきました。したがって、ベース技術の成熟度が高く、導入直後から安定した加工設定を実践することができます。
また、CAMWorksベースであることから、ポストプロセッサに関しても基本的なものは標準で導入されています。実際にNCデータ 出力を行う際も、一般的なフライス盤やマシニングセンタで用いるGコードをスムーズに生成可能です。
ただし、どうしても特殊な工作機械や複雑な要求に対応したい場合は、SolidWorks CAM Professional版へのアップグレードで追加のポストプロセッサや高度な工具パス制御を導入検討する必要があります。最初は無償版で操作や機能に慣れ、本格的な加工が増えてきた段階でアップグレードする流れが経済的にも無駄がありません。
このように、背景には高い実績を持つCAMWorks技術があり、初めてならではの不安を和らげながら使い始めることができるのがSolidWorks CAMの魅力です。
3. 無償版SolidWorks CAMの機能と限界
無償版のSolidWorks CAMについて語るとき、気になるのはその機能範囲とどこまで実務に耐えられるのかという点です。Basicな部分を押さえているものの、用途によっては物足りなくなるケースもあります。そこで、本節では無償版の具体的な機能と、有償版との違いを比較していきます。
無償版SolidWorks CAM Standardでカバーできる範囲は、設計から製造への橋渡しとして十分に役立つものです。ただし本格的に難度の高い加工や3軸ミーリング、さらには旋盤加工の導入を試みる場合には、別途Professional版などを検討する必要があるでしょう。
比較検討を通して、自社の加工レベルや将来の展望に照らし合わせ、SolidWorks CAMの導入をどう最適化するかイメージしていただければと思います。
3.1. 無償版で利用可能な機能
無料で使えるSolidWorks CAM Standardでは、Feature Recognitionの基本機能を活用し、穴やポケットなど2.5軸加工の基本工程を自動生成できます。具体例としては、以下のような機能が利用可能です。
1. 穴あけ加工 自動化:複数の穴を一度に設定し、深さや工具などの条件を一括管理。
2. ポケット加工:一定深さのくぼみを加工するためのツールパスを簡単に作成。
3. ツールテンプレート:よく使う工具径や回転速度などの加工条件を登録して再利用。
4. モデルの更新にあわせたツールパス 自動更新:CADモデルを改変すると、自動的に加工データが再計算される。
これらの機能を使えば、フライス盤や一般的な工作機械で行うレベルの部品加工に対応できます。効率が高まるだけでなく、ツールパス作成のミスが減るため、すぐに実務で役立つでしょう。
2.5軸を中心とした加工に用途を絞るのであれば、Machiningを始めたばかりの中小企業にとっては極めてコストパフォーマンスの高い選択だといえます。
3.2. 有償版との機能比較
無償版と有償版の大きな違いとしては、3軸ミーリングのサポート、複雑な工具パス生成、旋盤加工機能などが挙げられます。有償版であるSolidWorks CAM Professionalを導入すれば、ボリュームミリングなど高度な切削手法を扱えるようになり、より多彩な工作機械に対応しやすくなります。
たとえば、金型や曲面加工が多い現場では、3軸以上の自由度が求められることが少なくありません。また、大型ワークや高付加価値製品を加工する企業では、Professional版特有の機能を使いこなすほうが長期的に業務効率を高められます。
一方、無償版 solidworks CAM Standardは導入コストを抑えつつ、基本フライス加工や部品の試作などには十分な機能を提供します。これを実務で使い倒し、3軸ミーリングや旋盤加工が増えたタイミングでProfessional版へ切り替えるというステップが一般的です。たとえば、外注先からより高度なNCデータ 出力を求められるシチュエーションもあるため、そうしたときはProfessional版の機能が重宝されます。
健全な設備投資を行うには、自社の現在と将来の加工ニーズを整理し、ベストなタイミングでアップグレードを検討するのが賢明といえます。
4. 誰がSolidWorks CAMを無料で使えるのか?
無償版SolidWorks CAMを利用するには特定の条件があります。特に「SolidWorks 2018以降をサブスクリプション契約中」であることは必須事項です。この点を見落とすと、実際に使用しようとした際にライセンス要件を満たさず、ソフトが起動しないこともあります。
また、教育機関や学生版 SolidWorksならではのライセンス形態にも注目していきます。いずれの場合でも、SolidWorks 無料版を活用することでより多くの人が最新技術を学び、実務に生かす可能性が広がるはずです。
ここからは、対象となるユーザーの種類や、それぞれがどのような条件でSolidWorks CAMにアクセスできるのかを具体的に見ていきましょう。
4.1. 対象ユーザーと利用条件
SolidWorks CAM Standardの無償利用は、基本的には「SolidWorks本体をサブスクリプション契約しているユーザー」を対象としています。サポート契約の一環で無料アドインが付属しているイメージです。
具体的には、SolidWorks Standard、SolidWorks Professional、SolidWorks Premiumのいずれかを導入していれば、該当バージョンのインストールメディア内にCAMが同梱されているため、追加料金なしでインストール可能です。インストール後、アドイン設定画面からSolidWorks CAMを有効化すれば機能が開放されます。
ただし、ライセンス構成の確認は必須です。ライセンスが古すぎる場合やサブスクリプション契約が切れている場合、SolidWorks 2018以降でも無償版CAMが利用できないケースがあります。導入前に自社が保有しているSolidWorksのバージョンと契約内容をいま一度チェックすることをおすすめします。
4.2. 教育機関や学生版の利用可能性
学生版 SolidWorksや教育機関ライセンスであっても、バージョンや契約内容によっては無償版CAMが付属する場合があります。研究室や大学の授業で製造実習を行う際に活用される例が増えており、将来のエンジニアにとって貴重な実践機会になるでしょう。
ただし、教育機関向けは契約形態が一般企業向けとは異なるため、導入できる機能や期間など、制約が設定されることが少なくありません。実際に使える範囲も学習目的に限定される場合もあります。
そのため、学生版を用いてSolidWorks CAMに取り組みたい方は、まずは学校がSolidWorksの何年バージョンを導入しているのかを調べることが大切です。必要に応じて担当教官やシステム管理者に問い合わせ、利用条件を確認するとスムーズでしょう。
5. 無償版SolidWorks CAMの基本機能
2.5軸加工に対応するSolidWorks CAM Standardは、製造の流れをコンパクトにまとめられる貴重なツールです。設計を行うCAD画面からダイレクトにツールパスを確認し、加工工程を最適化できます。ここでは、具体的にどのような基本機能が用意され、実務で役立つかをまとめます。
自動でツールパスが更新されるのは大きな魅力であり、一度属性情報をセットしておけば、設計変更のたびに設定をやり直す必要もありません。実務現場の忙しさを考えれば、この自動化効果はとても大きいと言えるでしょう。
それでは、2.5軸加工に特化した機能と、モデル連携の仕組みについて順番に見ていきます。
5.1. 2.5軸加工の特化機能
無償版SolidWorks CAMが得意とする「2.5軸加工」とは、X,Y方向へ自由に動かしながらZ軸の高さを一定刻みで上下させる切削方式を指します。機械加工全般では、穴あけ、ポケット加工、外周加工などがこれに該当します。
たとえば、複数個の穴あけ加工を一挙に定義し、深さやドリル径を簡単に決めることが可能です。さらに、公差ベース加工のセットを活用することで、下穴と仕上げ穴を切り分けるといったステップも自動制御できます。
小型の部品試作や板金用の部品製作などでは2.5軸で十分対応可能なケースが多く、中小企業が日常的に扱う加工ならなおさらです。高精度までは求めないが、小回りの効く加工が必要な状況で、SolidWorks CAM Standardが強力な助っ人となります。
5.2. モデル連携と自動ツールパス更新
設計変更が頻繁に起こる製造現場の効率化の要として、ツールパスの自動更新は欠かせません。SolidWorks CAMが有する特徴の一つが、CADモデルとCAM工程を一元的に扱う仕組みです。つまり、設計データで穴の直径を変更したり、部品形状を修正した場合にも、CAM側でその変化を検知して新しいツールパスを生成します。
これは「自動ツールパス生成」あるいは「ツールパス 自動更新」といわれ、特に図面レス加工を進めたい企業にとって大きな強みです。設計から製造までの情報が一貫しているため、ソフト間でデータを転送する手間や、手作業によるミスのリスクを減らせます。
もちろん、モデル変更後にはツールパス設定をチェックした上で実行する必要がありますが、それでも一から作り直すよりはるかにスピーディーです。こうした自動化によって、スケジュールの厳しいプロジェクトでも柔軟な対応が可能になります。
6. 実務での無償CAMの活用術5選
SolidWorks CAM Standardを使った2.5軸加工は、限られたリソースでの試作や初期生産にうってつけです。ここでは、その具体的な活用シナリオとして、5つの実用例を紹介します。いずれも特別なカスタマイズを要しない方法であり、そのまま実務に転用しやすい内容となっています。
ソフトの導入だけでなく、作業手順の標準化や設計フローの整理と組み合わせると、さらに効果を高められます。たとえば、ツールテンプレートの活用は工具や加工条件を統一化することにつながり、会社内での作業品質を安定させる一助となります。
ぜひ、これから紹介する活用例を参考に、現在の生産体制に落とし込んでみてください。
6.1. 穴あけ加工の自動化と図面レス加工
複数の穴を持つ部品を加工する場合、従来は図面を参照しながら一つひとつの穴をプログラムに打ち込んでいました。しかし、SolidWorks CAMのFeature Recognition機能を使えば、モデリング段階で設定した穴の情報が認識され、深さや径、位置情報をまとめて反映できます。
これにより「穴あけ加工 自動化」が実現され、図面レス加工の第一歩となります。部品点数が多いほど、この効率化の恩恵は大きく、穴の数が多いプレート部品などで大いに威力を発揮するでしょう。
実際の製造現場では、図面を印刷する時間やヒューマンエラーが削減され、しかもツールパス修正の手間も少なくなります。こうした小さな積み重ねが、プロジェクトの予算削減やスケジュール短縮につながります。
6.2. ポケット加工での工程統一
ケースやハウジングの内部をくり抜くポケット加工は、機械部品を設計するときによく見かける工程です。SolidWorks CAM Standardなら、カットする範囲を選択するだけで自動ツールパス生成が行われ、工具径や切削条件もテンプレート化できます。
このポケット加工をまとめて管理すれば、各部品を統一的に加工できるため、バラつきが減り、品質の安定にもつながります。さらに、穴あけや外周加工など他のプロセスとの組み合わせも容易なので、工程順をシンプルに保てるのです。
たとえば、製品ごとにポケット形状が若干変わる場合でも、モデルデータを差し替えればツールパスが自動更新されるので、手作業によるプログラム修正は最小限です。結果的にリピートオーダーへの迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上やリードタイム短縮につながります。
6.3. ツールテンプレートによる加工条件の標準化
SolidWorks CAMにはツールテンプレート機能が用意されており、送り量や切削速度、ステップダウン量などの加工条件をあらかじめ登録しておけます。これにより、同じ工具を使う加工であれば、ボタン一つで設定を呼び出すだけでOKです。
現場によっては、熟練作業者が個々にノウハウを持っているため、工具選びや切削条件がまちまちになることがあります。テンプレート化を進めれば、新人でも一定水準以上の加工を行いやすくなるため、品質を安定させつつミスの削減が狙えます。
また、外注先や他部署にCAMデータを渡す際も、ツールテンプレートを共有すれば情報のズレが少なくなります。合理化できるポイントを一つひとつ潰していくことで、全社レベルでの製造現場 効率化に貢献できるでしょう。
6.4. 設計変更時の自動再計算
設計段階で生じる細かな修正にも、SolidWorks CAMの自動ツールパス再計算機能が威力を発揮します。製品の外形や穴の位置が変更されても、CAM側で新しい形状を読み取り、ツールパス 自動更新が行われます。
これにより、従来は再度プログラムを一から作り直していた手間が大幅に軽減されるのです。結果として、設計者自身がCAMデータの変更を素早くこなし、プロトタイプの試作や量産への移行をスムーズに行えるようになります。
プロジェクトスケジュールが厳しい場合、リワークにかかる時間を最小化できることは大きなアドバンテージです。さらに、手戻りを減らすことでコストを抑えられるため、企業規模を問わず、この機能の恩恵は大きいといえます。
6.5. 公差設定の最適化
公差ベース加工を利用すれば、設計時に設定した寸法公差や仕上げ指示を自動的に読み取り、粗取りから仕上げ加工までが一貫して管理できます。たとえば、部品の重要寸法には厳しい公差を適用し、それ以外の部分ではゆるめの公差を設定して加工時間を短縮するといった戦略が可能です。
結果的に、無駄な切削工程が減り、必要なときに必要な精度だけを確保する合理的なプロセスを実現します。これはコスト削減にも直結し、短時間で高品質の製品を生み出すための根拠となるでしょう。
多くの設計者にとっては、モデル上の公差情報がCAM工程に直結するメリットは計り知れません。十分に退避量を考慮した粗加工や、最終仕上げの切込量などを自動調整できるため、経験豊富なオペレーターがいない場合でも安定した加工品質を獲得しやすくなります。
7. まとめと発展: Professional版へのアップグレード検討
ここまで紹介してきたように、2.5軸加工を主とする無償版のSolidWorks CAM Standardでも、製造フローの効率化を十分に図れます。しかし、より複雑な形状や多様な工具を活用する工程が増えれば、SolidWorks CAM Professional版へのアップグレードを検討すべき時が訪れます。
たとえば、3軸ミーリングを頻繁に使う製品設計や、旋盤加工(ターニング)に対応しなければならない場合は、Professional版が持つ高度な機能が必要となります。外注先への拡張的なNCデータ 出力を求められるケースや、カスタムポストプロセッサによる複雑な加工プロセスの管理にも適しています。
もちろん、アップグレードにはライセンス費用や導入の手間が伴います。さらにツールを使いこなすためには社内教育やワークフロー整備が必要でしょう。ただし、設計から製造までのトータルコストを削減でき、競争力を高められるのであれば、一度検討する価値は十分にあるはずです。
7.1. アップグレードのタイミングとメリット
一般的には、以下のような状況が訪れたときに、Professional版に切り替えるパターンが多いようです。
1. 3軸ミーリングやボリュームミリングが必要な複雑形状の部品が増えた。
2. 旋盤加工を自社で完結させたいが、無償版では対応できない。
3. 製品ラインナップを広げ、社内や外注先へのNCデータ 出力を高効率化したい。
4. 社内ルールに合わせてポストプロセッサを細かくカスタマイズしたい。
これらの要件に対してProfessional版へのアップグレードを行えば、より高度な加工機能やカスタマイズ性、高度な工具パス制御が利用できるようになります。最終的には、製品の付加価値を向上させるだけでなく、生産性を高めることで企業全体の競争力向上にも寄与するでしょう。
ただし、タイミングを誤ると過剰投資になりかねません。まずはSolidWorks CAM Standard(無償版)を使い倒し、CAD/CAM統合によるメリットがどの程度自社の業務改善に貢献するか、実際のデータを通じて検証することをおすすめします。そこから、必要性が明確な時期にステップアップを行うのがベストな選択です。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
SOLIDWORKS CAM
https://www.solidworks.com/ja/product/solidworks-cam
SOLIDWORKS CAMで設計から製造までを網羅
https://www.solidworks.com/ja/media/design-manufacture-solidworks-cam
SOLIDWORKS 新規機能 2024-SOLIDWORKS
https://help.solidworks.com/2024/japanese/WhatsNew/c_wn_cam.htm
SOLIDWORKS 新規機能 2025-SOLIDWORKS
https://help.solidworks.com/2025/Japanese/WhatsNew/c_wn_cam.htm
SOLIDWORKS顧客事例 株式会社デンソー
https://www.solidworks.com/ja/story/denso