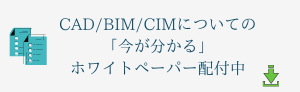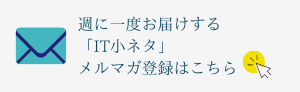DIY革命!3Dプリンターで作れる便利工具10選と作成方法
1. はじめに:DIYと3Dプリンターの革新的な組み合わせ
DIY(Do It Yourself)は、自分の手でモノを作り上げる創造的な行為です。近年では3Dプリンターの普及により、金属加工や木工のように専門的な技術が必要だった自作工具づくりも、より身近になりました。
3Dプリンターを使えば、CADソフトで作った3Dモデルを基に、3Dプリンティングという方法でプラスチックなどの材料を積み重ねて成形できます。これにより、従来は高コストだった「カスタムメイドの道具」も、比較的低いコストで実現しやすくなりました。
しかも自作工具だけでなく、ちょっとした便利グッズの作成も可能です。例えば歯ブラシ立てやケーブルクリップなどをDIY工具と一緒に設計すれば、作業場だけでなく日常生活のシーンでも役立ちます。
この記事では、3Dプリンターという革新的な技術がDIYをどのように変えるのか、そして実際にどんな「自作工具」や「便利グッズ作成」ができるのかをご紹介します。プロのエンジニアや技術者の方が業務や趣味に役立てられる具体的なメリットや方法にも触れますので、ぜひ最後までお読みください。
2. 3Dプリンターの基本とその可能性
3Dプリンターは、デジタルデータをもとに立体物を作り出す装置です。代表的な方式として、熱で溶かした樹脂(フィラメント)をノズルから少しずつ押し出し、層状に積み上げるFDM(熱溶解積層)方式が知られています。必要な準備としては、スライサーソフトで3Dモデルを読み込み、積層の厚みやフィラメントの種類を設定する「3Dプリント設定」作業があります。
3Dプリンターメンテナンスも重要です。ノズルの詰まりやベッドレベリングなど、定期的な点検を行うと失敗が少なく、安定的に高品質な印刷が続けられます。こうしたメンテナンスの手間を惜しまないことで、いわゆる「使いたいときに使える」状態を保つことができます。
また、最近の3Dプリンターでは、PLA・PETG・ABSなど種類豊富なフィラメントが使用できるため、用途に合わせて選べる強みがあります。例えば、心棒が必要なバイスケースには耐久性の高いABS、あるいは少し柔軟性のあるTPUでドアストッパーを作る、といったカスタマイズも自由自在です。
では、実際に3Dプリンターでどんなアイテムが作れるのでしょうか。次項では、DIY工具を中心に幅広く例を挙げて可能性を探ってみます。
2.1. 3Dプリンターの仕組みとは?
3Dプリンターは、まず3Dモデルのデータをスライサーソフトで読み込み、レイヤーごとの指示を造形用ファイルに変換します。そのファイルをプリンターに送り、ノズルからフィラメントを少しずつ押し出して積み上げていく方式です。
具体的には、ベッドと呼ばれる平面上に最初の層を敷き、その上に2層目、3層目と積み重ね、最終的に立体を完成させます。各レイヤーの厚みは0.1mmや0.2mm程度に設定されることが多いため、積み上げる作業にはある程度時間がかかります。
印刷中は、サポート材が必要な箇所(例えば大きく突き出した部分)に合わせ、プリンターが自動的にサポート構造を生成します。完成後に取り除く必要がありますが、サポート材除去ツールを用いると作業効率がぐんと上がります。
この層を重ねていく仕組みのおかげで、複雑な形状や既製品にはないカスタム形状を作りやすい、という大きなメリットがあります。
2.2. 3Dプリンターで作れるアイテムの種類
3Dプリンターを用いて作れるものには多種多様な例があります。例えば、日常で使うスマホスタンドや歯ブラシ立てといった小型グッズだけでなく、DIY工具や精密計測用の治具も作成できます。
また、マヨネーズスタンドやケーブルマネージメント用のクリップ、さらにパーツトレイや収納ボックスといった整理・収納に役立つものも人気です。用途に合わせて3Dモデルさえ用意すれば、自由に大きさや形状を変えるカスタマイズができるのも大きな魅力です。
その他に、スピードスクエアやモンキーレンチのように作業に必要な道具をあらかじめ自作しておくことで、自分の手にしっくり合うものを手軽に手に入れられます。これにより、プロフェッショナルな現場でも作業効率を高める貢献が期待できます。
そうした様々な種類の中でも、本章では「DIY工具」に焦点をあて、便利な10の例を次で詳しくご紹介します。
3. 便利なDIY工具10選
ここでは、3Dプリンターで手軽に作成できる便利なDIY工具を10種類挙げました。部品の固定や測定から後処理にいたるまで、さまざまな局面で役立ちます。それぞれの工具が作業効率や作業精度の向上につながる仕組みと注意点を解説します。
本来なら金属製や市販品として用意された工具も、3Dプリントで自作工具にすればカスタマイズや修正が簡単です。使っているうちに壊れたり改良のアイデアが浮かんだりしたら、新しい3Dモデルを少し修正して再度プリントするだけで、独自の最適化が進められます。
ただし、工具の種類によっては負荷が大きくかかる場合もあります。例えばモンキーレンチやバイスのように強税力を要する道具をフルプラスチックで作ると、用途によっては強度不足になるかもしれません。そのため、強い樹脂や金属部品との組み合わせを考慮するなど、使い方に合わせた材料選びや設計を行うことが重要です。さらに、樹脂製特有の摩耗問題もあるため、必要に応じて交換部品を容易に用意できるようにすると安心です。
これから紹介する10選はあくまで例ですが、組み合わせ次第でカスタムスタンドやサポート材除去ツールなど様々な「便利グッズ作成」への応用が効きます。実際の用途に合わせて自由な発想で挑戦してみてください。
3.1. デジタルノギス:精密な測定が可能に
デジタルノギスは、長さや厚みを正確に測定するための工具です。3Dプリンターで外装や補助部品を作成すると、センサー部分は市販品や流用パーツを組み合わせることで完成させられます。
具体的な作成手順としては、CADソフト上で外装パーツの3Dモデルを設計し、既存の計測ユニットがスライドする溝を設計します。計測用のバー部分をメタルレールとして用意することで、プラスチック特有の反りや摩耗を防ぐ工夫を加えるのもおすすめです。
さらに、USB接続可能なセンサーを取り付け、PCで数値を読み取れるよう改良する例もあります。DIY工具として独自に拡張することで、プロフェッショナルな現場でも使いやすい革新的なデジタルノギスが出来上がります。
測定が重要な仕事をしているエンジニアや技術者にとって、作業精度の向上は大きなメリットです。自作することで測定範囲を拡張したりサイズを調整したりできるため、自分の用途にぴったり合ったノギスを作成できます。
3.2. バイス:作業中の部品固定用
バイスは、部品をしっかりと固定しておくための道具です。3Dプリンターで作成する場合は、ネジやボルトを通すための穴を設計に組み込んでおくと、金属パーツとのハイブリッド構成が可能になります。
例えば、樹脂製の本体に市販ボルトとナットをはめ込むことで、強い固定力を確保できます。さらに、ベース部分に吸盤を取り付ける構想も考えられ、机の上に設置しておくのに便利です。
バイスを使えば、手作業中に材料がずれにくく、手を離しても安定した状態を維持できます。これにより仕上げ作業や穴あけ、接着などのDIY工程が効率的になります。
大型のバイスが必要な場合は、強度面を配慮してABSやPETGといったフィラメントを使うか、金属補強材を組み合わせることをおすすめします。実際の作業負荷を想定した仕様に設計するのがポイントです。
3.3. サポート材除去ツール:後処理の手間を軽減
3Dプリントでは、造形時にサポート材が発生することがあります。これは本体の空中部を支えたり、オーバーハング箇所を成形しやすくするために必要ですが、完成後には取り除かなければなりません。そこで役立つのが、サポート材除去ツールです。
先端部を薄いヘラ状にしたり、細かな溝に届くピック状のパーツをレイアウトするなど、サポートを効率良く掻き出す形状に工夫を凝らすことができます。
作り方としては、CADソフトで細長いツールを設計し、持ちやすいグリップを備えておくと便利です。握りやすさを追求するなら、滑り止め形状を付けると作業性が向上します。
仕上げとして、先端を紙ヤスリでさらに薄く整えたり、サンディングブロックホルダーを併用して全体を表面処理したりすると使いやすいツールになります。
3.4. ケーブルクリップ:整理整頓の強い味方
ケーブル類が多すぎると、デスクや作業テーブルが散らかり、見栄えが悪いだけでなく事故を誘発する恐れもあります。そこを解決してくれるのがケーブルクリップです。
ケーブルクリップは、小さなフック状の部品にケーブルを挟んでまとめる形が一般的です。3Dプリンターで作れば、机の縁に合わせた曲面デザインやケーブルの太さに合わせた大きさを自由に設計できます。
固定方法としては両面テープやネジ止めなどがあります。しっかり固定するならネジ、取り外しを重視するならテープタイプがおすすめです。ケーブルマネージメントの一環として、複数のクリップを組み合わせるとさらにキレイに整理整頓できます。
こうした自作クリップを使えば、用途が増えるたびに新しいサイズを追加作成でき、個人の作業スタイルに合ったケーブル管理が可能になります。
3.5. パーツトレイ:小さな部品の整理に
DIY作業で釘やネジ、電子部品など小さいパーツが散らばると、紛失のリスクが高まったり、作業効率が低下したりします。そこで役立つのがパーツトレイです。
3Dプリンターでパーツトレイを作成すれば、区画を仕切って複数の部品を分類できるほか、トレー自体の大きさや深さも自由に変えられます。自分のプロジェクトに合わせて容量を調整できるのがメリットです。
形状の工夫として、重ねて収納できたり、スタッキングできるよう突起や凹みを設計に入れることもあります。また、取っ手を付けて持ち運びやすくしたり、フタを付けて埃が入りにくくするアイデアを盛り込むことも可能です。
必要なパーツを視覚的に把握できるため、組み立て作業中に「あれが見つからない」といった無駄を減らせます。
3.6. スピードスクエア:正確な角度測定
木工作業などで用いられるスピードスクエアは、板材などに正確な90度や45度の線を描くときに使う三角定規のような道具です。DIY工具の定番でもあり、市販品も多数あります。
しかし3Dプリンターを活用すれば、特定の溝やマグネットホルダーを備えたオリジナル設計が可能です。例えば、定規の端にメジャーが収納できるスペースを作ったり、小物用の収納が一体化したスピードスクエアを作成できます。
作る上では、正確さが非常に大切なので、CADデータを作り込む際には寸法精度を徹底しましょう。プリンターのベッドレベリングが狂っていると角度に誤差が生じる場合もあるので、事前にしっかり調整しておきます。
このように、本来金属製でなければならない箇所も、木工作業用であればプラスチック製でも充分機能します。角度の狂いなく仕上げるために、印刷後の計測や補正加工も適宜実施してください。
3.7. サンディングブロックホルダー:疲れにくい設計
手作業での研磨は、握力が必要なうえ、長時間行うと手先が疲れてしまいがちです。そんなときに役立つのがサンディングブロックホルダーです。
通常のペーパーやすりを巻き付け、ホルダーにはめ込むだけで使えます。人間工学を意識した形状にし、持ち手にフィットする湾曲を付けておくと疲れにくくなります。さらに手首の角度を補助する形に設計すると、より快適に作業できます。
作り方もシンプルで、CADソフトでブロック形状を設計し、中央部分にペーパーを固定するための溝やクリップ構造を設ければ完成です。後からホルダー部分だけを交換したり、サイズ違いをそろえたりして作業内容に合わせて選べるようにしておくと便利です。
DIYばかりでなく、模型工作や小物の加工などでも重宝します。手軽に印刷できるので、初めての自作工具として挑戦するのもおすすめです。
3.8. デバリングツール:仕上げ作業の効率化
デバリングツールは、バリ取りやエッジの滑らか化に重宝します。樹脂成形品でも金属加工面でも、鋭い余分な部分をそぎ落とすための専用工具として、業務用にもよく使われます。
市販の刃先やカッター部分を装着できるようにグリップだけ3Dプリントする方法が代表的です。刃が交換できる設計にしておくと、消耗品である刃先だけ取り換えられます。同時に自分の手の大きさに合わせて太めのグリップを作れば、疲れにくくなるというメリットも得られます。
また、刃の種類を切り替えられる構造を備えることで、さまざまな材質や形状に対応可能です。特定の現場では穴の内側を削る専用のツールなどを作り、自作工具で効率アップする事例も珍しくありません。
DIY工具ならではの強みは、とにかく自由なサイズや形状で作れることです。エンジニアの新発想を活かし、ユニークなデバリングツールを考案してみましょう。
3.9. フィラメントホルダー:整理とアクセスの向上
3Dプリンターを頻繁に使うなら、フィラメントのストックをきちんと管理する必要があります。そこに役立つのがフィラメントホルダーです。スプールを吊り下げたり、複数スプールを並べて保管したりできるように、独自の構造をデザインできます。
例えば、3Dプリンターの上部に取り付けられるフック型や、横に巻き取るリール型など、レイアウトの自由度が高いです。さらにフィラメントが引っかからないよう、滑車やベアリングを仕込む作りにしておくと、スムーズなフィラメント供給が期待できます。
フィラメント選択も重要ですが、どんな素材を使うにしても、絡まってしまうと印刷中にトラブルが起こるリスクが高まります。自作フィラメントホルダーで整理状態を保つことで、失敗プリントを減らし、生産性を向上させる効果があります。
また、ホルダー自体の素材にはPLAで十分な場合が多いので、簡単に追加作成してストックしておけば、急な作業にも対応しやすくなります。
3.10. カスタムスタンド:特定のニーズに応じた設計
最後に紹介するのが、カスタムスタンドです。スタンドは、その名の通り何かを支えるための道具であり、スマホスタンドやカード置き、マヨネーズスタンドのように身近な用途がたくさんあります。
3Dプリンターなら、形状をユーザーのニーズに最適化できます。例えば、作業机に合わせたペン置きや、収納ボックスの上に乗せられるスマホスタンド、モンキーレンチを収納できるホルダーなど、自由なアイデアが形にしやすいのが魅力です。
設計時には、支えたい物の重量やサイズに応じた強度計算も考慮してください。重めの工具スタンドを作る場合は下部を厚めにし、バランスを重視すると倒れにくくなります。
自分専用のスタンドを作っておけば、DIY作業の合間にスマホを立てて動画マニュアルを確認したり、すぐ手に取りたい工具を整然と並べたりできます。こうした小さな工夫が、トータルの作業効率に大きな効果をもたらします。
4. 3Dプリンターを使った工具の作成プロセス
ここでは、実際に3Dプリンターを使って自作工具を作り上げるまでの流れを、3ステップで解説します。アイデアを思い付いたら、CADソフトで形を具体化し、最終的に印刷・仕上げを行う、という流れです。
このプロセスを理解することは、自分の作りたいDIY工具を思い通りの形に仕上げるうえで非常に大切です。思いつきで設計をすると、いざ印刷してみてサイズが合わない、可動部がうまく機能しない、という失敗にもつながりかねません。
逆にしっかりプロセスを踏めば、必要な強度や精度を持ったアイテムが作りやすくなります。以下に示す工程を順守しつつ、柔軟に修正や改良を加えていきましょう。
また、各ステップでのコツとしては、構想段階で想定する使用シーンや、実際にかかる力の方向などをよく考えることです。実験や試作を重ねて、失敗を糧にすることも上達の近道です。
4.1. アイデアの具体化:必要な工具を想像する
まず最初のステップは、何を作りたいのか明確にすることです。例えばサンディングブロックホルダーなら「研磨作業時の疲労を抑えたい」といった目的があります。そこで、手のひらにフィットする形状や、サンドペーパーを固定しやすいリング構造を取り入れるなどのアイデアが具体化します。
また、DIYプロジェクト全体を見渡してみましょう。もし電子部品が多いならパーツトレイが役立ちますし、大がかりなものを組み立てるなら、バイスやフィラメントホルダーが重宝します。
この段階では、紙にSketch(スケッチ)を描いたり、頭の中で使用シーンをシミュレーションしたりします。またオンラインコミュニティを参考にして既存の3Dモデルのアイデアを取り入れるのも良い方法です。
具体的なサイズや形状、および強度要件を整理しておくと、次のCAD設計にスムーズに移れます。
4.2. 3Dデータの作成:CADソフトを使った設計
アイデアが固まったら、CADソフトで3Dモデルを作成します。Fusion 360やFreeCAD、Tinkercadなど、初心者から上級者まで様々なソフトが選択肢として存在します。
設計時に意識するポイントは、可動部がある場合はクリアランス(隙間)を確保すること、強度が必要な部分は厚みやリブ(補強)を付けることです。特にバイスなどは外力が大きくかかるため、コーナー部を丸めるなどの工夫が必要です。
一通り3Dモデルが完成したら、STLやOBJといった形式でエクスポートして、スライサーソフトに読み込みます。ここで積層ピッチ(レイヤーの厚さ)や充填率(インフィル率)、サポート材の有無などを細かく設定しましょう。
もし強度を重視するなら充填率を高める、仕上げを綺麗にしたいなら層の厚みを薄くするといった調整ができます。最適なバランスを見つけるためには、何度かテスト印刷することが大切です。
4.3. 印刷と仕上げ:3Dプリンターでの出力
スライサーソフトで設定を終えたら、いよいよ造形を開始します。装着するフィラメントの種類は、用途によって選んでください。例えば、衝撃に強いPETGやABSなら工具としての耐久性を高めやすいです。
プリント中は、造形物が台(ベッド)から剥がれないようにチェックし、ノズル閉塞やフィラメントの絡まりにも注意します。特に大型のパーツを印刷するときは、造形時間が長くなるため、途中の確認が欠かせません。
造形が終わったら、サポート材の除去やデバリングツールによるバリ取り、サンディングブロックホルダーでの磨きなどの後処理を行います。最終的には、一度動かしてみて問題点がないか確認し、必要があれば小修正を加えて再度印刷することもあります。
こうした一連の工程を踏むことで初めて理想の自作工具が完成します。時間と手間は多少かかりますが、その過程こそがDIYの醍醐味です。
5. 3Dプリンター活用のメリットと未来
3Dプリンターを使ったDIYは、ただの趣味にとどまりません。コスト削減や生産性の向上、さらには技術進化によって将来的にもさまざまな可能性が広がっていくことが期待されています。ここまで紹介した便利な工具や小物だけでなく、今後はより複雑な形状の部品や、部材を組み合わせたハイブリッド製品も気軽に作れるようになるでしょう。
特定の業種や制作現場では、3Dプリンティングによる迅速な試作品の作成や既存設備との組み合わせなど、実務レベルでの導入が進んでいます。個人でもCADソフトの学習や小型3Dプリンターの導入コストが下がったことで、作業環境を自由に最適化する人が増えています。
エンジニアや技術者にとっても、必要な道具を必要なときに素早くカスタマイズして使えるのは大きな利点です。自分だけのツールを作る過程で得られる知識やノウハウは、他の業務にも応用できます。逆にDIYから発見したアイデアが、工場やラボの現場改善につながるケースも多く見られます。
最後に、これからの展開として、マルチマテリアル対応の3Dプリンターや、新しいフィラメント(例えばカーボンファイバー配合など)の登場により、さらに性能や精度が上がっていくと考えられます。以下のようなメリットと事例を知れば、今後のDIYライフや業務効率化へ活かしやすくなるはずです。
5.1. コスト削減とカスタマイズの自由度
3Dプリンターを導入すると、最初の購入費用や定期的なフィラメントの出費はありますが、必要な時に道具をスポットで作れる利便性が得られます。市販品を買うよりも安上がりになるケースが多く、とくにたくさんの部品や工具を用意する現場ではコスト削減効果が顕著です。
また、市販品にはない細かい仕様を実現できることも大きな利点です。例えば収納ボックスひとつ取っても、引き出しの寸法にぴったり合う形にデザインしたり、取っ手の形を使いやすいよう変更したりできます。
自分に合ったツールを作ることで、作業効率やモチベーションも向上します。試作や小ロット生産が簡単に行えるため、短期的なプロジェクトやカスタム部品が必要なプロのエンジニアにもぴったりです。
さらに、壊れたり不具合が出ても、該当パーツだけを再度プリントすれば交換できる柔軟性もあります。そうした利点が重なり、DIY工具や便利グッズ作成における新たな革命が起こっているといえます。
5.2. DIYプロジェクトへの応用例
3DプリンターとDIYは非常に相性が良く、使い道は無限に広がります。例えば、家の修繕や改装に合わせてドアストッパーやカーテン留め具を作る、配線が煩雑になったパソコンデスクにケーブルマネージメントツールを追加するなど、さまざまな工夫が可能です。
マヨネーズスタンドやサンドペーパーホルダーといったキッチンや作業用の小物は、そのまま3Dモデルサイトからダウンロードしてもいいですし、そこに手を加えてオリジナル版に変えることもできます。
また、大がかりなDIYプロジェクトでは、部品を分割して印刷・組み立てる考え方もできます。例えば、一時的に使う型枠やジグなどは木工では作りにくい曲面や細かい溝が必要な場合でも、3Dプリンティングなら対応しやすいです。
こうした活用例を積み重ねると、手作業による不確定要素が減り、失敗コストを最小限に抑えることが期待できます。
5.3. 技術進化による新たな可能性
3Dプリンターの技術はまだまだ進化の途中です。今後、より高速で積層速度の速い機種や、複数の樹脂を同時に扱えるマルチマテリアルプリンターなどが普及すれば、自作工具の品質やバリエーションも飛躍的に増えるでしょう。
カーボンファイバー入りのフィラメントや、特殊金属粒子を含むフィラメントなどが既に出回っており、一部では切断工具の刃のように強度を要する部分も成形可能になりつつあります。こうした材料の選択肢が増えれば、モンキーレンチの可動ジョーや、高負荷なバイスの本体部分すら自作できる可能性が開けてきます。
また、より簡単に3Dモデルを作れるソフトウェアや、3Dスキャン技術が充実すれば、実物の部品をスキャニングしてそこに合わせたパーツを瞬時に設計するといった使い方も加速するはずです。
やがてはDIY工具や日常アイテムだけでなく、家電やロボットのパーツを作る時代が一般ユーザーの手に届くかもしれません。プロフェッショナルはもちろん、中学生でも楽しみながら工作できるさまざまな可能性が、今後の3Dプリンティング技術に期待されています。
6.3Dプリンターのモデルデータの入手先
(様々な3Dプリンター作品が見られます。)
| Thingiverse | 老舗サイト。DIY・工具カテゴリが充実。 | |
| ・Search Thingiverse – Thingiverse https://www.thingiverse.com/ | ||
| Printables | Prusa社提供。クオリティの高いデータ多数。 | |
| ・3D models database | Printables.comhttps://www.printables.com/ | ||
| MyMiniFactory | STLだけでなく印刷成功情報(Make)も参考になる。 | |
| ・Discover STL files for 3D printing ideas and high-quality 3D printer models. | MyMiniFactoryhttps://www.myminifactory.com/ | ||
| Cults 3D | 有料/無料が混在。高品質なデザインが多い。 | |
| ・Cults・Download free 3D printer models・STL, OBJ, 3MF, CADhttps://cults3d.com/en |
7.まとめ
3Dプリンターは、従来では実現しにくかったカスタム工具や便利グッズを低コスト・高自由度で作成できる革新的な技術です。本記事では、デジタルノギスやバイス、パーツトレイなど実用的なDIY工具10選を紹介し、それぞれの活用方法や作成のコツも詳しく解説しました。さらに、アイデアの具体化から設計、印刷、仕上げまでのプロセスも丁寧に紹介。3Dプリンターは趣味にとどまらず、現場での業務効率化や創造性の発揮にもつながります。技術の進化とともに、その可能性はますます広がっていくでしょう。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
・いまさら聞けない 3Dプリンター | リコー