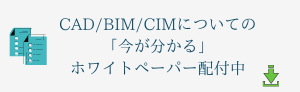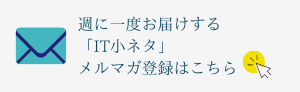CNCソフトウェア入門|おすすめのツールと選び方を解説
1. はじめに
CNCソフトウェアは、コンピューター制御による加工を行う際に欠かせない存在です。近年では、ホビー用途からスタートアップ、小規模工房、さらには大手の製造業まで、さまざまな分野でCNC加工が活用されるようになってきました。
特にCNCをこれから始めようとする初心者にとっては、「どのソフトを使えばいいのか?」という選択が最初の大きな壁になります。選んだソフトによって操作の習得スピードや加工の品質が大きく変わるため、この選択はとても重要です。
この記事では、CNCソフトウェアの基本的な仕組みから、初心者におすすめのツールや選び方のコツまでをわかりやすく解説します。難しそうに見えるCNCの世界も、仕組みを理解すれば意外とシンプルです。
まず「CNC(Computer Numerical Control)」とは、コンピューターによって工作機械の動きを自動制御する技術です。CNC加工では、CADソフトで設計した図面や3DモデルをCAMソフトで加工パスに変換し、最終的に「Gコード」と呼ばれる命令として機械に送信します。この一連の流れを支える中心的な存在がCNCソフトウェアです。
CNCソフトをうまく活用できれば、手作業では難しい複雑な形状も、正確かつ短時間で加工できます。CADとCAMが統合されたソフトを使えば、設計から加工準備までをひとつの画面で完結できるため、作業効率も大きく向上します。
この記事を通じて、自分に合ったCNCソフトを見つけ、スムーズに加工を始められるヒントを得ていただければと思います。
2. CNCソフトウェアの種類と基本構成
引用:https://www.autodesk.com/jp/solutions/cnc-programming
CNC加工をスムーズに進めるには、ソフトウェアの基本的な種類と、それぞれがどのように連携しているかを理解することがとても大切です。CNCでは大きく分けて3つのソフトが関係します。まず、CADソフトで図面やモデルを作成し、次にCAMソフトでそのデータをもとに加工条件を設定、最後にGコード送信ソフトを使って、実際にCNCマシンを動かします。
これら3つのソフトは、それぞれ単独で使えるものもありますが、CNC加工を行う際にはこの順序で連携させる必要があります。たとえば、CADで描いた設計図をそのままマシンで削ることはできません。CAMを通して、工具がどのように動くか(ツールパス)を決める処理を行い、それを数値化したGコードとしてCNCマシンに送る必要があります。Gコードは、マシンの動きをミリ単位で正確に制御する命令の集合です。
さらに、近年ではこれらをひとつのパッケージにまとめたCAD/CAM統合ソフトも増えており、設計から加工までを一つのソフトで完結できるケースもあります。たとえば「Autodesk Fusion」などは、設計・加工・シミュレーションなどを一括で扱える代表的なツールです。統合ソフトを使うことで、ファイルのやり取りや形式変換によるトラブルが減り、初心者にとっても扱いやすい場合があります。
2.1. CADソフトウェアの役割
CAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアは、CNC加工において「設計図を描く」ためのツールです。加工の第一歩は、作りたい形状や寸法を図面や3Dモデルとして表現することから始まります。この段階で使用するのがCADソフトです。
CADソフトには、2D図面作成に特化したものから、3Dモデリングやアセンブリ(部品の組み合わせ)機能まで備えた高機能なものまで、多くの種類があります。たとえば、AutodeskのAutodesk Fusionは、3Dモデリングに対応した統合型ソフトで、個人利用や学習用途では無料で使えるプランもあります。FreeCADのようなオープンソースソフトは、無料ながらも強力な機能を備えており、カスタマイズ性にも優れています。
2.2. CAMソフトウェアの機能
CAM(Computer-Aided Manufacturing)ソフトウェアは、CADで作成した図面やモデルを実際に加工できる形に変換する役割を持っています。具体的には、素材の種類や工具の大きさ、回転速度、送り速度などの条件を設定し、ツールパス(刃物の動きの軌跡)を自動で計算・生成します。
このツールパスが正しく設定されていれば、素材を無駄にせず、工具への負荷も抑えながら効率よく加工することが可能です。逆に、パスの設定が不適切だと、工具が破損したり、加工ミスが発生したりする恐れがあります。CAMは、CNC加工の中でも「品質と安全性を左右する」重要なステップです。
CAMソフトには、初心者向けの軽量なツールから、産業用の高機能ソフトまでさまざまな種類があります。たとえば、「Carbide Create」や「Estlcam」は、2.5D程度の比較的シンプルな加工に特化しており、はじめてCAMを触る人に適したソフトです。操作も直感的で、ツールパスの可視化やシミュレーションも可能です。
2.3. Gコード送信ソフトウェアの重要性
CAMソフトで生成されたGコードを、実際にCNCマシンに送って動かす役割を担うのがGコード送信ソフトです。このソフトは、マシンとの通信を担当し、加工の開始・停止、工具の動作、軸の移動などをリアルタイムで制御します。
代表的な送信ソフトには、「UGS(Universal Gcode Sender)」や「bCNC」などがあります。どちらも無料で使えるオープンソースソフトであり、DIYユーザーやホビー用途のCNC環境で広く利用されています。UGSはJavaベースで開発されており、Windows/Mac/Linuxいずれでも動作するマルチプラットフォーム対応。bCNCはPythonで構築されており、編集機能やスクリプト機能も備えた上級者向けの送信ソフトです。
Gコード送信ソフトは、単にコードを送るだけでなく、マシンのステータス確認や加工中の操作に重要な役割を果たします。たとえば、スピンドルの回転速度を制御したり、加工位置の微調整を行ったりといった作業が可能です。CNC加工中にトラブルが起きた際に、緊急停止(エマージェンシーストップ)が効くかどうかも、送信ソフトの安定性にかかっています。
2.4. ソフトウェアの連携とフローの理解
ここまで、CAD → CAM → Gコード送信という一連の流れを紹介してきましたが、この工程は一度きりで終わるものではありません。実際のCNC加工では、試作 → 修正 → 再加工というプロセスが繰り返されることが一般的です。たとえば、削り出した部品の形状に問題があれば、CADでモデルを修正し、CAMで新しいツールパスを作り直し、再度マシンに送信して再加工するという流れになります。
こうした繰り返しの作業をスムーズに行うためには、各ソフトウェア間の連携がしやすいかどうかが大きなポイントになります。ファイル形式の互換性、操作フローの整合性、設定項目の一貫性などが整っていれば、作業の無駄やミスを大幅に減らすことができます。
特に、個人や少人数で作業を行う場合、ミスがあっても自分で原因を特定して修正しなければなりません。その際、ソフトウェアの挙動が理解しやすく、トライ&エラーを繰り返せる環境が整っていることは、非常に大きな安心材料となります。
3. CNCソフトウェアの選び方
ここからは、CNC初心者が最初に直面する大きなテーマである「CNCソフトウェアの選び方」について、具体的なポイントを順を追って解説していきます。CNCソフトは種類が多く、それぞれに特徴や強みがあるため、自分に合ったものを見極めることがとても重要です。
選ぶ際には、まずCNCマシンとの互換性をチェックし、次に予算やライセンス体系、さらに操作のしやすさや学習のしやすさを比べていきます。加えて、将来的な拡張性や、困ったときに頼れるサポートやコミュニティの有無も見逃せないポイントです。
また、どんな材料をどのくらいの頻度で加工したいのかを明確にすることも大切です。たとえば、木材を使った簡単な看板づくりが目的なのか、金属部品の精密加工をしたいのかによって、求められるソフトの機能や操作の複雑さは大きく変わります。
加えて、ソフトの対応言語や、学習用のチュートリアル・ガイドの充実度も見ておきたいところです。CNCの学習は基本的に独学になることが多いため、オンラインで情報が得やすいかどうかは、実際の使いやすさに直結します。
3.1. マシンとの互換性の確認
最初に確認すべきなのが、使っているCNCマシンとソフトウェアの互換性です。CNCマシンには、GRBLやMach3、LinuxCNC、Fanucなど、さまざまなコントローラーやファームウェアが存在します。ソフトが出力するGコードが、マシン側で正しく解釈・実行できるかをチェックすることがとても重要です。
たとえば、多くのDIY用CNCマシンにはGRBLというオープンソースのファームウェアが搭載されています。この場合、「GRBL対応」と明記されたGコード送信ソフト(例:UGSやbCNC)を選べばスムーズに接続できますが、Mach3やFanuc専用のソフトでは接続できない可能性があります。
また、CAMソフトの出力するGコード形式にも注意が必要です。特定のコントローラーに合わせた「ポストプロセッサ(出力変換機能)」がないと、せっかく作ったデータがマシンで使えないこともあります。
そのため、使用中のマシン名・コントローラーの種類を確認し、対応実績のあるソフトを選ぶことが、安全で確実な導入の第一歩となります。導入前には、メーカーサイトやユーザーコミュニティを活用して「このソフトは○○マシンで使えるか?」という事例をチェックしておくと安心です。
3.2. 予算に応じたソフトウェア選定
次に考えたいのが、CNCソフトにかけられる予算です。CNCソフトには、完全無料で使えるものから、年間ライセンス料が必要な商用ソフトまで、さまざまな価格帯の製品が存在します。どれが最適かは、利用目的や加工の頻度、求める機能の範囲によって変わります。
たとえば、趣味で簡単な加工をしたい人であれば、Carbide CreateやbCNCなどの無料ソフトで十分対応可能です。さらに、Autodesk Fusionのように、非商用利用に限って個人向け無償ライセンスを提供しているソフトもあります。これらを活用すれば、コストをかけずに本格的な加工を始められます。
一方、ビジネス用途で大量生産や精密な制御が求められる場合は、有料ソフトの導入を検討する必要があります。たとえライセンス費用がかかっても、業務効率の向上や不良品の削減によって、そのコストは十分に回収できることもあります。
3.3. 操作のしやすさと学習リソース
CNCソフトを初めて使う人にとって、操作のしやすさは非常に重要です。どれだけ高機能なソフトでも、使い方がわからなければ意味がありません。最初は、シンプルで直感的なUI(ユーザーインターフェース)を持つソフトを選ぶことで、操作に慣れるまでの時間を短縮できます。
また、独学で学ぶケースが多いため、オンラインチュートリアルや解説動画、ユーザーコミュニティの充実度も選定時の大きな判断材料になります。公式のYouTubeチャンネルを持っていたり、ユーザーフォーラムが活発なソフトであれば、わからないことがあってもすぐに情報を得ることができます。
実際に試してみないと操作感はわからないため、無料版やデモ版をダウンロードして、自分の手で試してみることが最も確実な方法です。使ってみて「これは扱いやすい」「説明がわかりやすい」と感じたソフトであれば、長く付き合っていける可能性も高くなります。
また、日本語に対応しているかどうかも大きなポイントです。英語メニューしかない場合でも、有志による日本語解説ページが存在するケースもあるため、事前に調べておくと良いでしょう。
3.4. 機能の範囲と拡張性の検討
CNC加工は、最初は簡単な2Dの彫刻やカットから始める方が多いですが、作業に慣れてくると、「もっと複雑な3D形状を削ってみたい」「他の素材にも挑戦したい」とステップアップしたくなるものです。そのときに重要になるのが、使っているソフトの機能拡張性や柔軟性です。
たとえば、Autodesk Fusionのように、設計・CAM・シミュレーション・レンダリングまでを統合的に扱えるソフトであれば、ひとつのソフトでCNC加工の幅を広げていくことができます。また、最初はシンプルなソフト(例:EstlcamやCarbide Create)で基本を学び、上達してから高機能なソフトへ切り替えるという段階的なアプローチも現実的です。
将来的に4軸・5軸といった多軸加工に対応したい場合や、さまざまな素材(アルミ、真鍮、アクリルなど)を扱いたい場合は、そのソフトが対応しているかどうかを事前に確認しておきましょう。また、プラグイン機能や外部ツールとの連携が可能かといった「拡張性」も、長期的に使い続けるうえで重要になります。
3.5. サポート体制とコミュニティの活用
CNCソフトを使っていると、思わぬエラーや動作不良に遭遇することがあります。そんなときに役立つのが、ソフトのサポート体制やユーザーコミュニティの存在です。特に初心者の場合は、自己解決できない問題に直面したとき、すぐに相談できる窓口があるかどうかで、安心感がまったく違います。
有料の商用ソフトであれば、公式の問い合わせ窓口やチャットサポート、メールサポートが用意されているケースが多く、迅速な対応が期待できます。一方、無料ソフトではサポートが限定的である代わりに、活発なフォーラムやSNS上での情報交換が頼りになります。
特に海外製ソフトの場合、日本語の公式情報が少ないこともありますが、有志が作成した使い方ガイドや動画解説などが公開されている場合もあります。困ったときに検索すれば情報が出てくるかどうかも、ソフトを選ぶ際の大きな判断材料になります。
また、ソフトの使い方だけでなく、加工ノウハウや失敗事例の共有ができる場があるかも、成長を支える大きな助けになります。身近にCNCの経験者がいない場合でも、オンラインコミュニティやフォーラムを活用すれば、全国・全世界のユーザーと情報を共有することができます。
継続的にCNCを使っていくためには、トラブルを乗り越えるための情報源が豊富にあることがとても重要です。導入前に、ソフトごとのサポート状況やコミュニティの活発さをチェックしておくことをおすすめします。
4. 初心者におすすめのCNCソフトウェア5選
ここからは、CNCをこれから始めたい初心者の方に向けて、導入しやすく使いやすい代表的なCNCソフトウェアを5つご紹介します。いずれも操作性に優れ、比較的スムーズに導入できるツールばかりです。また、インターネット上で多くのレビューや使用例が見つかるため、独学でも学びやすい環境が整っています。
今回は、設計からツールパスの生成まで対応できるAutodesk Fusion、シンプルな2D加工に強いCarbide Create、CAM専用で操作性の高いEstlcam、軽量で実績あるGコード送信ソフトのUGS、そして多機能なオープンソースであるbCNCを選定しました。
どのソフトにも特徴があり、向いている加工やユーザー層が異なります。初めてCNCに触れる方は、まず1つのソフトに集中して使い方を覚えるのがコツです。複数のツールを並行して使うと混乱しやすいため、まずは1つをじっくり習得し、必要に応じて他のツールを導入するスタイルが効率的です。
以下では、各ソフトの特長や活用シーンをわかりやすく解説していきます。自分の目的やスキルに合ったツールを見つける参考にしてください。
4.1. Autodesk Fusion:総合的なソリューション
引用:https://www.autodesk.com/jp/products/fusion-360/overview
Autodesk社が提供するAutodesk Fusionは、設計(CAD)・加工準備(CAM)・シミュレーション・レンダリング機能まで一体化したオールインワン型のソフトウェアです。ひとつの環境で完結するため、データのやり取りや形式の違いによるエラーが起きにくく、ワークフローが非常にスムーズです。
非商用や個人利用に限定される条件付きであれば、無料プランも提供されており、コストをかけずに高機能なツールを試すことができます。また、WindowsだけでなくMacにも対応しているため、使用環境を選ばず導入しやすい点も魅力です。
操作画面は多機能で最初は少し複雑に見えますが、豊富なチュートリアルや公式の解説動画が用意されているため、独学でも着実に習得していくことが可能です。特に3Dモデリングや金属加工を視野に入れている方にとって、Autodesk Fusionは将来性のある選択肢と言えるでしょう。
加工の自由度が高く、設計からシミュレーションまでを一貫して行いたい場合には、Autodesk Fusionのような統合型ソフトが非常に有効です。まずは無料ライセンスで試してみて、自分のプロジェクトとの相性を確認すると良いでしょう。
4.2. Carbide Create:直感的な2Dデザイン
引用:https://community.carbide3d.com/
Carbide Createは、Carbide 3D社が提供する2D設計とCAM機能に特化したシンプルなCNCソフトウェアです。とくに初めてCNCを使う方にとっては、操作が直感的でわかりやすく、2.5D程度の加工であればこれ一つで対応できます。
無料で使えるソフトながら、基本的な加工設定やツールパスの作成、プレビュー機能などが揃っており、木材やアクリルなどの比較的やわらかい素材を扱う加工には非常に適しています。特に看板づくりや文字彫刻、小型部品の切削などを行う場合に力を発揮します。
インターフェースもシンプルで、CADやCAMに不慣れな人でもすぐに操作に慣れることができます。一方、複雑な3D形状のモデリングには対応していないため、高度な設計をしたい場合は他のCADソフトと併用する必要があります。
導入のハードルが低く、CNC加工の第一歩を踏み出すには最適なツールのひとつです。まずは簡単な図形を使って加工にチャレンジしてみたいという方には、Carbide Createがぴったりです。
4.3. Estlcam:CAMに特化した選択肢
Estlcamは、ドイツ製のCAM機能に特化したCNCソフトウェアで、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。特に2.5D加工に強く、穴あけやポケット加工、外形カットなど、CNC加工の基本を効率よくこなすことができます。
FreeCADなどで作成した図面やモデルをEstlcamに読み込んで、工具の径や切削条件を設定し、Gコードを生成して出力するという流れが一般的です。ツールパスのシミュレーションも可能なため、加工前に動作を確認しながら作業を進めることができます。
Estlcamは試用期間付きのシェアウェア形式で提供されており、一定の機能を無料で試すことができます。有料版は比較的手頃な価格で購入でき、個人ユーザーにとって導入のハードルは高くありません。
ただし、対応OSはWindowsのみであるため、Macユーザーは別のソフトを検討する必要があります。とはいえ、軽快な動作とわかりやすい設計思想により、多くのCNC愛好家から支持を集めているソフトです。まずは基本的なCAM操作を学びたいという方に、最適な選択肢のひとつといえるでしょう。
4.4. UGS:軽量で汎用性の高いGコード送信
引用:https://winder.github.io/ugs_website/
UGS(Universal Gcode Sender)は、Gコード送信に特化した軽量かつ高い汎用性を持つソフトウェアです。特にGRBLファームウェアを使用するCNCマシンとの相性が良く、DIY用途やホビー加工に広く利用されています。
このソフトはJavaで開発されており、Windows・Mac・Linuxといった主要なOSに対応しているため、さまざまな環境で利用できるのが特長です。インターフェースはシンプルで、必要最小限のボタンと設定で、軸の移動や加工の開始・停止が直感的に操作できます。
UGSにはClassic版とPlatform版があり、前者は軽量で動作が早く、後者はより多機能で拡張性に優れています。自分の環境や目的に応じて、適したバージョンを選ぶことができます。
ただし、UGS自体には設計やCAM機能はありません。そのため、CADやCAMソフトと組み合わせて使う必要があります。たとえば、CADで作図し、EstlcamでGコードを生成し、それをUGSでマシンに送信するといった運用が一般的です。
Gコード送信ソフトとしての安定性が高く、設定も難しくないため、初めてCNCマシンを動かす人にとって安心して使えるツールです。とくにGRBLを使っている場合には、UGSの導入をぜひ検討してみてください。
4.5. bCNC:オープンソースの多機能性
引用:https://github.com/vlachoudis/bCNC/wiki
bCNCは、Pythonで開発されたオープンソースのGコード送信ソフトウェアであり、送信機能にとどまらず、簡易的なGコード編集やビジュアル表示、工具パスの確認など、多彩な機能を備えています。
一見するとインターフェースがやや素朴で、操作に慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、使いこなせるようになると非常に高機能で柔軟な運用が可能です。特にスクリプトによる自動処理や、加工中のリアルタイムなモニタリング機能は、上級者だけでなく、成長意欲のある初学者にとっても魅力的です。
bCNCは、GRBLファームウェアとの相性が良く、精密な操作や細かな加工条件の調整が求められるケースでも安定して動作します。また、英語圏を中心にユーザーコミュニティが活発で、GitHubやフォーラム上には多くの情報が蓄積されています。
ただし、日本語の情報はやや少なめであるため、英語の解説に慣れておく必要があります。とはいえ、ユーザー事例やカスタマイズ例も豊富で、自分なりの環境構築を楽しみたいという方にとっては、bCNCは非常に有力な選択肢となります。
とくに、「ツールに制限されずに、自分の加工環境を自由に組み立てたい」という方には、bCNCの柔軟性と拡張性は大きな武器になるでしょう。
5. よくある疑問とその答え
CNCソフトの導入や操作について、初心者の方がよく抱く疑問にお答えします。実際に使い始めると「これはどうすればいいの?」といった細かな悩みが次々と出てくるものです。この章では、CNCソフトに関する代表的な質問とその答えをまとめました。操作や選定で迷ったときのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 無料ソフトだけで加工はできますか?
はい、目的によっては無料ソフトだけで十分に加工できます。例えば、2D加工や簡単な彫刻、看板づくりなどであれば、Carbide CreateやbCNCのような無料ソフトで問題なく作業が可能です。さらに、Autodesk Fusionのように、個人利用や教育目的に限って無料で提供されている高機能ソフトもあります。
ただし、複雑な3D加工や商用での高精度な生産を目指す場合は、有料ソフトの導入も検討したほうがよいでしょう。無料ソフトでは機能制限やサポートの少なさがネックになることもあります。まずは無料ソフトで基本操作を覚え、必要に応じてステップアップするのが現実的な方法です。
Q2. 商用利用できるCNCソフトはありますか?
はい、商用利用が可能なCNCソフトは複数あります。代表的なものとして、Autodesk Fusion(商用プラン)、Estlcam(ライセンス購入後)、Mach3などが挙げられます。これらはライセンスを正しく取得すれば、業務用として安心して使うことができます。
一方で、無料版や非商用向けプランには「個人利用限定」や「教育目的に限る」といった制限が設けられていることが多いため、利用目的とライセンス条件を事前にしっかり確認することが重要です。
商用目的で使いたい場合は、サポート体制やアップデート頻度、ライセンスの更新条件なども含めて、トータルでの導入メリットを比較検討しましょう。
Q3. 英語のソフトでも使えますか?日本語化できますか?
多くのCNCソフトは英語で提供されていますが、英語ソフトでも十分に使用可能です。メニューや用語に多少の慣れが必要ですが、YouTubeなどの動画解説や、操作手順を紹介するブログ記事などが充実しているため、ある程度の学習は独学でも可能です。
また、一部のソフトでは日本語への切り替え機能や、日本語化パッチが用意されていることもあります。さらに、有志による日本語マニュアルや解説ページが公開されているケースもあり、それらを活用すればハードルを下げられます。
操作に慣れるまでは多少戸惑うかもしれませんが、アイコンやレイアウトを頼りに感覚的に操作できるソフトが多いため、最初は簡単な機能から試して徐々に慣れていくのがコツです。英語に苦手意識がある場合でも、ツールの導入をためらう必要はありません。
このように、初心者が気になりやすい疑問には、基本的に明確な解決策や代替手段があります。まずは自分にとっての優先事項を明確にしながら、少しずつ知識と経験を積んでいくことがCNC成功への近道です。
6. まとめ
CNC加工を始めるうえで、ソフトウェアの選定は非常に重要なステップです。設計(CAD)、ツールパス作成(CAM)、加工命令の送信(Gコード送信)といった各段階で適切なツールを選ぶことで、作業効率や加工品質が大きく変わります。
特に初心者のうちは、「どのソフトを使えばいいのか」「設定は難しいのでは?」と不安になることもあるかもしれません。しかし、今回ご紹介したように、直感的に操作できるソフトや無料で試せるツールも多く、自分の目的やスキルに合ったものを選べば、スムーズにCNCの世界に入っていくことができます。
また、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは簡単な図形からテスト加工を行い、少しずつソフトやマシンの動作に慣れていくことで、自然と理解が深まっていきます。失敗も学びの一部ととらえ、楽しみながら経験を積み重ねていくことが、長く続けるためのコツです。
CNCソフトは日々進化しており、新しい機能や便利なツールも次々と登場しています。最初の一歩を踏み出し、自分に合ったソフトを見つけることができれば、その後のものづくりの幅は大きく広がります。
この記事が、あなたにとって最初の一歩となり、CNC加工の世界へ自信をもって踏み出すきっかけになれば幸いです。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
Autodesk Fusion | 3D CAD/CAM/CAE/PCB が1つに集約されたソフトウェア | 無料体験版
https://www.autodesk.com/jp/products/fusion-360/overview
Carbide Create CAD/CAM Software for CNC Routers
https://carbide3d.com/carbidecreate/
Estlcam: 2D / 3D CAM und CNC Steuerung…
GitHub – winder/Universal-G-Code-Sender
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
GitHub – vlachoudis/bCNC
https://github.com/vlachoudis/bCNC
CNC プログラミング | CNC プログラミングとは | Autodesk