BricsCAD 基本操作ガイド|初心者が最初に覚える使い方と操作手順
1. はじめに
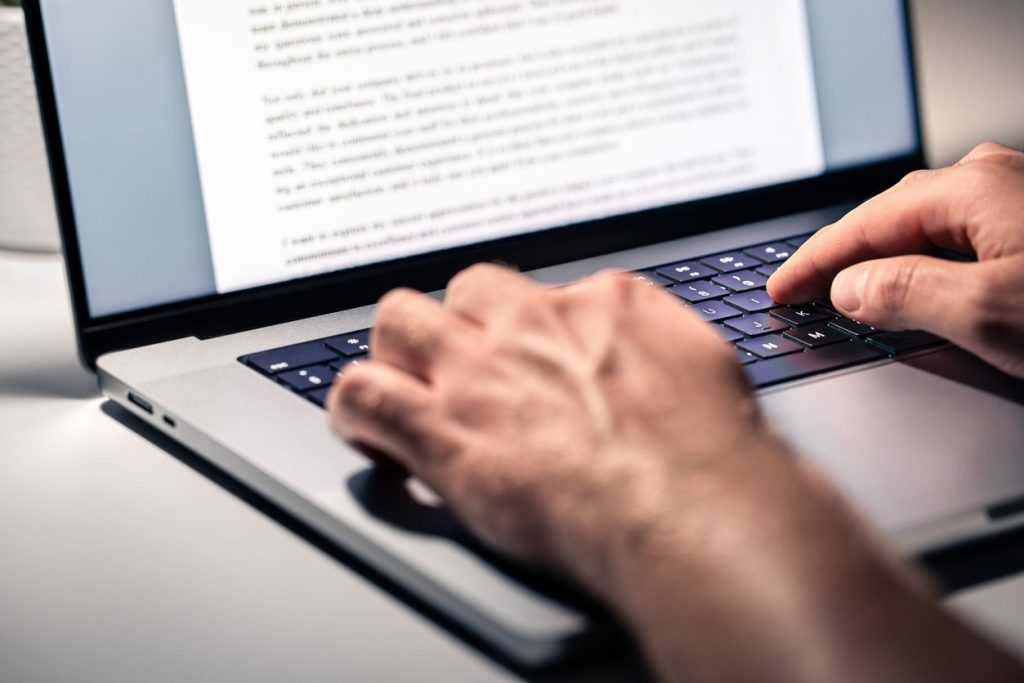
BricsCADは、AutoCADと高い互換性を持つCADソフトウェアです。特にファイル形式であるDWGを共通で扱えるため、過去にAutoCADで作成した図面データを再活用しやすいことが大きな魅力です。さらに、ライセンスコストが比較的低いことから、導入にかかる経済的負担を抑えながら十分な機能を得られる点も注目されています。
初心者が最初に覚えておくべき操作手順や画面構成を押さえることで、短期間でも実務に近い形の作図や編集を行えるようになります。AutoCAD経験者であれば、操作の類似性から比較的スムーズに乗り換えたり学習コストを低減できるでしょう。今回は、そんなBricsCADの基本操作について、中学生にも分かりやすいように平易な言葉で解説していきます。
また、CAD作業においては図形の精度やレイヤー管理が欠かせません。BricsCADでは、多様なツールバーやコマンドラインを使いこなすことで、業務の効率化を実現しやすくなります。レイアウト設定やPDF出力の手順も理解しておくと、完成度の高い図面を外部に提示しやすくなるでしょう。
この記事の目的は、BricsCAD初心者やAutoCADからの移行組に向けて、最初に押さえるべき使い方や操作手順を体系的に示すことにあります。使用できるショートカットキーやカスタマイズのコツなど、覚えるべきポイントを順序立てて紹介し、少しずつ手を動かしながら学習を進められるように構成しています。
これからご紹介する各セクションでは、BricsCADの特徴や画面構成、作図・編集の基本からレイアウトの設定、そして図面管理の方法まで、それぞれ具体的な方法と根拠を示して解説します。ぜひ、本記事を参照しながら実際にソフトを触り、BricsCADを使った図面作成の楽しさや効率の高さを実感してください。
2. BricsCADの概要と基本的な特徴
BricsCADは、AutoCAD互換のCADとして知られ、新規導入のコスト削減ができるだけでなく、これまでの操作経験を活かしながら学べる柔軟性が評価されています。特に2D製図だけでなく3Dモデリング、およびBIM(ビルディング情報モデル)的な要素への発展性も備えていることから、幅広い分野での応用が可能です。
また、BricsCADはバージョンアップによって機能面も強化されています。サブスクリプション形態も用意されていますが、買い切りライセンスを選べる点はコスト計画を立てやすい利点を生み出します。そのため、多彩な学習ニーズや企業規模に応じた導入形態を見極めやすいでしょう。
以下の小見出しでは、まずAutoCADとの比較を行い、BricsCADを利用するうえで得られるメリットを深掘りしていきます。学習コストや業務効率化など、導入前に確認しておきたいポイントをまとめてご紹介します。
2.1. BricsCADとは?AutoCADとの比較
BricsCADは、ベルギーのBricsys社によって作成されたソフトウェアで、AutoCADと同様にDWGファイルを標準形式として採用しています。そのため、AutoCADで作成した図面をBricsCADで開いて再編集することが可能です。また、操作体系も類似点が多く、リボンやツールバー、コマンドラインなどがあるため、AutoCAD経験者であれば短期間で慣れやすいのが特徴です。
一方、ソフトの動作が軽快であるという利点も挙げられます。必要スペックを比較的抑えられるため、多少古いパソコンでも動かしやすくなっています。加えて、AutoCADよりも購入費用やサブスクリプションのコストを抑えられる場合が多く、企業が導入する際には魅力の一つと言えるでしょう。
このように、ファイル互換や操作の共通点を維持したまま、費用と動作面で優位性を得やすい点がBricsCADの強みです。CAD業界での実績も着実に伸びており、近年では2D製図や3Dモデリング機能の向上と共に、BIM機能や他の関連技術との連携にも力を入れています。
2.2. BricsCADの主な利点と効率化のメリット
BricsCADの利点の一つは、カスタマイズ性が高いことです。リボン操作に慣れている人はリボンをメインに使えますし、必要に応じてツールバーやコマンドラインで作業環境を自由に組み合わせられます。ショートカットキーの設定も柔軟なので、自分の作業スタイルに合わせてキー操作を割り当て、効率的に作図や編集を行うことができます。
さらに、多機能でありながら、マシンパワーに対する要求水準が比較的低めです。これにより、大規模なプロジェクトだけでなく、ライトユーザーが頻繁に導入しやすい点も見逃せません。AutoCAD互換のコマンドを違和感なく操作できるので、業務への移行時に大きな混乱が少なく、学習コストの削減にも期待が持てます。
また、BricsCADは2D製図だけでなく、3D機能やBIM機能としても実用的な環境を提供しています。建築関係や機械設計など、多岐にわたる分野で活用されているため、一度習得しておけば仕事の幅を広げる可能性があります。結果的に、CADオペレーターやエンジニアとしてのスキルアップが見込める点も大きなメリットとなるでしょう。
3. BricsCADの画面構成と操作環境
BricsCADの画面を理解することは、効率的に操作を習得するための第一歩です。画面内のどこに主要なメニューやツールがあるのかを知ることで、迷いを減らし作業時間を短縮しやすくなります。ここではワークスペースの概念やツールバー、コマンドラインの活用法、そしてカスタマイズ方法を見ていきましょう。
ワークスペースを切り替えることで、2D製図や3Dモデリングなど用途に合わせた操作環境を用意できます。また、コマンドが多数存在するため、よく使用するものをツールバーの上部やクイックアクセスツールに配置しておくと、検索の手間が省けます。コマンドラインを常時表示にしておくことも、入力作業を効率化するコツの一つです。
各要素の基本的な役割を理解したら、自分がどの機能を多用するのかを見極め、必要に応じて配置を変更していきましょう。キーボードショートカットの設定とも連動させると、より効率的に作業できるようになります。以下の小見出しでは、画面構成のポイントを順番に解説します。
3.1. 画面の基本構成とワークスペースの理解
BricsCADを起動すると、上部にはリボンあるいはツールバーが配置され、左下または中央下部にコマンドライン、メインとなる作図エリアが中央を占めます。デフォルトでは2D製図向けのワークスペースが立ち上がることが多いですが、3Dモデリング用のワークスペースも簡単に切り替えできます。
作図エリアでは、マウスのホイール操作によるズームイン・ズームアウトや、右ドラッグによる画面移動を行いながら図面全体を把握できます。ワークスペースの切り替えは、上部のプルダウンメニューやクイックアクセス部分から行うことができ、用途に応じて見やすいレイアウトに変えられます。
なお、初心者のうちは作図エリアの背景色と用紙イメージが一致しないケースがあるため、必要に応じて背景色を白やグレーに変更しておくと印刷プレビュー時との差異をイメージしやすくなります。そうした設定変更もワークスペースの一環として覚えておくと便利です。
3.2. 主要なツールバーとコマンドラインの活用
リボン形式に慣れていれば、リボンタブに表示されたアイコンをクリックすることで主要なコマンドを実行できます。一方、ツールバー形式を好む方は必要なボタンやプルダウンメニューを表示させておき、最小限のスペースで操作できます。また、コマンドラインを利用してテキストベースでコマンドを入力する方法に親しみのある方も多いでしょう。
コマンドラインは、導入当初からベテランまで幅広く利用される操作手段です。例えば「L」と打ち込むだけで線分作成(LINEコマンド)が起動され、Enterキーを押すことで図形を描き始められます。ショートカット設定を確認しながら覚えると、操作速度が大幅に上がるでしょう。
なお、よく利用するコマンドについては、クイックアクセスツールバーやショートカットキーに登録しておくとさらに効率が高まります。保存や元に戻す(Undo)などの基本操作も同様で、ミスを防いだり作業の流れをスムーズに保ったりするうえで重要です。
3.3. カスタマイズ:作業効率を高める設定方法
BricsCADでは、キーボードショートカットやリボン/ツールバーの配置など、環境を自在にカスタマイズできます。まず、最初に実行頻度が高いコマンドを洗い出し、それらをワンクリックで呼び出せるようにツールバーに配置すると学習が進むでしょう。
また、背景色の変更やグリッド表示のON/OFFなども同じメニューから設定できます。図面が複数ある場合でも統一感を保ちたい場合、テンプレートを作成しておくと効率が上がります。テンプレートにはレイヤー構成や注釈スタイルなどをあらかじめ登録できるので、プロジェクト開始時のセットアップ時間を短縮可能です。
さらに、ショートカットキーのカスタマイズは作業スピードを左右する大きな要素となります。BricsCADの初期設定はAutoCADユーザーに馴染みやすい反面、独自のショートカットを使いこなすことで他の操作との連携がスムーズになることがあります。自分好みの作業環境を追求してみるのもおすすめです。
4. 基本操作:作図と編集
BricsCADで図面を作成する際は、まず線を引く、円を描く、矩形を作るなどの基本的なコマンドを覚えましょう。これらを組み合わせることで複雑な形状も描画できるようになります。また、オブジェクトを選択・移動・複製・回転・トリムといった編集手順を身につけると、細部の修正やレイアウト調整が素早く行えるようになります。
特に正確な寸法で図面を作りたい場合は、グリッドやスナップ機能を活用してマウス操作のみでの目測による誤差を減らすのがポイントです。線と線の交点や中心点に正確にカーソルを合わせられるため、各部品の寸法や位置合わせも容易になります。以下の小見出しで詳しく説明します。
基本コマンドは一度押さえてしまえば操作全体の流れを理解しやすくなるため、焦らずゆっくり慣れましょう。また、ショートカットキーを同時に覚えておくと、作図作業が一段と速くなります。
4.1. 基本的な図形の作成方法
BricsCADでよく使われる作図コマンドとして、LINE(L)、CIRCLE(C)、RECTANGLE(REC)などが挙げられます。例えばLINEコマンドは、コマンドラインに「L」と输入しEnterキーを押下後、マウスクリックで始点を指定して終点を指定すると線分が描画されます。CIRCLEコマンドであれば半径を入力する方法や、2点・3点を指定して描く方法など、複数のパターンを使い分けられます。
また、AutoCADの経験がある方は同じ要領でショートカットを利用できるため、ほとんど混乱せずに作図を始められるでしょう。ここで重要なのは、正確な座標を入力できること、あるいは動的に寸法を設定できることです。BricsCADでは、ダイナミック入力を有効にすることで、マウス操作だけでも数値の入力欄が表示されるため、慣れれば数値指定のズレが減らせます。
図形を複数組み合わせたい場合はポリライン(PLINE)を使うことも覚えておくと便利です。複数の線分を一つのオブジェクトとして扱えるので、編集作業で一体化させたい時に役立ちます。
4.2. オブジェクトの選択と編集技術
作図後の編集操作として頻繁に用いられるのが、MOVE(M)、COPY(CO)、ROTATE(RO)、TRIM(TR)、EXTEND(EX)などです。例えば、MOVEコマンドでは基点をクリックして別の場所を指定すると、図形をそのまま移動できます。COPYコマンドでは、同じ要領で複製を作成できます。
TRIMコマンドを用いると、不要な部分を簡単に切り取って整理できます。これと逆の機能であるEXTENDでは、図形を指定した線にまで伸ばせるため、端点合わせや交点合わせを容易に行えます。オブジェクト同士を寸分の誤差なく編集したい場合は、常にスナップを有効にし、正確性を保ちましょう。
また、選択方法には対象を1つずつクリックする単一選択と、窓選択や交差選択など複数を一括して捕捉する方法があります。編集作業に合わせて効率的な選択を使い分けると、広い図面での修正もスピーディーに完了します。
4.3. グリッドとスナップ機能を使った精密作業
図面を正確に仕上げるには、グリッド(画面上に表示される格子)とスナップ(カーソルを自動的に頂点や端点などに吸着させる機能)を活用するのが基本です。スナップが有効な状態だと、マウスを近づけるだけで交点や中心点などにカーソルが吸い付くため、寸法の誤差を極力減らせます。
グリッドは視覚的なガイドとして役立ちますが、実際のプリントアウト時には表示されないので安心してください。必要に応じてON/OFFを切り替えられるため、慣れないうちは常時表示しておくと良いでしょう。例えば、建築図で一定間隔の柱を配置するときなど、グリッドを目安に寸法確認を行うと効率的です。
なお、スナップやグリッドの設定は画面下部のステータスバーから簡単にON/OFFできます。状況に応じて機能を切り替え、無駄のない作図・編集を行いましょう。
5. レイヤー管理とプロパティ操作
レイヤー管理は、CAD図面を整理するうえで大変重要な要素です。特定のレイヤーを非表示にしたりロックしたりできるため、大きな図面でも部分的に作業エリアを限定して集中できるメリットがあります。プロパティ操作も同様に、線色や線種を切り替えることで図面全体を見やすく整理し、誤読や見落としを防ぐ役割を果たします。
一般的には、建築図・設備図・注釈・寸法などのように分野や用途別にレイヤーを振り分け、他者が図面を見た時にもどこで何を示しているのかが一目で分かるようにするのが理想です。BricsCADではAutoCADと同様、レイヤープロパティマネージャを使ってまとめて編集できますので、ぜひ活用しましょう。
以下の小見出しでは、レイヤーを実際に設定する際のポイントと、プロパティを活かした図面整理の効率化術を解説します。
5.1. レイヤーの設定と管理
BricsCADでレイヤーを管理するには、レイヤープロパティマネージャを呼び出し、新規レイヤーを追加して名前や線色、線種を指定します。一般的な運用としては、例えば“Walls”“Doors”“Dimensions”“Text”など、用途に応じてレイヤーを分けることで図面をレビューしやすくします。
特定のレイヤーだけ表示・非表示にしたいときは、レイヤープロパティマネージャ内の電球アイコンを切り替えます。図面が複雑になるほどレイヤー数が増えますが、Namingルール(命名規則)を統一しておけば混乱を避けやすくなるでしょう。加えて、「LAYISO」コマンドを使うと、選択したレイヤー以外を一時的に隠すことができるため、必要な箇所に集中して作業できます。
また、チームで図面を共有する場合は、レイヤー名を決める際に社内基準などを作成しておくと、誰が見ても同じルールで図面を扱えるため作業効率を高められます。
5.2. プロパティの変更と効果的な図面整理
プロパティ操作の代表例としては、線色、線種、線の太さなどがあります。これらは図面上での視認性や印刷時の仕上がりに直結します。例えば、重要な部位には太めの線を割り当て、補助線やガイドラインは薄い色・細い線を使うといった工夫で、複雑な図面でも見やすく整理できます。
BricsCADでは、オブジェクトプロパティパネルから対象オブジェクトの各種設定をまとめて変更できます。大量のオブジェクトを一括で変更したい場合は、前もってレイヤーを細分化しておけば、レイヤー単位のプロパティ変更で済むので効率的です。
また、図面作成時点でプロパティを適切に振り分けておくと、後からの修正が少なくなります。習慣として、図形を作りながら、その図形が属するレイヤーと、適切な線種や線色が割り当てられているかを都度確認すると、完成図の品質が高まります。
6. 図面注釈とレイアウトの基本
図面上に寸法や注釈を正しく入れることで、受け取り手に情報を正確に伝えることが可能になります。加えて、最終的な成果物として紙に印刷する場合やPDFで共有する場合には、レイアウト設定が大切です。BricsCADではペーパー空間とモデル空間を使い分け、きれいに寸法が表示されるように設定します。
寸法スタイルの管理や注釈スケールの調整を行うことによって、異なる縮尺で図面を表示しても注釈が読みやすい状態を保てます。さらに、印刷設定では紙のサイズや印刷領域を指定し、最終的にPDFに保存する方法を覚えておくと、外部に提出したりレビュー用のファイルを作る際に手際よく進められます。
以下の小見出しで、寸法記入や注釈の挿入方法、ペーパー空間を利用したビューポートの設定、印刷手順まで、実践的な操作を解説します。
6.1. 寸法記入と注釈の挿入
寸法を正しく記入するためには、まず「DIM」などの寸法コマンドを使いこなす必要があります。水平・垂直の寸法はもちろん、直径や半径、角度の寸法もそれぞれ専用のアイコンやコマンドが用意されています。寸法スタイルの設定で文字の大きさや矢印の形状を変えることも可能です。
注釈としては文字ツールを使って部品名や注釈を入れます。図形の大きさに合わせて文字のサイズを調整し、日本語入力の場合、フォント選びも見栄えに関わります。重要な箇所には太字や赤字を使うなど、必要に応じて装飾を行うと良いでしょう。
なお、複数の寸法や注釈をまとめて一括設定したい場合は、寸法スタイルを複製して条件を変更する方法がおすすめです。そうすることで、図面全体の体裁を統一することが容易になります。
6.2. ペーパー空間とビューポートの設定
CADソフトでは一般的に、モデル空間で実寸の作図を行い、印刷したいレイアウトはペーパー空間で調整します。BricsCADでも同様で、ペーパー空間にはビューポートという枠を配置し、その枠を通じてモデル空間の図形を覗かせる仕組みです。
ビューポートは、好きなサイズや形状にカットしてレイアウトを組むことができます。複数のビューポートを作成し、それぞれ異なる縮尺を設定すれば、拡大図や全体図などを同じ用紙にまとめることも容易です。例えば、あるビューポートでは1/50、別のビューポートでは1/10といったように、場面に応じた表示を切り替えます。
この設定を正確に行うことで、印刷時の寸法スケールも整合性が保たれます。初心者には最初少し戸惑う点ですが、一度習得すれば様々な図面レイアウトを自在にコントロールできるようになるでしょう。
6.3. 印刷設定とPDF出力の手順
図面が完成したら、最終的に外部提出用として紙に印刷したりPDFに出力する工程に進みます。BricsCADでは、印刷コマンドからプリンタや用紙サイズ、印刷領域を指定し、必要に応じて横向き・縦向きを切り替えます。
PDFに出力する場合は、仮想プリンタを選択して設定をすることで、紙に印刷する手順と同じ要領で簡単にファイルへ変換可能です。印刷線の太さや色の出方については、ペン設定ファイル(CTBやSTBと呼ばれることもあります)を管理し、太線・細線を分けて指定すると仕上がりがきれいになります。
提出先がデジタルデータのみを求めている場合や、大判サイズの紙にこだわらなくても良いケースではPDF化が特に便利です。こうした印刷設定や出力手順をあらかじめ把握しておくことで、納期の迫る場面でもスムーズに資料をまとめられます。
7. 図面管理の基本

設計作業には図面管理が不可欠です。建築や機械設計などの大規模プロジェクトになると、どのバージョンの図面が最新かを把握することが難しくなりがちです。そこで、ファイルの保存形式やテンプレートの利用、そしてバージョン管理の仕組みを事前に理解しておくことで、混乱やミスを防ぎながら作業効率を底上げできます。
BricsCADではAutoCADのDWG形式と基本的に互換性があるため、DXFなど別の形式への変換が必要な場合を除けば、DWGを標準保存形式として扱うことが多いでしょう。また、テンプレート管理では明確な命名規則を持つことが大切です。以下の小見出しで詳細を説明します。
正確な保存と管理ができれば、万が一データが破損した際もバックアップファイルや自動保存されたデータから復元できる可能性が高まります。プロジェクトを円滑に進めるためには欠かせない工程です。
7.1. ファイル形式と保存オプション
BricsCADのデフォルトの保存形式はDWGで、これはAutoCADと同じです。従って、過去にAutoCADで作成されたデータを開く場合でも原則として問題なく扱うことができます。ただし、バージョンが大きく異なると互換性に注意が必要になることが稀にあります。
さらに、DXF形式(Drawing eXchange Format)は異なるCADソフト間でのデータ交換を行う際によく使われます。DWGをDXFに変換したり、その逆も可能です。DWT(テンプレートファイル)を活用すると、レイヤーや注釈スタイルの初期設定をあらかじめ保存しておけるため、新規図面作成のたびに同じ設定を繰り返す手間を省けます。
保存オプションとしては自動保存の時間間隔を設定しておくと安心です。万が一ソフトが強制終了しても、バックアップファイル(.bakや.sv$など)からある程度のデータを復元できるため、大幅な作業のやり直しを防ぎやすくなります。
7.2. テンプレートの活用とバージョン管理
テンプレートはレイヤー構成や図面尺度、寸法スタイルなど、頻繁に使う設定をあらかじめ用意しておくためのファイルです。BricsCADでもDWT拡張子のファイルをテンプレートとして利用できます。建築用、機械用など、用途別に複数テンプレートを作っておくことで、プロジェクト開始の準備時間を節約できるでしょう。
バージョン管理では、図面を更新するたびにファイル名に日付を入れる方法や、クラウド上のバージョン管理サービスを利用する方法などがあります。チーム全体で作業する場合、誰がいつどの部分を変更したのかを明確にしておくことは極めて重要です。誤って古いバージョンを使って作業を続けると、大きな手戻りが発生する可能性があります。
こうした管理体制をしっかり構築することで、設計プロセスを円滑に進められます。AutoCADからBricsCADへ移行する際も、すでに存在するテンプレートやバージョン管理ルールを踏襲すればスムーズに切り替えられるでしょう。
8. AutoCAD経験者向けの移行ポイント
AutoCADに慣れ親しんだユーザーにとって、BricsCADへの移行時に気になるのは、具体的にどの操作が同じで、どの部分が異なるのかという点です。幸い、ショートカットキーのほとんどは同じように使える場合が多いですが、一部異なるものもあるため注意が必要です。また、独自の機能である「Quad Cursor」は使いこなせると大きな効率アップが期待できるでしょう。
通常のコマンドの動作やリボン・ツールバーのレイアウトも、AutoCAD経験者が初期設定のままでも比較的スムーズに操作できる設計になっています。以下の小見出しでは、共通点と相違点、具体的なショートカット比較などに触れながら、移行におけるポイントを解説します。
移行前にあらかじめ意識しておくことで、作業中のストレスを減らし、短期間で成果物を出せるようになるでしょう。費用面でも安心できる要素が多いBricsCADですが、操作習熟の早さは競争力にも直結しますので、ぜひ押さえてください。
8.1. 操作の共通点と相違点
BricsCADはコマンド体系やファイル形式がAutoCADと非常に近いため、LINE(L)やCIRCLE(C)、COPY(CO)など、ほとんどのショートカットが同様に使えます。また、レイヤー管理やプロパティ操作の仕組みもほぼ変わらないので、図面制作から編集までの基本操作はスムーズに身につくでしょう。
相違点としては、一部のショートカットや独自機能が挙げられます。例えば、「Quad Cursor」は右クリックやオブジェクト選択時に瞬時に関連コマンドを呼び出せる便利な機能で、最初は戸惑うかもしれませんが使いこなすと作業が加速するでしょう。また、Ctrl+Shift+Cで基点コピーが実行できるなど、細かな部分で操作性が異なる点もあります。
ただし、こうした相違点は慣れてしまえばむしろ作業効率を高める要素になり得ます。初期段階でのショートカット確認やツールチップの参照を意識しておけば、そこまで難しく感じることはないはずです。
8.2. ショートカットキーとコマンドの比較
BricsCADとAutoCADのショートカットキーを並べて比較する表を作成しておくと、移行作業が格段に楽になります。多くのコマンドは同じ記号やアルファベットで呼び出せますが、BricsCAD独自のショートカットは早めに把握しておきましょう。
例えば、AutoCADでは“CTRL+SHIFT+V”が特定の機能を実行するのに対して、BricsCADでは同じショートカットが別の動作をする可能性があります。そのため、移行前にぜひ「キーボードショートカット」一覧を印刷したり、画面の片隅にメモを貼って参照しながら作業すると覚えやすいでしょう。
また、LISPなどのカスタムスクリプトを利用している場合も、互換性が高いと言われています。ご自身がAutoCADで使用していたルーチンがそのまま使えるケースも多いので、継続的な業務効率化に役立つことが期待できます。
9. 学習を効率化するコツ
BricsCADを習得するには、最初の基本コマンドや操作概念を理解するのが第一歩ですが、効率を高めるための学習リソースも非常に重要です。公式サイトやYouTubeチャンネル、ユーザーフォーラムには数多くのチュートリアルが公開されており、無料リソースを活用すれば独習で十分なスキルを身につけることが可能です。
また、AutoCADとの類似性を活かしつつ、BricsCAD独自の機能にも少しずつ触れていけば、新しい操作方法やショートカットに対する躊躇が消えていきます。以下の小見出しでは、コマンドやショートカットを素早く覚える方法、さらに活用できる学習サイトや動画コンテンツなどを紹介します。
計画的に学習すれば、短期間でも仕事の実践レベルに達することは十分可能です。そこで必要なのは、問題が出た際にどのリソースを参照すればよいか、またどの順番で機能を習得すれば効率的か、事前に見通しを立てることです。
9.1. 基本コマンドとショートカットの習得
最初のうちは、日常的によく使うコマンドを集中して練習すると習得が早まります。LINEやCIRCLE、MOVE、COPY、TRIM、EXTENDなど、図面を作成するうえで欠かせない機能を丁寧にマスターし、それと同時に対応するショートカットキーを身体で覚えるイメージで進めましょう。
仮に10個前後のコマンドを覚えただけでも、シンプルな図面ならひと通り作成が可能です。その後、必要に応じてDIM(寸法)やLAYISO(レイヤー表示分離)、属性を持ったブロックなど、より実践的な機能へと学びの幅を広げていけば、業務にも即対応しやすくなります。
また、学習の段階でUnixなど他のOS環境利用者向けの情報も目にするかもしれませんが、Windows版が多く使用されるため、まずはWindowsの操作に馴染むほうが理解を深めやすいでしょう。
9.2. 効果的な学習リソースの利用方法
BricsCADの公式サイトにはチュートリアル動画やドキュメントが充実しており、操作方法を映像で学べるのが大きな利点です。また、ユーザーフォーラムは疑問に思った点を質問したり、すでに解決済みのトピックから知識を得たりできる貴重なコミュニティとして機能しています。
初心者に特におすすめなのが、YouTubeなどの無料リソースです。初歩的な操作から高度な3D機能、さらにはBIM機能まで解説しているチャンネルも多く、必要なテーマだけに絞って短時間で習得できます。公式やユーザーが作成した解説動画を繰り返し見ながら、手を動かして学びましょう。
書籍やオンライン講座を併用すると、体系的に頭の中を整理することができ、疑問点も明確になります。実践的な演習問題を通じて理解したことが定着しやすいので、習得スピードをさらに高めたい方は参考にすると良いでしょう。
10. まとめと次のステップ
本記事では、BricsCADの基本操作方法や画面構成、レイヤー管理、注釈やレイアウト、そしてAutoCAD経験者向けの移行ポイントまでを総合的に解説してきました。BricsCADは、AutoCAD互換でありながらも低コストで導入できる選択肢として注目を集めています。学習コストを抑えつつ、業務効率化に繋がる理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。
初めて触れるユーザーにとっては、リボンやツールバー、コマンドライン操作など、最低限の使い方を習得するだけで2D製図や編集業務をこなせるようになります。AutoCAD経験者なら共通点をさらに活用し、短期間での移行を狙うことができるでしょう。併せて、独自機能やショートカットを使いこなせると、操作効率は一段とアップします。
次のステップとしては、3DモデリングやBIM機能など、BricsCADが提供する追加機能へのチャレンジを検討してみてください。これらの機能を習得すれば、平面図だけでなく立体的な構造や建築設計などの高度な場面でも活用が可能になります。ぜひ、さらなるスキルアップを目指して、本記事や公式サイト、学習リソースを活用しながら着実にステップを踏んでいきましょう。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
・CADソフトウェア – 2D/3D CAD – Bricsys®












