Vectorworks 2020で学ぶ基本の使い方|旧バージョンとの違いも解説
1. はじめに
Vectorworksは、建築・インテリア・ランドスケープ・ステージなど幅広い分野で使えるBIM対応のCADです。1つの環境で2D作図と3Dモデリング、そしてレンダリングまで一貫して行えるのが大きな魅力。2020ではUIの見直しや操作性の改善、表示パフォーマンスの向上が進み、必要な機能にすばやくアクセスしやすくなりました。
本記事は、これからVectorworks 2020を使い始める初心者の方、旧バージョンからアップグレードを検討している方 に向けて、基礎から実務で役立つポイントまでをやさしく整理します。
まずはVectorworksの全体像(何ができるのか/どんな場面で強いのか)をつかみ、そのうえで基本操作、旧バージョンとの違い、スムーズに導入するコツ、よくあるトラブルの対処を順に解説します。建築はもちろん、イベントや舞台など“空間”を扱うプロジェクト全般に応用できる内容です。
「最短距離で手を動かせるようになること」をゴールに、実務で迷いがちなポイントも具体的にフォローします。初めての方でも、読み終えるころには自分のプロジェクトで使い始められるはずです。
2. Vectorworks 2020の概要
Vectorworksは、建築設計やインテリアデザイン、ランドスケープ設計など、幅広い分野で利用されているBIM対応のCADソフトウェアです。2020年版では特にユーザーインターフェースの改善と処理速度の向上が重視され、初心者でもスムーズに操作でき、プロフェッショナルにとっても効率的に活用できる環境が整備されました。
旧バージョンに慣れているユーザーにとっては、レンダリング機能やナビゲーションパレットの操作感が変わった点に戸惑うかもしれません。しかし、新機能を取り入れることで、プロジェクト全体のワークフローはこれまで以上に滑らかになります。特に、BIM機能の強化によってデータマネージャが拡張され、IFCデータのマッピング制御がより柔軟になったことは大きな進歩です。必要なプロパティやMVDを設計意図どおりに管理できるため、建築業界におけるOpenBIM連携の実務性がさらに高まりました。
この章では、Vectorworks 2020の代表的な特徴と全体像を把握することを目的に、ソフトの基本的な役割やシステム要件、サポート体制などを紹介します。数値データや推奨環境を確認しながら、自社のパソコンやプロジェクト規模に適した導入方法を見極める参考にしてください。
さらに、分野ごとに最適化されたツールセットが同梱されている点も重要なポイントです。たとえば、ランドスケープデザイン向けの機能やインテリア用のリソースが標準で用意されているため、建築に限らず幅広い領域で活用できる柔軟性がVectorworksの大きな強みといえます。
2.1. Vectorworksとは?
Vectorworksは、2D作図と3Dモデリングを同じ環境で扱える統合型CADソフトウェアです。建築だけでなく、インテリアや舞台、展示会など、さまざまな設計プロセスに対応できるBIMソフトウェアとしての拡張性を備えています。
具体的には、図形の作成、寸法設定、リアルなレンダリング、プロジェクト全体を整理しやすいレイヤー・クラス管理など、設計に必要な作業を1つのプラットフォームで完結させることが可能です。こうした統合性により、新しく導入する設計事務所でも比較的スムーズに運用を開始できます。
また、世界中にユーザーコミュニティが存在し、日本語での情報も以前に比べて増えてきました。インテリア分野では、家具レイアウトや照明計画を立体的に確認できる機能が浸透しており、空間の検討をわかりやすく支援します。加えて、2020年版ではBIM機能がさらに強化され、建築モデルの多角的な分析や情報管理でも高い効果を発揮します。
このように、Vectorworksは建築設計だけでなく、ステージデザインや展示会ブースの空間演出など、分野を横断して活用できる点が大きな特徴です。
2.2. 2020年版の新機能と改善点
Vectorworks 2020では、従来から高く評価されてきたデザインツールがさらに充実しました。最も大きな改良はグラフィック性能の向上で、2Dや3Dビューの切り替えがこれまで以上にスムーズになり、大規模なCADデータを扱ってもストレスを感じにくくなっています。
また、UI(ユーザーインターフェース)の改善として「ウィジェットグループ」や「リスト表示の直接編集」が追加され、必要な機能に直感的にアクセスできるようになりました。パレットのドッキング自体は従来から可能でしたが、2020ではナビゲーションパレットやリソースマネージャの応答性が改善され、作業効率を大幅に向上させています。
BIM機能に関しては、データマネージャによるIFCマッピング制御が強化され、他ソフトウェアや関係者とのデータ連携がよりスムーズに行えるようになりました。設計データの流用性が高まったことで、OpenBIMによるコラボレーションの実務性が一層増しています。さらに、レンダリングや表示の面ではVectorworks Cloud Servicesを利用でき、重い処理をクラウドに任せることでローカル作業を中断せずに進められます。加えて、VGM(Vectorworks Graphics Module)の改善や断面表示・ビューポートの強化により、結果確認や試行の回数を増やしやすくなりました。
こうした改良を実感するには、実際にプロジェクトを操作しながら体験するのが最適ですが、導入のハードルを下げるために公式チュートリアルやサンプルファイルも充実しています。後のセクションで効率的な学習方法を詳しく紹介しますので、併せて確認してください。
さらに、ライブ・データ・ビジュアライゼーション機能により、ゾーニングや工程別の属性情報を色分け表示するなど、図面やビューポートでの“見える化”が進化しました。
2.3. システム要件とサポート
Vectorworks 2020はWindowsとMacの両方に対応していますが、快適に利用するには十分なハードウェア環境が必要です。推奨環境はプロジェクトの規模によって変わりますが、大規模ファイルや複雑なレンダリングを扱う場合には16GB以上のRAMが望ましく、VRAMは使用する解像度に応じて2GB〜4GB以上を目安とすると安心です。SSDを導入すればファイルの読み込みや書き出し速度が大幅に向上します。
OSは、Vectorworks 2020の公式対応範囲に従ってください。例として、Windows 10(64bit)やmacOS 10.13〜10.15が挙げられます。「常に最新OSを使う」のではなく、必ず公式の対応表に基づいて運用することが安定動作の前提です。なお、一部の旧OS(例:Windows 8.1、macOS 10.11–10.12)が記載されているケースもありますが、導入前には最新の動作環境ページを確認することを強くおすすめします。
サポート面では、公式ウェブサイトやユーザーコミュニティフォーラムが充実しています。初心者向けのチュートリアル動画やFAQも整備されているため、疑問点を解決しながら学習を進められます。さらに、コミュニティでは建築やインテリアなど分野別の実務的ノウハウを共有できる点もメリットです。
ライセンス形態も複数用意されており、教育機関向けのアカデミックプランから業務用のサブスクリプションまで幅広く選択できます。自社の利用目的や予算に応じてプランを選べば、長期的に高いコストパフォーマンスを得られるでしょう。
3. 基本操作の解説
ここでは、Vectorworks 2020を使い始める際に知っておきたい基本操作を紹介します。最初はインターフェースの配置やファイル管理に戸惑うかもしれませんが、仕組みを理解しておけばスムーズに作業を始められるようになります。
まず大切なのは、メニューバーやナビゲーションパレットといった基本要素の役割を把握することです。どのツールがどこから呼び出せるかを理解しておくと、作図や3Dモデリングを行う際に迷わず操作できます。初心者向けガイドやオンラインチュートリアルには図解入りで説明された資料も多いため、それらを並行して学ぶと理解が深まります。
また、効率的なファイル管理やビュー操作はプロジェクト全体の生産性に直結します。レイヤーとクラスを上手に使い分けることで、大規模プロジェクトでも混乱を避けられ、2Dと3Dの切り替えもスムーズに行えます。以下では、具体的な操作方法と注意点を見ていきましょう。
ここで紹介する手順は実際の業務フローに沿っているため、そのまま実務に活かせます。あわせて、2D作図から3Dモデリング、データ管理までを一貫して理解できるため、実際のプロジェクトで役立つ知識として定着させやすい内容です。
3.1. インターフェースの紹介
Vectorworks 2020を起動すると、画面上部にメニューバー、左右にツールパレット、下部にステータスバーといった構成が基本です。さらにナビゲーションパレットやオブジェクト情報パレットを表示させれば、画面の端に並ぶパネルから各機能へ素早くアクセスできるようになっています。
メニューバーには作図や編集に関するコマンドが集約されており、初心者が最初に操作を覚えるのに最適です。慣れてきたらカスタマイズ機能を使ってショートカットキーを設定すると、作業効率をさらに高められます。
ツールパレットには図形作成や変形のツールがまとめられており、2D・3Dの両方で頻繁に使う機能が揃っています。たとえば「長方形」「円」「ポリゴン」といった基本図形のほか、Push/Pullやソリッド操作などモデリング用のボタンもあり、直感的に立体操作が可能です。
また、インターフェースのレイアウトは作業者の好みに合わせて調整できます。作図スペースの広さや視認性を考えながら、パレットをドッキングさせたり位置を変えたりして、自分に合った環境を整えてみましょう。
3.2. ファイル管理とビュー操作
Vectorworks 2020では、プロジェクトごとにひとつのVectorworksファイルを作成し、その中に複数のレイヤーやクラスを設定するのが基本です。レイヤーは大きな構造単位の分け方、クラスはオブジェクトの属性管理を担うため、建築やインテリアといった様々な設計分野で混乱を防ぐのに役立ちます。
ビュー操作も重要な基本スキルです。2Dと3Dを切り替えながら作業する際には、ズーム・パン・3D回転といった操作を使い分けて、対象を常に見やすい角度に保つことが大切です。特にBIMとして活用する場合、立体モデルを確認しながら寸法や配置を修正する場面が多く、ビュー操作のスムーズさが作業スピードを大きく左右します。
データが大きくなりがちなプロジェクトでは、外部参照を活用したり、オブジェクトをシンボル化して再利用したりすると効率的です。Vectorworks 2020にはリソースマネージャが搭載されており、シンボルやマテリアルを一元管理できるため、整理しながら作業を進められます。
ただし、大規模なデータを扱うと処理が重くなることもあります。そのため、保存はこまめに行い、自動バックアップも設定しておくと安心です。これにより、予期せぬトラブル時のリスクを大幅に軽減できます。
3.3. 2D作図と3Dモデリングの基本
2D作図では、まず線や長方形、円といった基本図形をツールパレットから選んで描いていきます。スナップ設定を調整して寸法を正確に指定すれば、その後の編集がスムーズになります。Vectorworks 2020では、表示エンジン(VGM)の改良や詳細度設定の強化によって、ビュー切り替えやナビゲーションがより快適になり、スナップ操作の安定性も増しました。
3Dモデリングでは、押し出しや回転体などのコマンドを使い、2D図形を立体化していきます。建築設計であれば壁や床を、インテリアなら家具や照明器具を作成でき、ステージデザインでは舞台セットや照明リグの配置を立体的に確認できます。
モデリングが終わったら、テクスチャやマテリアルを設定して仕上がりを表現します。Vectorworks 2020のレンダリング機能は光源設定や質感表現が強化されており、単なる形状確認を超えてリアルなシミュレーションが可能です。
こうした操作を身につけるには、小さなプロジェクトから始めるのがおすすめです。公式チュートリアルや初心者ガイドでは、手順ごとに操作を確認できる教材が用意されているため、繰り返し練習しながら理解を深めていきましょう。
4. 旧バージョンとの違い
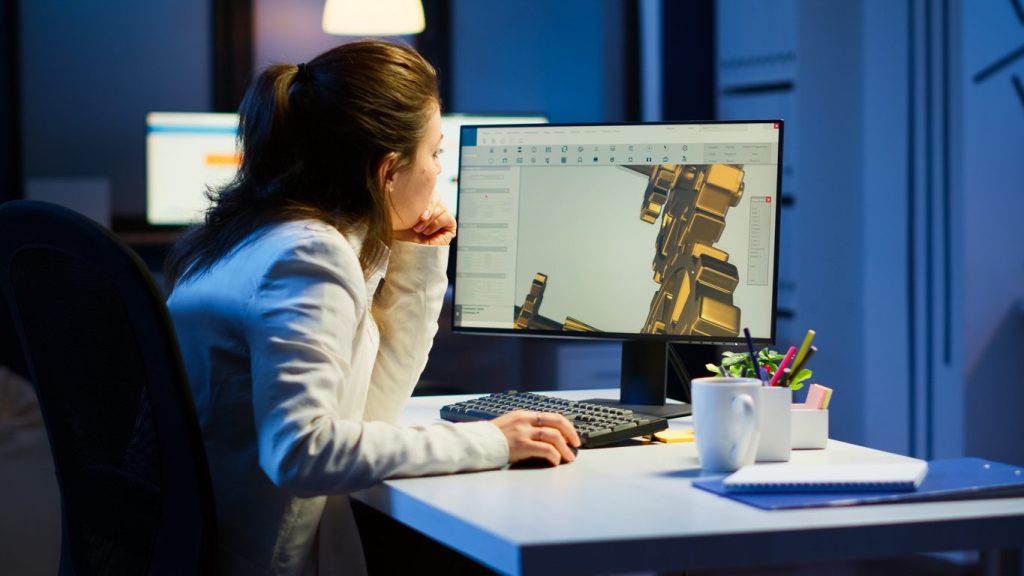
Vectorworksを2019以前のバージョンから使ってきたユーザーにとって、2020年版の変化点は大きな関心事でしょう。特にインターフェースや機能の進化は、作図効率やデータの扱い方に直結するため、あらかじめ注意点を把握しておくことが大切です。
ここでは、UI刷新による操作性の変化、従来機能がどのように改良されたか、そしてファイル互換性がどの程度確保されているかを順に整理します。移行の際には、ショートカットキーや細かな設定の違いが戸惑いの原因になりやすいため、ポイントを押さえておけばスムーズに乗り換えられるはずです。
また、プロジェクトの進行中にバージョンアップすることも珍しくありません。旧バージョンで作成したファイルを2020で開くときは、互換性を保ちながら新機能が適切に反映されるかどうかを確認しておきましょう。本セクションではそのあたりのトラブル対策についても触れていきます。
特に、測定単位や図形属性の仕様変更など、気づかないうちに影響が出る部分もあります。アップグレード前後でどこに注目すべきかを理解しておくことで、安心して移行を進められるでしょう。
4.1. インターフェースの変更点
Vectorworks 2020に移行してまず実感するのは、UIの改善による見やすさと操作性の向上です。ウィジェットグループやリスト表示の直接編集が追加され、アイコンやレイアウトが整理されて視認性が高まりました。旧バージョンではツールやパレットが雑然と感じられることもありましたが、2020年版では用途ごとにきれいに分類され、作図や編集の流れを自然に把握しやすくなっています。
さらに、ナビゲーションパレットやリソースマネージャの操作性も見直され、レイヤやクラスの管理をより迅速に行えるようになりました。パレットのドッキング位置を自由に変更できるため、画面を広く使いつつ必要な機能に素早くアクセスできます。建築設計やインテリアデザインのように要素が多い作業でも、作業画面を整理しやすいのが利点です。
加えて、配色やアイコンサイズのバランスも最適化され、全体としてより洗練された印象になりました。初心者でもコマンドを探しやすく、ショートカットキーのカスタマイズを組み合わせれば、作業スピードを大幅に高めることができます。
このように、2020年版のUI刷新は操作性を底上げし、作図効率を向上させます。旧バージョンに慣れている人は最初戸惑う部分もあるかもしれませんが、全体的には直感的で実務に即したワークフローが実現されています。
4.2. 機能の進化と操作方法の変更
機能面でも、旧バージョンから2020年版への移行で大きな進化が見られます。レンダリング機能が改良され、3Dモデリングの操作性も向上しました。以前は複数ビューを併用すると動作が重くなることがありましたが、2020年版ではVGMの改善やビューポート・断面表示の最適化によって、表示応答や操作感が安定しています。
2D作図の操作性も進化しています。線分や図形のトリミング処理がよりスムーズに行えるようになり、細かな編集作業の効率が高まりました。また、一部のコマンド名称や配置が変更されているため、アップグレード後はツールやメニューの位置を確認しておくと安心です。
BIM関連機能では、IFCエクスポートの手順が簡略化され、複雑な建築モデルでも情報を保持したまま他のソフトと連携しやすくなっています。これにより、異なるCADソフトを使うパートナーとも効率的にデータを共有でき、コラボレーションのスピードが上がります。
操作方法の変更点に戸惑いがちな場合は、旧バージョンと2020年版の主な差異を一覧にまとめておくと便利です。特に使用頻度の高いコマンドは、移行直後に確認しておけば作業の中断を防ぎやすいでしょう。
4.3. ファイル互換性と移行のポイント
旧バージョンで作成したファイルをVectorworks 2020で開くと、自動的に変換が実行され、新しい形式にアップグレードされた上で編集が可能になります。ただし、旧バージョン特有のプラグインオブジェクトやレンダリング設定が完全に引き継がれないケースもあるため、重要なプロジェクトではバックアップをとっておくことを強くおすすめします。
また、2020の新機能を最大限に活かすには、レイヤ設定やクラス構造の見直しも効果的です。BIMソフトとしての情報管理能力が向上しているため、プロジェクト全体を一貫管理しやすくなっています。移行のタイミングでフォルダやリソースマネージャのライブラリを整理しておくと、以降の作業効率アップにつながります。
さらに、ショートカットキーやワークスペースの設定は旧バージョンからインポート可能ですが、アイコンの変更やツール配置の違いにより一部が正しく反映されない場合があります。その際は、設定を再確認し、不足分を手動で補うことで快適に作業環境を整えられます。
これらの点を意識して準備すれば、旧バージョンからVectorworks 2020への移行は難しくありません。細かな変更点に注意しつつアップグレードを進めることで、より快適で効率的な作業環境を手に入れることができるでしょう。
5. 実践的な活用例とトラブルシューティング
ここでは、Vectorworks 2020を実際のプロジェクトに導入する際の進め方と、よくある不具合の対処法を解説します。ソフトをインストールしただけでは十分ではなく、日常の業務フローに組み込んでスムーズに運用できるようにすることが重要です。
Vectorworksは建築設計ソフトとして広く利用されていますが、インテリアデザインやランドスケープデザインにも同じように応用可能です。基本操作の多くは共通しているため、ツールセットの違いさえ理解すれば分野をまたいで活用できます。さらに、ステージデザインの現場では、照明やセットのレイアウトを3Dで直感的に検証できる点が強みとなり、空間演出の検討を効率的に進められます。
一方で、作業中に動作が重くなったり、ファイルが開けなくなるといったトラブルに直面することもあります。その場合は、パフォーマンスの最適化や環境設定の見直しが必要です。本セクションでは、そうしたトラブルの原因と解決方法についても整理していきます。
原因はハードウェア不足やソフト設定の不備など、意外と小さなところに潜んでいるケースが多いものです。そのため、公式サポートやユーザーコミュニティを積極的に活用し、迅速に問題を解決できる体制を整えておくと安心です。
5.1. 効率的なプロジェクト進行のためのチュートリアル
初めてのプロジェクトで戸惑わないためには、Vectorworks 2020が提供する公式チュートリアルやサンプルファイルを活用するのが効果的です。たとえば建築設計のチュートリアルでは、敷地情報の登録から壁の作成、窓やドアの配置までを段階的に学べるようになっており、実務に近い流れを理解できます。
インテリアデザイン向けのチュートリアルでは、室内の家具レイアウトや照明計画を3Dシミュレーションで確認できるため、完成イメージをクライアントと共有する際に非常に役立ちます。こうして得た知識は、そのまま業務プロジェクトに応用できるのが大きな利点です。
また、ランドスケープデザインを学びたい場合は、公園計画や植栽配置を例にした練習データが用意されているケースがあります。これを使ってレイヤーやクラスの管理スキルを磨くことで、より大規模な案件でも混乱を防ぎやすくなります。
チュートリアルを進める際に大切なのは、一度に詰め込みすぎず、少しずつ学ぶことです。特にBIM機能は奥が深く、すべてを短期間で習得するのは困難です。必要な手順を実務に沿って繰り返し練習し、段階的にスキルを積み重ねることが効率的な学習につながります。
5.2. よくある問題とその解決法
Vectorworks 2020を利用していると、ときどき動作が遅くなる、あるいはソフトがフリーズするなどの不具合に遭遇することがあります。考えられる原因としては、PCのメモリ不足や古いグラフィックドライバの使用などが挙げられます。解決策としては、メモリを増設したり、グラフィックカードのドライバを最新に更新したりするなど、環境面を改善することが基本です。
また、図形が思ったようにスナップしない場合は、スナップ設定が無効になっていたり、精度設定が不適切である可能性があります。環境設定を確認し、正しいモードや精度を選び直すことで解決できる場合があります。さらに、データ量が多すぎるとスナップが遅延することもあるため、不要なオブジェクトやレイヤーを整理して軽量化するのも効果的です。
旧バージョンから移行した後に「特定のプラグインが動作しない」といった問題が発生することもあります。その場合は、プラグイン提供元がVectorworks 2020に対応しているかを確認し、必要であれば最新版を導入しましょう。移行計画を立てる際は、使用中のプラグインの対応状況を事前にチェックしておくのが安心です。
どうしても解決できない場合は、公式サポートに問い合わせたり、ユーザーコミュニティで相談するのが有効です。過去の事例や他ユーザーの経験談が豊富に蓄積されているため、似たトラブルの解決方法を見つけられるケースが多くあります。
6. まとめ
ここまで、Vectorworks 2020の概要から基本操作、旧バージョンとの違い、そして実際の活用例やトラブルシューティングまで幅広く解説してきました。2D作図・3Dモデリング・レンダリングを一つの環境で統合的に扱える強みは、建築設計やインテリアデザインにとどまらず、ランドスケープやステージデザインといった多様な分野でも大きな力を発揮します。
特に2020年版では、UI改善やパフォーマンスの強化が進み、規模の大小を問わず快適に扱える環境が整っています。旧バージョンとの互換性も維持されているため、移行の際に大きな支障はなく、新機能を取り入れながらスムーズに作業を引き継ぐことが可能です。さらに、BIMワークフローの最適化や公式チュートリアルを活用したスキルアップによって、初心者でも確実に成長できるのが魅力です。
Vectorworks 2020の導入によって得られるメリットは、単に作業スピードやエラー削減にとどまりません。クライアントへのプレゼン品質を高めたり、複数分野との連携を円滑にしたりと、業務全体の質を底上げする効果があります。とりわけ、BIM機能による情報共有の強化は、現代の設計業務において競争力を維持するための重要なポイントといえるでしょう。
今後も学習リソースやサポートを活用しながら、自分のプロジェクトに合ったワークフローを築いていくことで、業務効率と表現力をさらに高められます。定期的にアップデート情報をチェックし、最新機能を柔軟に取り入れる姿勢が、長期的に見ても大きな成果につながるはずです。
大手ゼネコンBIM活用事例と 建設業界のDXについてまとめた ホワイトペーパー配布中!
❶大手ゼネコンのBIM活用事例
❷BIMを活かすためのツール紹介
❸DXレポートについて
❹建設業界におけるDX

<参考文献>
Vectorworks Japan
https://www.vectorworks.co.jp/
Vectorworks 2020|製品別動作環境
https://www.vectorworks.co.jp/Support/sysreq/vw2020.html
テクニカルサポートデスク|Vectorworks Japan
https://www.vectorworks.co.jp/Support/
チュートリアル|Vectorworks Japan












