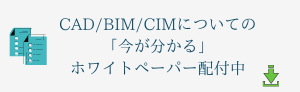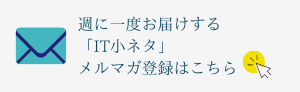基礎から学ぶSOLIDWORKSでの公差解析入門
はじめに
製品開発において、公差解析の重要性はますます高まっています。特に、製品精度向上や製造リスク低減などを重視するエンジニアリング分野では、寸法公差や形状公差、位置公差といった要素を適切に管理することが不可欠です。これらを考慮せずに設計を進めると、組み立て時や量産時に思わぬ不具合が生じ、製造コスト削減の取り組みが台無しになることさえあります。
公差解析にまつわる基本的な概念をはじめとして、SOLIDWORKS TolAnalystを活用した実践的方法や公差解析事例、さらに設計教育の面でも役立つポイントを本記事では詳しく解説します。
公差解析の基本知識
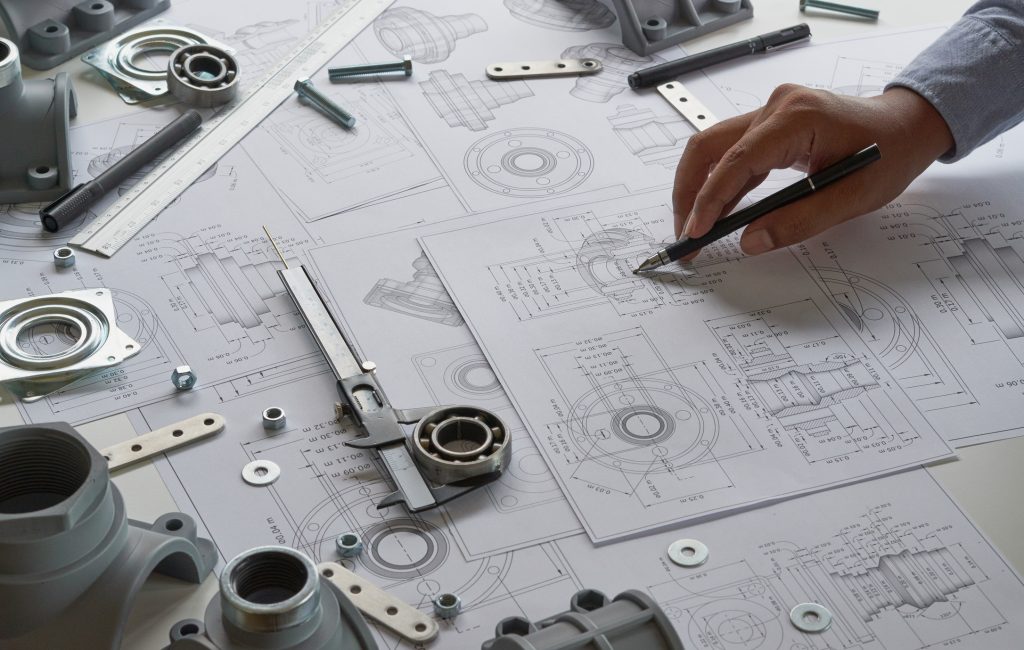
公差解析は、製品設計において必要不可欠な考え方です。単に部品のサイズを決めるだけでなく、組み立て後の動作や強度、さらには最終製品の品質管理までを含めた多角的な評価が求められます。特に、公差解析では個々の部品が持つ寸法公差、形状公差、位置公差などがどのように累積し、組み合わせによってどの程度のばらつきが発生するかをチェックします。
こうした綿密な検証は、事前にリスク要因を洗い出すことで、設計段階の調整による製造コスト削減を可能にし、量産時の不良率低減にも効果的です。また、公差解析を正しく行えば、最終的に製品精度向上につながり、結果的に顧客満足度の向上や市場での競争力強化にも寄与します。CADや3Dモデリングを活用した設計が主流になった今こそ、解析ツールを使いこなして確かなデータに基づいた意思決定を行うことが重要といえるでしょう。
公差解析とは何か?
公差解析とは、簡単に言えば“部品ごとの誤差の積み上げ”を予測し、製品全体として要求される機能や性能を満たすかどうかを検証するプロセスです。実際の製造現場では、寸法を理想値どおりに保つことは不可能であり、必ずある程度のばらつきが生まれます。例えば、位置公差が大きくずれれば、組み立ての際に回転や滑りがスムーズに行われなくなる可能性もあります。また、形状公差による面のたわみや傾きが想定以上に大きいと、密着が必要な箇所に隙間ができてしまうかもしれません。
こうした要因の総合的な影響を分析し、設計段階で最適な公差設定を行うことで、量産段階での不具合や手戻りを最小限に抑えることができるのです。公差解析を取り入れれば“作ってみないと分からない”という無駄な試作回数が減り、設計プロセス全体の効率化と信頼性向上が期待できます。
公差の種類とその影響
公差には、寸法公差、形状公差、位置公差という大きく3つの分類があります。
寸法公差は、部品の長さや直径などの許容範囲を示すもので、もっとも基本的な公差情報入力項目です。形状公差は、面の平面度や円筒度、真直度など、特定の形状要件をどこまで許容するかを決めるものです。これは、滑りや振動などに影響を与えやすい要素となります。位置公差は、穴の中心や形状の位置をどの程度の誤差で配置できるかを示したもので、複数の部品を組み合わせる際には特に重要な意味を持ちます。
これらの公差の設定には、製品の要求品質と製造コストが大きく関わってくるため、厳しすぎると加工工程や検査工程が過度に増えてしまう一方、緩すぎれば不良や組み立て不良を招くリスクが高まります。したがって、適切なバランスを見出すためには、各公差が最終製品の機能にどのような影響を及ぼすのかを理解し、全体を俯瞰した設計プロセスの中で整合性を取ることが大切です。
公差解析の役割と効果
公差解析は、制約の多い製品開発において、その制約をきちんと数値化し、最適解を探るための道具ともいえます。特に、3Dモデリングで大きなアセンブリを構築する際には、部分的な寸法誤差が他の部品へ波及し、思わぬ組立不具合を引き起こす可能性があります。
公差解析を導入することで、それぞれの部品が持つ寸法公差や形状公差、位置公差の範囲内で実際にどのくらいの組立偏差が生じるのかを予測し、製造リスクの早期発見に役立てることができます。これにより、手戻りを減らし、納期を守るだけでなく、品質管理面でも大きなメリットが得られます。
さらに、どの工程でどの程度の誤差を許容できるか明確になるため、加工や検査の工程設計にも指針が立てやすくなり、全体コストを管理しやすくなる利点もあります。公差解析を実践し、設計段階で精度とコストのバランスをとることが、製品開発の成功への近道となるでしょう。
実践!SOLIDWORKSで公差解析を行う手順

ここからは、具体的な手順に沿って公差解析を行う方法を解説します。実際にどのような流れで作業が進むのかを確認することで、設計の現場にそのまま応用できるようになります。主に解析の準備からデータ整理、そしてシミュレーション実行と結果の評価までを詳しく追いかけることで、全体の流れをつかみましょう。
解析ツール:TolAnalyst
TolAnalystはSOLIDWORKSに組み込まれている公差解析ツールで、寸法や位置公差、さらには形状公差の影響を定量的に評価できる機能を備えています。
使用方法として、最初にアセンブリ内で公差情報を入力(またはモデル上の注記を自動認識)し、解析の基準となる寸法の関係性を指定するステップがあります。その後、解析を実行すれば、部品間の取り合いが最悪ケースまたは統計解析のどちらの手法で評価されたかに応じて、部品ごとの誤差蓄積やトータルの寸法偏差が数値化されます。
この結果により、最適な公差設定や部品加工の優先度などを見直すことができ、無理な精度要求や過度なコスト発生を回避しやすくなります。解析結果の可視化も比較的優れており、色分けやグラフ表示などを通じて一目で問題点を把握できる点が実務では大変便利です。
解析の準備とデータ整理
解析を始めるにあたって、まずはモデルの状態を再点検し、必要な寸法公差、形状公差、位置公差などが正確に設定されているかを確認します。さらに、“どの部分に対する公差解析を行いたいのか”を明確にし、検証目的を絞り込むことが大切です。
アセンブリが複雑な場合は、最初から全てを解析対象にするのではなく、要所となる部品や組付け関係を中心に検討を進めると効果的です。加えて、どのような組立順序や製造工程が想定されているのかを把握しておくと、シミュレーションの設定がスムーズになります。
具体的な作業としては、CADモデル上の寸法注記を改めて見直し、実際の設計要求を満たすかどうか、余分な要素はないか確認する作業から始めると良いでしょう。これらの準備段階をしっかり踏まえておけば、解析結果を正確かつわかりやすい形で得ることができます。
ステップバイステップの解析手順
第一ステップでは、アセンブリ内で注目したい寸法をTolAnalystに認識させるため、解析対象の寸法と公差を指定します。必要に応じて、モデル上に注釈として定義されていない公差があれば追加しておきましょう。
第二ステップとして、解析用の設定を行います。これは、最悪ケース(ワーストケース)の解析なのか、あるいは統計的な要素を導入してRSS解析を行うのかを選択する段階です。
第三ステップでシミュレーションを実行し、その結果として総合的な寸法の変動範囲や、個々の部品がどの程度ばらつきに寄与しているかが数値化されます。
最後のステップでは、解析結果評価に基づき、要件を満たしていない部品や公差設定が厳しすぎる箇所があれば修正を検討します。こうしたプロセスの繰り返しにより、設計プロセスを合理化し、製造リスク低減を達成するための具体的なアクションが明確になるのです。
結果の評価と判断基準
解析結果を受け取ったら、まずは最大と最小の公差積み上げ値が、設計目標や組み立て要件を満たしているかどうかを確認します。
次に、各部品が製品全体のばらつきにどの程度寄与しているかを把握することで、設計の手直しを行うべき箇所を優先度順に洗い出すことができます。例えば、わずかな公差修正で大きな不具合が解消される部品がある場合は、そこを最初に改善するのが効率的です。
一方、公差を厳しくしすぎると加工コストや検査負荷が増大するため、企業やプロジェクトの方針に沿って費用対効果を評価する視点も欠かせません。また、解析後の判断基準としては、“改善で得られる品質向上と追加コストのバランス”を明確に示すと、チーム内での合意形成が進めやすくなるでしょう。
最適化された公差設定によって期待できるのは、組み立て段階での問題発生率の低減や、再加工の削減といったメリットであり、より信頼性の高い製品を短期間で市場に投入するための重要なカギとなります。
ケーススタディ:公差解析例
例えば、複数の部品からなるアセンブリで、位置公差が原因で組み立て不良が多発していたケースにおいて、公差解析を実施することで、部品間の重複干渉箇所がどの程度の頻度と許容量で発生するかを定量的に把握できます。その後も、最も寄与度の高い部品の寸法公差を適度に見直しすることで、結果的に組み立て作業がスムーズになり、検査に要する時間も削減され、全体の製造コスト削減につながります。
こうした公差解析事例を積み重ねることで、製品精度向上とともに企業としてのノウハウが蓄積され、将来の設計効率をさらに向上させる好循環を生み出せるのです。
よくある疑問とトラブルシューティング
公差解析は非常に有用な手法ですが、実際に取り組むうちにさまざまな疑問や問題に直面することもあります。
例えば、解析範囲が広すぎて計算時間が長くなる、あるいは公差情報が揃わないまま解析を進めてしまい、結果が不明瞭になるなどのケースです。また、解析ツールの操作や手順自体に慣れていないうちは、エラーが表示されても原因が分からず、無闇にパラメータを変更してしまうことがあるかもしれません。
そんなときに役立つ簡単な対策や、よくある質問への回答をまとめておくことで、初心者エンジニアでも対応策を見つけやすくなり、スムーズに設計改善へと移行できます。
以下は作成例ですので、作成の参考にしてください。
FAQ形式での解説
Q1: 初めてTolAnalystを使用したところ、解析対象外とみなされる寸法がありました。これをどう対処すれば良いでしょうか?
A1: 解析前にアセンブリの拘束条件や寸法注記が正しく関連付けられているかチェックし、必要ならモデル上で公差設定を補足してください。
Q2: 公差を厳しくしすぎるとコストが跳ね上がるのでは?
A2: その通りです。生産数や要求品質を踏まえて公差値を設定する必要があります。過度な厳格化は工数増につながるため、解析結果を見ながら最適な範囲を見出しましょう。
Q3: ワーストケース解析と統計解析のどちらが良い?
A3: 安全重視ならワーストケース、現場の実際のばらつきに近い評価をしたいなら統計解析が有効です。目的に合ったアプローチを選んでください。
Tips
公差解析をスムーズに進めるためのヒントとして、まずモデルの段階で過度に複雑な形状を取り扱う際は、重要度の高い部品や機能から先に解析を進めるのがお勧めです。ソフトウェアの機能をフル活用するためには、普段からアセンブリ構造や部品名の整理など、設計データを整頓しておくことが大切になります。
また、社内の他部門とも連携し、製造工程や品質検査の担当者へ要求値を伝えることで、より的確な公差設定が可能となるでしょう。さらに、解析結果のレポート出力時にはグラフや図表を積極的に取り入れ、視覚的にわかりやすい形で共有することで、チーム内での合意形成をスピーディに行えます。日頃から小さなプロジェクトでも公差解析を試み、ノウハウを積み上げていくことが、将来的な大きなリスク回避や設計教育の手助けにもなるはずです。
まとめ
今回紹介したように公差解析は、SOLIDWORKSなどのCADソフトウェアと解析ツールを組み合わせることで、効率良く実践できます。公差解析のメリットは、製品精度向上や設計最適化はもちろんのこと、組み立て上の不具合を未然に防ぎ、製造リスク低減につながる点にあります。
さらに、プロセスデータを蓄積していくことで、次回以降の設計に役立つ知見が生まれ、企業全体として品質管理のレベルが底上げされる効果も期待できます。特に初心者エンジニアにとっては、実務を通じて学習しやすい分野でもあるので、積極的に取り組むことでスキルアップにつなげることが可能でしょう。
公差解析をさらに深めたい場合は、まずSOLIDWORKSの公式ドキュメントやユーザーコミュニティを活用し、TolAnalystの詳細マニュアルや応用例を研究することをお勧めします。また、有償/無償のオンラインセミナーや設計教育プログラムを利用すれば、より実践的な操作技術を短期間で学習できます。
さらに、3DモデリングだけでなくCAEツールを組み合わせて構造解析や流体解析を行うことで、総合的なエンジニアリング力を高めることも可能です。社内で公差解析が浸透していない場合は、小規模なプロジェクトから実践し、その成果をチームで共有する文化を作ると良いでしょう。
こうした取り組みが積み重なれば、将来的には公差解析の専門家が社内に育ち、一層高度な設計最適化や迅速な製造リスク低減へとつながっていきます。
本記事が皆様のより良い活躍のきっかけとなれば幸いです。
記事中の用語
・寸法公差:製品の長さや幅などの寸法に許容される誤差範囲。
・形状公差:真円度、平面度、真直度など、形状要素に設定される公差。
・位置公差:穴や軸などの中心位置を制御する公差。
・TolAnalyst:SOLIDWORKS内で公差解析を行う専用モジュール。
・RSS解析:二乗平均平方根(Root Sum Square)を用いた統計的公差評価手法。
・ワーストケース解析:公差の最大・最小を積み上げて安全側のシナリオを想定する解析。
・CAD:Computer-Aided Designの略称。3Dモデリングや図面作成を行う設計支援ソフトウェア。
・CAE:Computer-Aided Engineeringの略称。構造解析や熱流体解析などを行うエンジニアリング支援ソフトウェア。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

参考情報
・SOLIDWORKS公式サイト
https://www.solidworks.com/ja
・SOLIDWORKSヘルプ:TolAnalyst の概要(TolAnalyst Overview)
https://help.solidworks.com/2025/japanese/SolidWorks/tolanalyst/c_TolAnalyst_Overview.htm