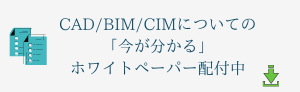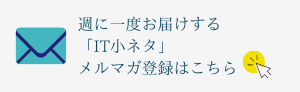いつものCADが電気設計の専門CADに?「ACAD-DENKI」を機能から事例、価格まで一挙解説
はじめに
電気制御CADの効率化や製造現場でのミス削減を目指している方にとって、どのようなCADシステムを選ぶかは極めて重要です。特に中規模電気製造企業の設計部長など、実際に設計業務を管理されている方々は、短納期やコスト削減、そして部品情報処理を含む幅広いニーズを同時に満たすソリューションを探されているのではないでしょうか。そこで注目されているのが、図研アルファテックが提供する「ACAD-DENKI」です。
これはBricsCADやAutoCADなど、業界標準のCADソフトウェアをベースにした電気制御CADで、図面管理やIO自動作図など、電気制御設計に特化した機能を搭載しています。さらに、設計のみならず製造支援機能まで網羅しているため、設計段階から製造現場まで一貫してデータを連携できる強みがあります。例えば、CADデータを用いて線番や部品番号を自動生成し、部材手配や加工工程に活用するといった仕組みを実装することで、一度入力した情報を重複して入力する必要がなくなります。これにより作業時間の短縮だけでなく、ヒューマンエラーの大幅な低減が期待できます。このような電気CADシステムの導入は企業のDX推進にも直結するため、デジタル化やデータ化の観点からも注目が集まっています。
本記事では、ACAD-DENKIの基本的な特徴や主要機能、実際の導入事例を通じてわかった具体的なメリット、そして価格情報やライセンス形態まで包括的に解説します。特に工数削減や品質向上を重要視される方々にとって、有益な情報が得られるはずです。さらに、導入を検討する際のFAQや、なぜACAD-DENKIが数ある電気CADの中でも選ばれているのか、その根拠についても言及いたします。実際に導入して成果を上げた企業の声を知ることで、導入後のイメージもより具体的に想像できるのではないでしょうか。この記事を読むことで、単なるCAD置き換えにとどまらず、設計から製造に至るプロセス全体を見直すヒントをつかんでいただければ幸いです。
ACAD-DENKIの概要と基本情報
画像引用: 図研アルファテック株式会社「ACAD-DENKI」
https://www.alfatech.jp/products/acad-denki/
ACAD-DENKIは、図研アルファテックが長年にわたり電機製造業界で培ってきた知見をもとに開発された、電気制御設計向けのCADシステムです。ベースとしてBricsCADまたはAutoCADが必要になるのが特徴で、業界標準のDWG形式に対応している点から、既存の図面資産を最大限に活用しやすくなっています。一般的な汎用CADに比べ、電気図作成や図面管理に特化した機能を最初から多数搭載しており、例えば配線や端子台、シンボルの配置など、電気制御CADならではの設計業務を迅速かつ正確に行えるのが大きな利点です。さらに部品情報処理による部品マスタ管理や、IO自動作図による効率的な図面展開など、製造現場につながるデータ活用が意識されています。
またACAD-DENKIの導入メリットは、設計部門だけで完結しないところにもあります。例えば、図面に紐づいた部品情報はそのまま購買部門や製造部門に送られ、調達や製造支援に活用される仕組みを整えやすいのです。これにより重複作業や入力ミスが減り、全社的に情報を共有することでDX推進にも拍車がかかります。近年は電気CADシステムをただ導入するだけでなく、デジタル化をとおして効率を高め、長期的な生産性向上を図りたいという企業が増えています。その要望に応えられるだけの機能とサポートを兼ね備えている点が、ACAD-DENKIの非常に強みとなっています。たとえば、導入支援からCAD教育まで対応できる技術サポートが充実しており、カスタマイズにも柔軟に応えてくれるため、企業独自の運用スタイルを確立しやすいのです。
さらに、コスト面も大事な要件です。ACAD-DENKIは他社製の電気CADと比較しても競争力のある価格設定を行っており、導入しやすいことがしばしば指摘されます。ライセンス形態もスタンドアロンとネットワークの両方を選択できるため、利用者数や企業規模に応じて柔軟に最適化が可能です。クラウド環境が進む現代とはいえ、製造現場によってはオフラインでの作業もあり得ますので、運用自由度の高さは魅力的でしょう。
製品の特徴と主な機能
ACAD-DENKIの大きな魅力は、汎用CADに電気制御設計ならではの機能を付加し、優れた操作性を保ちながら強力な作図支援を行う点です。例えば、電気図作成においては交点マークを自動で追加したり、シンボルを挿入するときに配線を自動でカットしたりといった、電気制御CAD特有のコマンドが用意されています。さらに複数図面全体にわたってリレーや端子番号を一括管理できるため、図面をまたぐ大規模プロジェクトでも整合性を保ちやすいのが特徴です。また、図面管理機能は「電キャビ」と呼ばれ、エクスプローラー形式での一括検索や連続印刷、図題情報のまとめて編集など、大量の図面を抱える現場で重宝される仕組みになっています。これにより、設計業務の効率化だけでなく、図面のバージョン管理や改訂履歴を明確に残しやすくなり、品質保証面でも安心感が高まります。
一方で、部品情報処理機能「ACAD-Parts」は、CADデータと部品データベースを緊密に連携させることができる強力なツールです。過去の設計情報を流用して必要な部品リストや配線情報をすぐに反映させることができるため、データ化とDX推進を同時に実現する企業も少なくありません。このようにして作成された図面や部品情報は、そのまま製造支援に活用されるケースが多く、これまで手動で行っていた入力作業や在庫管理をスムーズに行えるようになります。実際に、CADデータ連携により工数が大幅に削減された導入事例も多く報告されており、製品構成を柔軟に設定できることが、様々な業種・規模の企業に支持されている理由の一つです。
これらの機能が標準パックやフルパックといった複数のグレードに分かれて提供されるのも特筆すべき点です。企業の要件に合わせて必要な機能だけを組み込み、追加のカスタマイズも可能なため、初回導入時のハードルを低く抑えられるメリットがあります。また、BricsCADやAutoCADを導入済みであれば、その操作感やインターフェースをほぼそのまま活用できる点も魅力です。ACAD-DENKIならではの電気制御CAD機能と汎用CADの利便性を同時に手に入れることで、設計担当者のモチベーション向上にも寄与していると言われています。
動作環境と対応CADソフトウェア
ACAD-DENKIは、主に二つのベースCADに対応しています。ひとつはBricsCADで、もうひとつがAutoCADです。どちらのCADも業界標準のDWG形式を採用しているため、データ互換性が高く、既存の図面資産を用いたスムーズな移行が可能です。BricsCADとAutoCADのいずれを選んでも、Windows 10やWindows 11といった64ビットOS環境下で快適に動作するよう配慮されています。推奨スペックとしては、Intel Core i7やi9、あるいはAMD Ryzen 7や9を搭載したPCが推奨されており、グラフィックボードに関してもVRAM 4GB以上があると作図がさらにスムーズになります。特に大規模な制御設計や3D CADの操作を想定されている場合には、高いスペックを用意しておくことが望ましいです。
ライセンスの形態はスタンドアロン版とネットワーク版の二種類が用意されているので、企業の利用形態に応じて最適な選択がしやすいです。ネットワーク版の場合、FlexNet Publisherを使用してライセンスを一括管理できるため、例えば製造現場や設計部、さらには別拠点のチームが同一プログラムを必要な数だけ同時起動するといった運用にも対応できます。離れた環境で作業するスタッフ用に一時的にスタンドアロンライセンスを借用できる機能も用意されているので、外出先や出張先などで制御設計や図面管理が必要になったときにも柔軟に対処できるのは大きなアドバンテージでしょう。
一方で、AutoCAD LTには対応していないという点には注意が必要です。またWindowsのサポート状況に応じて、今後のバージョンアップでは対象OSが変わる可能性も考えられるため、導入前に使用するCADとOSのバージョンが最新の対応範囲であることを確認するのが望ましいです。動作環境や対応CADソフトウェアを事前にしっかり理解しておけば、稼働後に想定外の不具合が生じるリスクを低減でき、スムーズな設計業務の開始につなげられるでしょう。
主要機能の詳細解説
ACAD-DENKIの大きな魅力は、多岐にわたる主要機能が連携しあうことで、制御設計の一連の作業を最適化できる点にあります。はじめに、図面管理によって膨大なプロジェクトファイルを一元化し、標準化された作図を可能にする土台を築きます。続いて、部品情報処理を活用することで、設計時に利用するパーツ番号や仕様を自動的に抽出・反映し、重複入力やヒューマンエラーといった問題を減らしながら作業効率を上げられます。
さらに、IO自動作図機能があることで、制御盤における入力出力の情報をExcelなどにまとめておき、それをCADに取り込んで一気に図面展開するといった高度な自動化が実現できます。加えて、カスタマイズオプションも豊富で、ユーザーの業務フローに合わせたコマンドの追加や、既存のデータベースと連携した拡張などが可能です。また、データを企業のサーバー上に一元的に集約することで、ネットワーク経由でのライセンス運用やファイル共有も容易になり、設計者同士のコラボレーションがシームレスに進むようになります。こうした仕組みはDX推進の一環でもありながら、実務に即した具体的な機能として高く評価されています。
図面管理と部品情報処理
制御設計では、一つの製品や装置に対して多数の図面ファイルが発生しがちです。例えば電源回路や制御ロジック、操作パネル配線図など、多彩な設計資料が必要となります。ACAD-DENKIには「電キャビ」と呼ばれる図面管理機能が標準パック以上に付属し、これによって作品単位や物件単位で図面を効率的に管理できます。エクスプローラースタイルのインターフェースによって、図面の検索やソート、連続印刷などがまとめて行えるため、手間のかかるファイルの開閉や保存の作業を最小限に抑えられます。しかも図題情報をまとめて一気に書き換える機能があるので、大規模な設計変更が必要になった場合でも時間を大幅に短縮できるのは大きな強みです。
一方、部品情報処理機能「ACAD-Parts」は、設計の根幹を支える部品DBとCADを連動させる役割を担っています。この機能を活用すると、回路図上で部品を配置した際に、あらかじめ登録されている部品仕様や型番、さらには数量などの情報をCAD内部で一括管理できます。設計を進めながら部品リストを自動生成し、そのまま購買や製造現場に送り込めるため、伝票作成や入手チェックの工数を削減できる効果が期待できます。従来は「図面は単なるお絵描きツール」として活用されていた現場も、設計した情報を部品DBに反映させるだけで、手動入力の繰り返しから解放されるケースが多々あります。特に既存部品DBをCSV形式でインポート可能な点は、企業ごとに異なる資産をスムーズに引き継げるので導入時の抵抗を最小化できます。
これら二つの機能は相互作用によって強いシナジーを生み出します。図面管理が整っていることで、部品情報処理によって得られた部品リストを簡単にプロジェクト別またはバージョン別に集約できるほか、複数設計者が同時並行で作業する場面でも混乱を起こしにくいのです。設計者の誰かが部品データを追加・変更すれば、それが共有サーバーを介して全員のCAD環境に即時反映されるなど、情報の一貫性を保てる点が、最終的な生産性向上の大きな要因といえるでしょう。
IO自動作図とカスタマイズオプション
電気制御CADで特に作業負荷がかかりやすい工程の一つに、IO図面の作成があります。入力側と出力側の相互対応を正確に描き分けることが要求されるため、手動で行うと人的ミスが生じやすい上に工数も多くかかります。ACAD-DENKIでは「ACAD-IO」というIO自動作図モジュールが用意されており、Excelなどでまとめたアドレス情報やコメントを読み込んで一括で作成することが可能です。これにより、従来のようなコピペや文字修正の繰り返しが激減し、短時間で正確なIO図面が完成します。指示されたExcelフォーマットに情報を整理するだけなので、設計者以外の担当者もデータ入力を分担しやすい点がメリットです。
さらに大規模案件や外注先が多い場合は、カスタマイズオプションも検討するとよいでしょう。ACAD-DENKIでは、ユーザー定義のコマンドやスクリプトを追加することで、さらに業務体系にフィットした操作を実現できます。たとえばPDMシステムやERPシステムとの連動を図り、CAD上で設計した情報がリアルタイムに生産管理システムに連携されるようにすれば、手動でのトランザクションを大きく削減できます。また、FromToリストやケーブル接続情報の自動作成をカスタマイズすることで、製造支援の精度と速度を一段と引き上げる企業も存在します。これらのカスタマイズは一度開発して運用に載せることができれば、その後のDX推進にも継続的な効果を及ぼすため、初期投資としては十分に検討する価値があります。
IO自動作図やカスタマイズによって得られる運用効率化の効果は、短期的な工数削減だけでなく、長期的な品質維持にもつながります。図面修正の際にも、既存のExcelデータやマスタ情報を参照して部分的に再作図ができるため、変更漏れやバージョン管理の混乱を防げるからです。従って、ACAD-DENKIを導入する際は、標準機能の活用とともに業務フローに合わせたカスタマイズ導入も見据えておくと、より高いROIを期待できるでしょう。
データ一元管理とライセンス形態
設計や製造現場が複数の部署や工場にまたがる場合、データ一元管理の仕組みが整っていないと、図面の旧バージョンが混在してしまうなどの問題に直面しがちです。ACAD-DENKIでは、シンボルや設定ファイル、図面や部品情報といった要素をサーバー側で一元管理する運用が可能です。スタンドアロンライセンスでも一元管理を実現できる一方、ネットワークライセンスを導入すると、メインサーバーでライセンス管理をするため、複数のPCが同時にCADシステムを利用しやすくなります。必要な分だけライセンスを確保すればよいため、無駄なコストを抑えつつ業務のピークに合わせた柔軟な運用ができます。
ネットワークライセンスの場合、遠隔地の拠点や出張先でもライセンスを借用して作業できる機能が提供されているのも利点です。出張先の製造現場で急な修正が必要になった際、わざわざ拠点に戻らなくても作図やデータ化が可能だからです。こういった仕組みは、社内の情報共有を促進し、DX推進にも大きく寄与します。また、ライセンスを一元管理することで、ソフトウェアバージョンがバラバラになる恐れを最低限に抑えられ、サポート契約を更新する際にも手続きが簡易化されます。
コスト面では、スタンドアロンとネットワークのいずれも年間サポート契約を結ぶことで、バージョンアップや電話・メールによる問い合わせ対応を受けられます。こうしたサポート体制のおかげで、安心してライセンスを長期運用できるのです。特にCAD教育や技術サポートが必要な場合は、サポート契約の存在が重要になります。新たに配属された設計者や、CAD操作に慣れていないスタッフのトレーニングを行う上でも、公式資料と専門スタッフのサポートが受けられるのは心強いでしょう。
実際の導入事例
理論上のメリットだけでなく、実際にACAD-DENKIを導入して大きな成果を上げた企業の事例を知ることで、導入後の具体的なイメージを持ちやすくなります。ここでは、アイム製作所と三葉電機工業の二社における事例を中心に解説します。どちらの企業も、設計部門から製造現場までのワークフローを改善し、その効率性を飛躍的に向上させたことが特徴です。部品情報処理やCADデータ連携は実際にどう役立つのか、さらにはIO自動作図やカスタマイズの効果のほどは――といった疑問に答える事例です。こうした事例を参考に、自社での電気CAD導入に際してどの部分を重点的に改善可能か思い描くことが大切です。
アイム製作所の事例
画像引用: 図研アルファテック株式会社「アイム製作所様 導入事例」
https://www.alfatech.jp/users/eim2023.html
アイム製作所は公共設備や化学設備などの制御盤製造を得意とする企業で、2009年にACAD-DENKIを導入しました。当初は“お絵描き”としてのCAD運用が主流で、図面がデータ化されても部品表や購買情報との連携が十分にとれていませんでした。しかし、ACAD-DENKIの導入で、CADをただの作図ツールではなく、設計で生まれる情報を最大限に活用するシステムへと変革することができたのです。具体的には、部品情報処理機能を使って部品DBを構築し、CAD上のユーザー属性へ設定することで、購買管理とのデータ連携を自動化しました。これにより、人為的な入力ミスや転記作業が大幅に削減され、設計者はより高度な制御設計に集中できる環境が整備されました。
さらに、製造現場では線番の自動生成や器具番号のラベル作成をCADデータからダイレクトに行えるようになり、以前は数時間を要していた作業がわずか数分で完了するようになったといいます。ちなみに設計工程においては、1オーダーあたり14時間を超える工数削減に成功したというデータも公開されています。これは単に時間の削減だけでなく、品質面にも寄与しています。以前は複数の担当者が手入力で情報を引き継ぐために発生していたヒューマンエラーがほぼ消滅し、配線ミスや発注ミスも激減しました。こうした事例を通じて、組織全体でのデータ活用の重要性と、ACAD-DENKIによる電気制御CADの有効性が具体的に示されています。
社員の意識改革にも寄与している点も見逃せません。アイム製作所では、デジタルの有用性を実感した人が増えたことで、他の業務領域にもデジタル化を拡張しようとする動きが自然発生的に起こったそうです。これにより同社はDX推進に大きく前進し、結果的に企業全体の生産性が底上げされる好循環を生み出しました。デザインだけでなく、社内文化変革のきっかけにもなるのが、ACAD-DENKIの潜在的な力の大きさを物語るエピソードだといえるでしょう。
三葉電機工業の事例
画像引用: 図研アルファテック株式会社「三葉電機工業株式会社様 導入事例」
https://www.alfatech.jp/users/mitsubadenkikogyo.html
三葉電機工業は官公庁や一般施設などの受配電設備や監視盤の回路設計・製造を行う企業で、ACAD-DENKI導入以前は他社製電気CADを使っていました。しかし既存CADでは接点情報の管理や部品拾いがすべて手作業であったため、設計ミスやライセンスのコスト問題がしばしば課題になっていたといいます。そこで、現場と協力してCADリプレースを検討し、最終的にACAD-DENKIを選んだのが導入の経緯です。
導入後の最大の効果は、電気図から外形シンボルを展開してミス・ロスを削減しつつ、設計データを社内発注システムへ直接連携できる点にあるといいます。CADデータに基づいて自動的に部品情報を抽出するため、担当者が手打ちで入力する必要がなくなり、転記ミスや発注数のズレが激減しました。しかも、その情報をそのまま製造現場の線番プリンタや器具番号シール作成ソフトへ連携しているため、こちらも目視チェックが不要になり、非常に短い時間で準備できるようになりました。
加えて、BricsCAD Proのライセンスを導入することで3Dモデルを活用する試みも進められています。板金部分や銅帯などの干渉チェックを3Dモデル上でシミュレートし、問題箇所があれば設計段階で修正できるのです。今後さらに少子化が進む中で、短納期対応や熟練工の退職を見越して、CAx技術をより深く活用することで生産性の向上を目指す方針だといいます。三葉電機工業の例は、単なるコスト削減にとどまらず、3D展開や高度なデータ連携を含む包括的なデジタル化戦略を実践している好例といえるでしょう。企業として得られるメリットは多岐にわたり、ACAD-DENKIを足がかりにしてより幅広い業務改革を実現することも十分可能なのです。
価格情報とコストパフォーマンス
ACAD-DENKIの価格帯は電気CAD業界の中でも特に競争力があると評されています。製品構成としては、主に「作図パック」「標準パック」「フルパック」「フルパックPlus」の4つのグレードが存在し、目的や利用範囲に応じて選択できるようになっています。2025年2月7日現在、販売代理店である大塚商会のWebサイトによると、ACAD-DENKIの価格は以下の通りです。
画像・価格引用: CADJAPAN.com「ACAD-DENKI 価格」
https://www.cadjapan.com/products/items/acad_denki/price.html
最も基本的な作図パックがスタンドアロン版で24万円(税別)、最も上位のフルパックPlusでスタンドアロン版60万円(税別)というラインナップは、多機能でありながら導入しやすい価格帯といえるのではないでしょうか。ネットワーク版はスタンドアロン版の1.2倍ほどの価格設定で、ややコストは上昇しますが、ライセンスを複数人で共有したい企業にとっては無駄の少ない選択肢です。
ベースとなるBricsCADまたはAutoCAD自体のライセンス費用は別途必要になる点に留意が必要ですが、すでにAutoCADを導入している企業や、BricsCADに切り替える余地がある企業はスムーズに比較検討できるでしょう。なお、ネットワークライセンスを導入する場合はFlexNetライセンス管理サービスが別途17万円(税別)かかり、管理サーバーのサポートにも3万円(税別)の年間費用が必要です。とはいえ、これにより複数拠点などからライセンスを柔軟に借用でき、多人数が同時利用してもコスト最適化が図れるので、運用形態次第では十分に元が取れる投資といえます。
さらに年間サポート契約が用意されており、最新バージョンの無償提供や問い合わせ対応を受けられるため、長期運用を見据えるとコストパフォーマンスは高いといえます。特に、設計業務が止まることは生産計画全体に響くため、技術サポートが手厚いことは企業のリスク管理上も大きなメリットでしょう。多くの導入企業が、CAD導入の初期費用と維持費を合わせてみても、作業効率化による人件費の削減効果やプロジェクトごとのリードタイム短縮を考慮すれば十分ペイできると報告しています。
各グレードの価格とサポートオプション
ACAD-DENKIのグレード構成は用途や機能に応じて明確に区分されています。シンプルな図面作成と基本的な電気制御CAD機能があればよいなら「作図パック」を、複数の図面管理や部品情報処理を本格的に使いたいなら「標準パック」以上を、といった形で最適な組み合わせを選ぶとよいでしょう。さらに「フルパック」では標準パックに加え、より高度で包括的な機能が活用でき、部品DBとの連携や複数図面の相互参照など、大規模な制御設計に対応しやすくなります。
そしてフルパックPlusになると、IO自動作図モジュールが加わり、Excelなどの表形式データをもとに一気にIO図面を作成したり、カスタマイズオプションを追加しやすくなるといったメリットがあります。実際に、設計工数や修正ミスを可能な限り減らしたい企業であれば、フルパックPlusの導入効果は顕著です。これらのグレードには、年間サポート契約が任意で付けられますが、導入企業の多くは申し込む傾向にあります。理由としては、最新版のソフトウェアを常に利用できることや、電話やメールでのオペレーション問い合わせがスピーディに対応される安心感が大きいからです。
なお、年間サポートの契約額は所有ライセンスの合計金額や、最低限の契約金額などによって決定されるため、導入ライセンス数を増やす際はサポート費の見直しも考慮する必要があります。ただ、技術サポートやメンテナンスを受けられるという意味では、導入後の作業トラブルに即応できる利点は計り知れません。特に新規導入時だけでなく、将来的な人員の入れ替えや拡大、または設計部署の増設を検討している場合、安定した体制で運用し続けるためのコストとして十分に許容されることが多いようです。結果的に、各グレードの価格とサポート費用を総合的に見ても、信頼性や効率化から生まれる利益を考慮すれば十分に優れた投資対効果が得られるという意見が多くあります。
まとめ
ACAD-DENKIは、電気CAD業界や制御設計の現場で長年培われてきた要件を的確に捉えた、高機能かつ操作性の良いCADシステムとして高い評価を得ています。身近なBricsCADやAutoCADをベースとし、業界標準のDWG形式を活用できるため、既存の図面資産をそのまま流用できる点は、導入ハードルを大幅に下げる要因となっています。さらに、図面管理、IO自動作図、部品情報処理といった機能が、購買部門や製造現場まで巻き込んだ一連のデータ活用を可能にし、結果的に工数削減と品質向上を同時に実現しやすいのです。
加えてカスタマイズ性が高いため、企業ごとに特殊な組み立てやプロセス管理を行っている場合でも、柔軟に対応できる点がDX推進のトリガーとなっています。導入事例からもわかるように、アイム製作所では手作業中心の運用から一転して、設計データをフルに活用する文化が育まれました。また、三葉電機工業は設計の効率化だけでなく3D CAD展開や発注システムとの連携を視野に入れ、製造支援の最適化を進めています。こうした事例は、単なるコスト比較だけではなく、電気制御CADをLANやクラウドを通じて組織全体で活用するという、新たな価値創造の可能性を示しています。
価格面も、より多くの企業が導入を検討しやすいファクターです。他の専用CADと比較した場合でも、スタンドアロン版やネットワーク版を含む多様なライセンス形態が用意されており、必要な機能に合わせてグレードを選び、予算に応じた導入が実現しやすいことが魅力です。そして何より、技術サポートやCAD教育プログラムが充実しているので、社内での使いこなしをサポートしてくれる環境が整っています。結果として、長期的に見てもデータ化やデジタル化によるコスト削減効果と高いROIが期待できるのです。電気制御CADの導入を本格的に検討される方にとっては、作図の効率化だけでなく、部門間連携やDX推進、そして企業文化の変革をも視野に入れられるスマートな選択肢と言えるでしょう。ぜひ、ACAD-DENKIをご検討してみてはいかがでしょうか。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

参考情報:
・図研アルファテック株式会社「ACAD-DENKI」
https://www.alfatech.jp/products/acad-denki/
・ 図研アルファテック株式会社「アイム製作所様 導入事例」
https://www.alfatech.jp/users/eim2023.html
・ 図研アルファテック株式会社「三葉電機工業株式会社様 導入事例」
https://www.alfatech.jp/users/mitsubadenkikogyo.html
・ CADJAPAN.com「ACAD-DENKI 価格」
https://www.cadjapan.com/products/items/acad_denki/price.html