ベクターワークス2018 PDF取り込み完全ガイド|基本操作から編集のコツまで
1. はじめに

Vectorworks 2018(ベクターワークス2018)は、CADソフトの中でも幅広い業種で活用されている代表的なソフトウェアです。建築設計をはじめ、インテリアデザインや舞台美術といった分野でも利用され、図面の作成や編集だけでなく、プレゼンテーション用の資料作成にも大きな力を発揮します。
特に便利なのがPDF取り込み機能です。この機能を使うことで、他のソフトで作成したPDFファイルや紙の図面をスキャンしたPDFを簡単に統合し、Vectorworks上でCADデータとして再利用することができます。設計業務の効率化や既存資料の活用に役立つため、多くのユーザーにとって必須の機能と言えるでしょう。
しかし、PDFには「ベクターデータ」と「ラスター画像」が混在していることがあり、それぞれの特徴を理解していないと編集作業で思わぬ制限や不便が生じます。たとえば、線や文字として扱えるはずの部分が画像化されてしまい修正できなかったり、逆にデータ量が大きくなりすぎて動作が重くなったりするケースもあります。また、フォントの互換性による文字化けなど、トラブルが発生することも少なくありません。
この記事では、PDFをVectorworks 2018に取り込むための具体的な操作手順や活用のメリットを、中学生でも理解できるように平易な言葉で解説します。さらに、取り込み後に行える編集方法や注意しておきたいポイント、トラブルが起こった場合の対処法についても詳しく紹介します。
加えて、実務においてどのように役立つのか、また他バージョンのVectorworksやAutoCAD・Illustrator・DWG/DXFといった他CADソフトとの互換性についても触れていきます。読み進めることで、PDFをスムーズに取り込み、効率よく編集するための具体的なノウハウが身につきます。記事内で紹介する実践的な手順やデータ軽量化のコツを活用し、Vectorworks 2018でのPDF編集をより快適で実用的なものにしてください。
2. Vectorworks 2018でPDFを取り込むメリット
Vectorworks 2018でPDFを取り込むことには、いくつもの大きな利点があります。なかでも注目すべきは、CAD間の互換性を補えること、アナログ資料を効率的にデジタル化できること、プレゼン資料づくりがスムーズになること、そして印刷イメージを事前に確認できることです。これらの機能を活用することで、日常業務の効率化や品質向上につながり、建築設計やインテリアデザイン、舞台美術といった幅広い分野で役立ちます。
ここでは、それらのメリットを4つのポイントに分け、より詳しく紹介していきます。
2.1 CAD間の互換性とデータ再利用
AutoCADやIllustratorなど、他のCADソフトで作成されたデータは、必ずしもDWGやDXF形式で受け渡しできるとは限りません。こうした場合でもPDF形式であれば、ほとんどの環境で共有が可能です。Vectorworks 2018にPDFを取り込めば、別ソフトで制作された資料を直接参照できるだけでなく、必要に応じて編集や修正にも活かすことができます。
たとえば、協力会社やクライアントから提供されたPDF図面をそのままVectorworks上で利用できれば、作業のやり直しや変換の手間を大幅に削減できます。また、過去のプロジェクト資料がPDF化されて保管されている場合も、Vectorworksに取り込んで再利用できるため、資料探しや再構築に費やす時間を短縮できるのです。この互換性の高さが、プロジェクト全体のスピードと柔軟性を大きく高めます。
2.2 アナログ資料のデジタル活用
手書きの図面や紙で配布された資料も、スキャンしてPDF化すればVectorworks 2018に取り込み可能です。取り込んだPDFは、参照用の下絵として利用したり、寸法の確認に使ったり、新しい設計を重ね描きするためのベースとして活用できます。
アナログ資料をそのまま扱うと、紙の折れや破れ、劣化といったリスクがありますが、PDFとして保存しておけば半永久的にデータを残せます。特に建築分野や舞台美術のように歴史的な図面やメモを大切に扱う分野では、こうしたデジタル化による保存は非常に価値があります。効率的な資料管理とバックアップの両立が可能になり、設計資産を長期的に守ることができます。
2.3 プレゼン資料としての活用
プレゼンテーションの場面では、PDFファイルの活用が大きな武器になります。Vectorworks 2018にPDFを配置することで、図面やレイアウト全体を見渡しながら資料を組み込めるため、より説得力のあるビジュアルを作り出せます。
例えば、製品カタログの写真や完成イメージのパースをPDF化しておき、必要な場面で配置すれば、短時間でわかりやすい資料が完成します。建築提案やインテリアデザインのプレゼンでは、こうしたビジュアル資料の効果は絶大です。さらに、配置後はレイアウト変更や縮尺調整、トリミングも自由に行えるため、柔軟で洗練されたプレゼン資料を作成できます。
2.4 印刷イメージの確認と調整
PDFを取り込むもうひとつの大きなメリットは、印刷物の完成イメージを事前に把握できる点です。最終的に紙で出力することを想定したデータをあらかじめVectorworksに配置しておけば、ページの分割状態や余白(マージン)のバランスを目で確認できます。
たとえば、舞台美術の施工図や建築の実施図を印刷する際、フォントがかすれていないか、画像が切れていないかといった点を事前にチェックして修正できるのです。これにより、印刷ミスを減らすだけでなく、余分な印刷コストの削減や資料の完成度向上にもつながります。効率よく仕上げたい実務の現場にとって、大きな助けとなるでしょう。
このように、Vectorworks 2018のPDF取り込み機能は「互換性」「デジタル化」「プレゼン強化」「印刷確認」という4つの観点から、日々の設計や資料作成を大幅に効率化します。PDFを上手に取り込むことで、作業の幅が広がり、業務の質とスピードを同時に高めることができるのです。
3. PDFの取り込み手順
ここでは、Vectorworks 2018にPDFファイルを読み込む際の操作手順を、具体的に解説します。初めて利用する方でも迷わず進められるよう、流れを順を追って説明していきます。手順を正しく理解しておくことで、読み込み作業でつまずくリスクを減らし、効率的に編集や加工ができるようになります。さらに、取り込み後のトリミングや縮尺調整のコツについても触れるので、実務でもすぐに役立てられるでしょう。
以下では3つの小見出しに分けて、取り込みの流れを丁寧に紹介します。
3.1 基本的なメニュー操作
PDFをVectorworksに取り込む際は、まず画面上部のメニューから「ファイル」→「読み込み」→「PDFを取り込み」を順に選択します。するとファイル選択のダイアログが表示されるので、取り込みたいPDFファイルを指定してください。
読み込みを実行すると、次にPDFのページ選択ウィンドウが開きます。複数ページを持つPDFの場合、この段階で必要なページだけを選べます。たとえば施工図のうち一部だけを使用したい場合には、この機能で必要なページだけを取り込むと、余計なデータを増やさずに済みます。結果としてファイルが軽量化され、後の作業が快適になります。
基本的な操作自体はシンプルですが、後々の編集作業や作業効率に大きく影響するため、どのページを取り込むかを慎重に選ぶことが重要です。
3.2 ページ選択と軽量化
特に注意が必要なのは、多ページかつ容量の大きいPDFを取り込む場合です。すべてのページを無条件で読み込むと、ファイル容量が膨れ上がり、動作が遅くなってしまうことがあります。高解像度の画像が含まれている場合には、さらに処理が重くなる可能性があります。
こうした事態を避けるためには、取り込みの段階で本当に必要なページだけを選ぶことが効果的です。また、取り込む前にPDFを別のソフト(たとえばAdobe AcrobatやIllustratorなど)で事前に編集し、不要な要素を削除したり解像度を調整してから読み込むのも有効です。
場合によっては、画質を多少落としてでも作業性を優先するほうが実務では合理的です。CAD作業では、必要な情報を読み取れるレベルの画質さえあれば十分であり、データが重すぎるとむしろ効率を妨げます。取り込み前のちょっとした工夫が、作業全体のスピードを大きく左右するのです。
3.3 配置設定と縮尺調整
ページ選択が終わったら、次はPDFを図面上に配置するステップに移ります。このとき最も重要なのは、縮尺を正しく設定することです。CADソフトでは縮尺の誤差がそのまま寸法の狂いにつながり、設計や製作の精度に大きな影響を与えます。
配置後には必ず寸法を測り、想定していた長さや幅と一致しているか確認しましょう。もし数値が合わない場合は、再度スケール設定をやり直す必要があります。その際には、正確な数値を入力することや、基準となる線分を使って縮尺を合わせることが効果的です。
また、位置を調整する際には、座標軸やガイドラインを活用することでスムーズに配置できます。建築設計の平面図だけでなく、インテリアの家具レイアウトや舞台美術の舞台配置などでも、この「基準に沿った調整」の考え方は共通しています。正確な縮尺と位置を意識することで、後々の修正作業も最小限で済ませることができるのです。
このように、PDFをVectorworks 2018に取り込む手順は一見シンプルですが、「ページ選択」「軽量化」「縮尺調整」といったポイントを意識することで、効率的かつ精度の高い作業が可能になります。正しい手順を身につけておけば、日常業務の中で安心してPDFを活用できるようになるでしょう。
4. 取り込み後の編集と制限
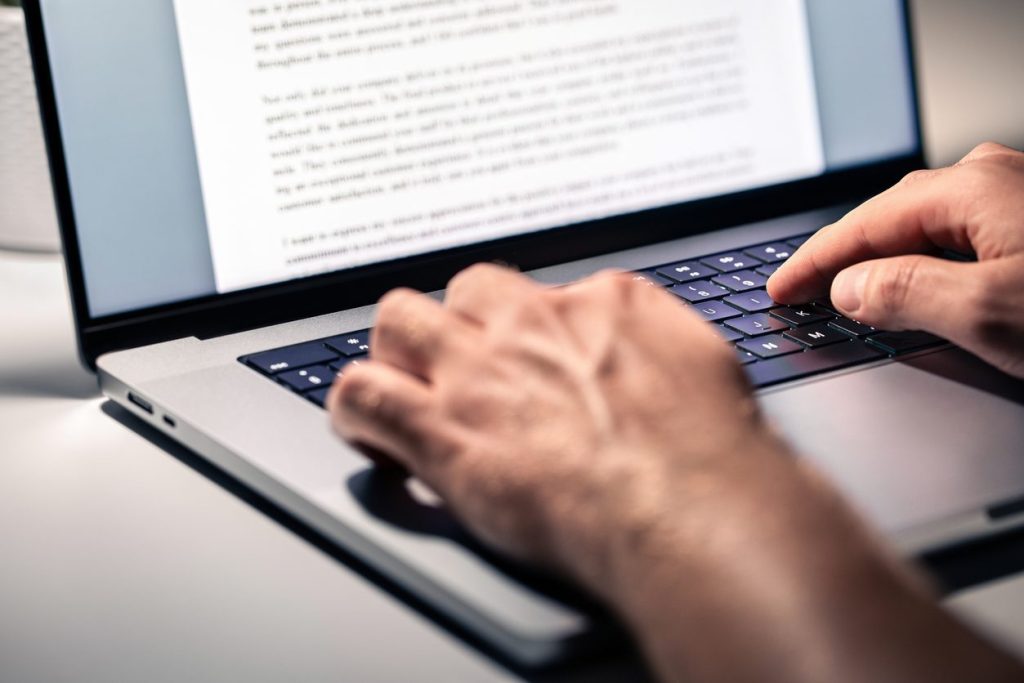
PDFファイルをVectorworks 2018に取り込んだあとは、「どの部分をどの程度編集できるのか」が次の大きなポイントになります。PDFはその性質上、ベクターデータで構成されたものと、ラスター画像として保存されたものがあり、ひとつのファイルの中で両方が混在しているケースも少なくありません。
ベクターPDFであれば線分や図形として編集できる一方で、ラスターPDFは拡大すると画質が荒くなったり、線単位での修正ができないといった制限があります。さらに、文字化けを防ぐためのフォント対応や、ファイルサイズ調整といった管理上の工夫も求められます。
ここでは、取り込み後に注意すべき編集上のポイントを3つの観点から詳しく見ていきましょう。
4.1 ベクターPDFの編集可能性
ベクターPDFとは、CADやIllustratorのようにベクターデータで作成されたPDFのことを指します。この形式のPDFをVectorworks 2018に取り込むと、線分や図形が個別のオブジェクトとして認識されるため、編集の自由度が大幅に広がります。
たとえば、寸法線を延長したり、不要な部分をトリミングしたり、線の色や線種を変更したりといった細かな編集が可能です。そのため、ベクターPDFは「再利用性の高いデータ形式」と言えます。特に既存の図面を下地として活用する際には、大きなメリットとなります。
ただし注意点もあります。PDF変換の過程で線が細かく分割されてしまい、扱いにくくなるケースがあるほか、フォントが正しく読み込まれず文字化けする場合もあります。そのため、編集後には図面全体を確認し、思わぬ崩れや欠損がないかを丁寧にチェックすることが大切です。
4.2 ラスターPDFの取扱い
一方で、スキャンした図面や写真をPDF化したものは、ほとんどがラスター画像として認識されます。ラスター画像はピクセル単位の情報で構成されているため、拡大するとぼやけたり荒れたりするほか、線や図形を個別に編集することはできません。
とはいえ、用途次第では十分に役立ちます。例えば、手書きスケッチをスキャンしてPDFとして取り込み、それを背景や下絵として配置すれば、その上から正確なCAD図形を描き起こすことができます。これは、アナログのアイデアをデジタルに変換する際の有効な方法です。
ただし、ラスターPDFは解像度が高すぎるとファイルが重くなり、動作が遅くなることがあります。取り込む前に解像度を調整しておくか、読み込み時に軽量化を意識することで、快適に扱えるようになります。適切な解像度設定は、実務における作業効率を大きく左右するポイントです。
4.3 フォントとファイルサイズの調整
PDFを取り込む際、もうひとつ気を付けたいのがフォントとファイルサイズの問題です。ベクターPDFであれば、文字情報がそのまま取り込まれることがありますが、使用されているフォントがVectorworks 2018にインストールされていない場合、文字化けが発生する恐れがあります。
このようなトラブルを避けるためには、PDFを作成する段階でフォントを埋め込んでもらうか、Vectorworks側で似たフォントに置き換えて調整する必要があります。特に建築図面や仕様書など、文字情報が多い資料では、フォントの扱い方が完成度を左右します。
また、ファイルサイズが大きすぎると、作業中の動作が重くなり、効率が低下します。スキャン時に必要以上に高解像度を選ばず、プレゼンや作業に支障のない範囲でデータを軽量化しておくことが大切です。サイズ調整を行うことで、自分の作業が快適になるだけでなく、他の協力会社やクライアントにデータを受け渡す際のストレス軽減にもつながります。
このように、Vectorworks 2018でPDFを取り込んだ後の編集には「ベクターPDFなら細かく編集できる」「ラスターPDFは背景利用に適している」「フォントとファイルサイズ管理が重要」といった特徴と制限があります。これらを理解しておけば、PDFをただ読み込むだけでなく、実務に合わせて効果的に活用できるようになるでしょう。
5. 実務での活用シーン
ここでは、Vectorworks 2018のPDF取り込み機能が実際の業務でどのように役立つのかを具体的に紹介します。建築設計、インテリアデザイン、舞台美術といった分野では、日常的にPDF化された図面や資料を取り扱う機会があり、それらを効率的に再利用することで業務の質とスピードが大きく向上します。
また、協力会社やメーカーから送られてくる施工図やカタログPDFを直接読み込めることにより、打ち合わせや修正作業がスムーズに進みます。目的に応じてPDFを適切に活用すれば、プレゼン資料や提案書の完成度も高まり、クライアントへの説得力も増すでしょう。
以下では、代表的な4つのシーンを例に挙げ、PDF取り込み機能がどのように効果を発揮するのかを詳しく解説します。
5.1 建築設計での活用
建築設計の現場では、AutoCAD由来のDWGファイルを直接やり取りするケースが多いものの、互換性やトラブル回避の観点からPDF形式で図面を共有することも少なくありません。こうした場合、Vectorworks 2018にPDFを読み込むことで、図面の再利用や変更点のマーキングを効率よく行うことができます。
施工段階で急な修正が必要になった場合でも、赤入れされたPDFを取り込み、即座に修正指示書を作成することができるため、納期の短縮や関係者間の情報共有に大きな効果を発揮します。
5.2 インテリアデザインのプレゼンボード作成
インテリアデザインの分野では、メーカーのカタログや資料をPDF形式で取り込むケースが非常に多く見られます。色や素材感を示すイメージ写真、家具や什器の配置図、リストなどを一枚のプレゼンボードに集約する際、PDF編集機能は大変役立ちます。
Vectorworks 2018上で縮尺を調整したり、必要に応じてトリミングを行い、図面と写真をバランスよくレイアウトすることで、提案内容を視覚的に分かりやすく伝えることが可能です。そのまま印刷・配布できるのも魅力で、クライアントに即応した提案ができます。
紙資料では修正や更新が煩雑になりますが、PDFをベースにしたデジタル管理なら変更への対応も柔軟で、プロジェクト全体のスピード感を維持できます。
5.3 舞台美術の設計と修正
舞台美術の分野では、ステージプランや背景デザインの図面を他部門と共有する機会が多くあります。Vectorworks 2018にPDF化された舞台図面やラフスケッチを取り込めば、演出家や照明担当者と同じ画面を見ながら調整を進めることができます。
また、登場人物の動線や小道具の配置を検討する際、PDFを下地にして新しいレイヤーに補足を描き込むと、修正や変更が容易になります。舞台はイベントごとに細かな変更が生じることが多いため、スキャンされたメモや修正指示をそのまま読み込んで活用できるのは大きな時短効果となります。短い準備期間の中でも柔軟な対応が可能になるのです。
5.4 施工図のチェックと修正
建築やインテリアの施工現場では、協力会社から施工図面をPDFで受け取るケースが頻繁にあります。こうしたPDFをVectorworks 2018に取り込むことで、既存の図面と比較しながら新しい寸法を記入したり、位置のズレを確認したりできます。
ベクターPDFであれば、細かい線分や寸法の直接編集が可能な場合もあり、即座に修正作業へと移行できます。特に工期が限られたプロジェクトでは、こうした迅速なチェックと修正が大きな武器となります。
さらに、現場では大量のファイルを扱うことが多いため、PDFごとに内容を整理して反映させることで、誤解や見落としを防ぎやすくなります。確認作業を効率化することで、やりとりの正確性も向上し、全体の進行がスムーズになります。
このように、Vectorworks 2018のPDF取り込み機能は「建築設計」「インテリアデザイン」「舞台美術」「施工図チェック」といった多様なシーンで威力を発揮します。単なる資料の取り込みにとどまらず、コミュニケーションの改善や作業効率化、さらには提案力の強化にもつながるため、実務において欠かせない機能といえるでしょう。
6. トラブルシューティング

Vectorworks 2018でPDFを取り込む際には、便利な一方でいくつかのトラブルに遭遇することがあります。代表的なものとしては「文字化け」「線の編集に関する問題」「ファイルサイズの肥大化」が挙げられます。これらのトラブルは原因を理解し、適切な対処法をあらかじめ知っておくことで、作業の停滞を防ぎスムーズな業務進行につなげることができます。
ここでは、よくあるトラブルとその解決策を3つのポイントに分けて紹介します。トラブルを未然に防ぎ、PDFを安心して再利用できる環境を整えていきましょう。
6.1 文字化けとフォントの問題
PDFを取り込んだ際に文字化けが発生する大きな原因は、作成元で使用されたフォントがVectorworks 2018側に存在しないことです。この場合、文字が意味不明な記号に置き換わったり、フォントそのものが別のものに変換されてしまうことがあります。
解決策としては以下のような方法が有効です。
作成者に依頼する方法:PDF作成時に「フォントを埋め込む」設定を有効にしてもらう。
Vectorworks側での対応:プリファレンス設定で「代替フォント」を指定し、見た目を大きく崩さずに表示する。
フォントファイルの導入:特殊なフォントを頻繁に使う資料であれば、同じフォントファイルをインストールしてからPDFを読み込む。
これらを実施することで、文字の可読性を保ちながら作業を継続できます。特に建築図面や仕様書のように文字情報が多い資料では、事前のフォント対策が重要です。
6.2 線の編集問題とその対策
ベクターデータで作られたPDFであっても、Vectorworksに取り込むと細かく分割された線の集合体になってしまうことがあります。その結果、一本の線を修正するつもりが複数の断片を扱う必要が生じ、編集に手間がかかってしまいます。
また、スキャン画像などラスター化された部分は拡大しても線として認識されず、編集そのものが不可能です。
こうした問題を軽減する方法としては、可能であればPDFではなくDXFやDWGといったネイティブなCAD形式でデータを受け取るのが理想的です。もしPDFしか入手できない場合は、Vectorworks上で「線の統合」や「再編集」を行い、不足部分を補う形で修正を進める必要があります。多少の手間はかかりますが、最終的な図面の完成度を高めるためには欠かせないプロセスです。
6.3 ファイルの重さと解像度調整
PDFに高解像度のスキャン画像や写真が多く含まれている場合、取り込み後のファイルが非常に重くなり、作業画面の反応が遅くなることがあります。保存や印刷にも時間がかかり、業務効率を下げる要因となります。
この問題を避けるためには、以下の工夫が効果的です。
事前の軽量化:不要なページを削除したり、解像度を下げたPDFに再構成してから取り込む。
Vectorworksの設定調整:表示画質を一時的に低めに設定し、必要なときだけ高画質に切り替える。
これにより作業中の動作が軽快になり、作業スピードと仕上がりのバランスを取りながら効率的に進められます。さらに、データが軽くなれば協力会社やクライアントへの受け渡しもスムーズになり、全体のワークフロー改善にもつながります。
このように、文字化け・線の編集問題・ファイルサイズの肥大化といったトラブルは、事前の準備や工夫によって大幅に防ぐことが可能です。あらかじめ対処法を知っておけば、PDFの取り込みを安心して行い、Vectorworks 2018をより快適に活用できるでしょう。
7. 他バージョンとの比較
Vectorworksは2018以降も毎年のように新しい機能や改善が追加されており、PDFの取り込み精度や互換性も少しずつ向上してきました。とはいえ、現在でも2018バージョンを使い続けているユーザーは少なくありません。業務環境によっては安定性やライセンスコストの兼ね合いから、最新版への移行を急がない方も多いのが現実です。
そこで、ここではVectorworks 2019以降で追加された改善点と、2018バージョンならではの注意点を比較して解説します。バージョンごとの違いを理解することで、自分の作業環境に合った使い方や、アップグレードのタイミングを検討しやすくなるでしょう。
7.1 Vectorworks 2019以降の改善点
Vectorworks 2019以降では、PDF関連機能が着実に強化されています。特に改善が目立つのはテキスト認識とフォント置換の精度で、2018で頻繁に起きていた文字化けのリスクが軽減されています。また、取り込み処理そのものの安定性や速度も向上し、大きなPDFファイルを扱う際のストレスが減ったとの声がユーザーから寄せられています。
さらに、多様なフォントへの対応や、複雑なベクターデータでも過度に細分化されないようにする改良が行われており、データ編集の効率が高まりました。加えて、PDFだけでなくDWG/DXFといった他形式の互換性もバージョンを追うごとに進化しているため、他CADソフトとのやり取りもよりスムーズになっています。
つまり、Vectorworks 2019以降を使用できる環境にあるなら、PDF取り込みに関する作業の効率化やトラブル回避の面で大きなメリットが得られるといえるでしょう。ただし、バージョンごとに細かい挙動の違いや互換性の変化があるため、常に最新のリリース情報やユーザー事例を確認しておくことをおすすめします。
7.2 2018バージョンの特有の注意点
一方で、Vectorworks 2018は最新機能こそ備えていないものの、一定の準備や工夫をすれば十分に実務で活躍できるバージョンです。ただし特有の注意点として、PDF取り込み時にフォント関連の不具合が起きやすい点や、ベクター要素が過剰に分割されてしまう現象が挙げられます。
特に複雑な図面をベクターPDFで受け取った場合、細部の線が多数の断片に分割され、編集時にノイズのような扱いにくさが生じることがあります。その結果、修正作業に時間がかかる場合もあるため注意が必要です。
もしこのような問題が頻繁に発生する場合は、データの送受信段階でDWGやDXFといったCADネイティブ形式での交換を依頼するのが理想です。あるいは、依頼元に対して「フォントを埋め込んだPDF」や「適切なベクトル化設定を施したPDF」を提供してもらうよう調整すれば、作業のしやすさが大きく変わります。
このように、Vectorworks 2018でも活用は可能ですが、特性を理解し、事前の準備や工夫を行うことでトラブルを最小限に抑えられます。
まとめると、Vectorworks 2019以降はPDF取り込みに関する機能がより進化している一方で、2018も適切に扱えば十分な成果を得られるバージョンです。バージョンごとの強みと制限を把握したうえで、自分の作業内容やプロジェクト環境に合わせて最適な選択をすることが重要です。
8. まとめ
本記事では、Vectorworks 2018におけるPDF取り込みの手順やメリット、編集時に気を付けるべきポイント、実務における活用シーン、さらにトラブルシューティングや他バージョンとの比較までを幅広く解説しました。最後に、ここまでの内容を整理し、主要なポイントを振り返ってみましょう。
第一に、PDF取り込みの大きな強みはCAD間の互換性確保とアナログ図面の再利用です。AutoCADやIllustratorなど別ソフトで作成されたデータであっても、PDF形式ならVectorworksで活用できます。また、手書き図面やスキャン資料を取り込むことで、デジタル環境で効率よく再利用でき、建築設計・インテリアデザイン・舞台美術といった幅広い分野で実務の即戦力となります。さらに、ファイル軽量化やフォント置換など基本的な知識を押さえれば、図面編集やプレゼン資料作成がスムーズに行えます。
第二に、正しい操作手順の理解が効率化の鍵になります。メニューから「ファイル」→「読み込み」→「PDFを取り込み」を選択し、必要なページだけを選んで取り込むこと、そして縮尺や位置を正確に調整することが重要です。また、ベクターPDFかラスターPDFかを見極め、それぞれに応じた扱い方を選択することで、精度と効率を同時に高められます。
第三に、トラブルへの備えと解決策を持っておくことが安心につながります。文字化けやフォント非対応の問題、線の細分化による編集の煩雑さ、ファイルサイズ肥大化による動作の重さといった課題は、事前の調整や軽量化、適切なトラブルシューティングで十分に対応可能です。さらに、2019以降のバージョンではPDF取り込みの精度や互換性が強化されているため、環境が整えばアップグレードによって作業効率をさらに高めることもできます。
これらを総合すると、PDF取り込みを習得することは、データの再利用性と表現力を飛躍的に向上させる大きな武器になります。図面の再編集やプレゼン資料作成を効率化し、クライアントや関係者とのコミュニケーションをより円滑に進められるでしょう。
ぜひ本記事で紹介した知識や手順を実務に取り入れ、Vectorworks 2018を最大限に活用してください。効率的で説得力のある提案を実現し、日々の業務をさらに充実させていきましょう。
建設・土木業界向け 5分でわかるCAD・BIM・CIMの ホワイトペーパー配布中!
CAD・BIM・CIMの
❶データ活用方法
❷主要ソフトウェア
❸カスタマイズ
❹プログラミング
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
・3D Design Software for BIM CAD & Modeling | Vectorworks
https://www.vectorworks.net/en-US
・Vectorworks 2025 Help
https://app-help.vectorworks.net/2025/eng/index.htm
・Vectorworks Japan












