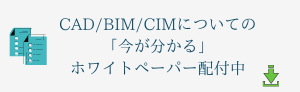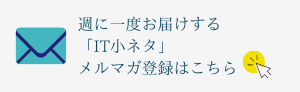建設GXとは?建設業界を変えるグリーントランスフォーメーションの現在地
1. はじめに
近年、「グリーントランスフォーメーション(GX)」という言葉を耳にする機会が増えています。GXとは、環境への負荷を減らしながら経済成長を実現しようとする取り組みで、エネルギー転換や脱炭素化を含む社会全体の変革を意味します。
なかでも建設業界は、大量の資材を使用し、エネルギー消費やCO₂排出量も多いことから、GXの推進が特に求められている分野です。しかし、「建設GX」と言われても、具体的に何をどう進めればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
建設GXとは、建物のライフサイクル全体を見直し、省エネや再生可能エネルギーの活用、ICT建機やAI技術などの導入を通じて、脱炭素と生産性向上を同時に目指す新しい取り組みです。この動きは、カーボンニュートラルの実現に貢献するだけでなく、業界内に新たなビジネスチャンスを生み出す可能性も秘めています。
本記事では、「建設GXとは何か?」という基本から、具体的な取り組み事例、関連する法制度、そして今後の展望までをわかりやすく解説します。
すでに多くの現場では、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(建設情報モデリング)、ドローン、スマート建機といった先進技術の導入が進み始めています。建設業全体でCO₂削減や持続可能なまちづくりに取り組む今こそ、建設GXを知り、行動に移すタイミングです。
2. 建設GXとは何か?
建設GXの全体像を理解するために、まずは「建設GXの基本的な考え方」と「建設業界で実際に進められている取り組み」の2つに分けて整理していきましょう。
現在、カーボンニュートラルや脱炭素化への取り組みが国内外で強く求められており、建設業界にもその対応が期待されています。
2.1. 建設GXの基本概念
建設GXとは、「グリーントランスフォーメーション(GX)」の考え方を建設業の領域に応用したもので、環境負荷を抑えながら持続可能な建設プロセスへと転換していく取り組みです。
特に注目されているのは、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー技術の普及、低炭素建材の活用といった、建設現場でのCO₂排出量を段階的かつ体系的に削減していく施策です。
このようなGXの実現には、デジタルトランスフォーメーション(DX)との連携も不可欠です。たとえば、ICT建機やAIによる施工技術を導入することで、生産性を高めながら環境負荷の低減を同時に実現できます。
また、GXは単なる現場の改善にとどまりません。設計・施工・運用・解体といった建築物のライフサイクル全体を見直し、サプライチェーン全体でCO₂排出削減を進めることを目的とした、より広範な概念として位置づけられています。
2.2. 建設業界におけるGXの具体的な取り組み
具体的な取り組みとしてまず挙げられるのが、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)などへの移行です。これらは、高断熱化や省エネ技術を積極的に取り入れ、建物のエネルギー消費を大幅に抑えつつ、太陽光発電などの再生可能エネルギーでエネルギーを自給することを目指しています。
次に注目すべきは、建設現場でのICT建機やスマート建機の導入です。重機にセンサーを搭載して燃料使用量をリアルタイムで管理したり、AI技術によって施工の効率化を図ることで、CO₂排出削減と同時に人手不足の対策にもつながると期待されています。
さらに、低炭素建材や再生資材の積極的な活用も進んでいます。建設廃棄物の発生を抑えるとともに、環境負荷を低減するために重要な取り組みです。ここで鍵となるのがLCA(ライフサイクルアセスメント)という考え方です。これは、建物が完成するまで、あるいは運用期間中にどれだけの環境負荷が生じるのかを可視化する手法で、建設物の環境性能を評価するうえで重要な指標となっています。
このように、さまざまな取り組みが組み合わさることで、「建設GX」という大きな潮流が形成されており、持続可能な社会の実現と経済成長の両立に向けた一歩となっているのです。
3. 建設業界を変えるGXの現状
ここでは、日本の建設業界におけるGXの現状について見ていきます。GXの推進に関する法整備の進展や、実際の脱炭素化の取り組みがどのように広がっているのかを確認し、建設業がどのような変革期にあるのかを具体的に把握しましょう。
3.1. GX推進法の影響と法改正の動向
日本政府は、「GXリーグ構想」を中心に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けたさまざまな取り組みを推進しています。その一環として整備が進められているのが「GX推進法」であり、企業が脱炭素に向けた投資や変革を行いやすくするための制度的な基盤となっています。
この法律は、脱炭素化に向けた国のロードマップを示すことを目指しており、企業のGX投資を促進するための制度整備が進められています。たとえば、今後はGX経済移行債の発行などを通じて、GX関連の設備投資資金の調達を支援する仕組みが検討されています。
また、建設業界においては、建設業法の改正が進められ、環境性能や脱炭素への取り組みを入札時の評価項目に反映する動きが広がっています。公共事業においては、CO₂排出削減の計画や、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価が加味されることで、GXに積極的な企業が有利になる環境が整いつつあります。
さらに、国交省や環境省などの省庁も補助金や助成制度を設けており、省エネ設備やICT建機の導入を支援する環境づくりが進められています。ただし、これらの制度は年度によって内容や条件が変わる場合があるため、活用の際は最新の情報を確認し、現場ごとの管理体制や申請対応の準備が重要になります。そのため、社内での情報共有や専門人材の育成が今後の重要な課題となっています。
3.2. 建設業界における脱炭素化の進展
現時点では、特に大手ゼネコンを中心に、建設現場における脱炭素化への取り組みが急速に進んでいます。たとえば、工場や物流施設、オフィスビルのZEB化(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)プロジェクトでは、高効率な省エネ設備と太陽光発電などを組み合わせ、使用エネルギーを実質ゼロに近づける試みが行われています。
また、ドローンやAIを活用した建設プロセスの最適化も着実に進んでいます。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(建設情報モデリング)を用いることで、設計段階から資材の無駄を削減し、再生可能エネルギーの活用計画も立てやすくなります。その結果、建物が完成した後の省エネ性能向上にもつながっています。
GXの取り組みは、単なる環境対策にとどまらず、労働環境の改善や品質向上といったさまざまなプラスの効果を生み出している点が特徴です。省エネと生産性向上の両立を図ることで、企業の競争力を高めることにもつながっています。
一方で、中小規模の建設企業においては、技術的なノウハウや初期投資のコスト面に課題を抱えるケースも多く見られます。特に人材や専門知識の不足がハードルとなっており、GXへの取り組みに踏み出しづらい現状もあります。このように、先進的な取り組みを行う大手企業と、それ以外の企業との間でGXの進展に差が生じているのが、現在の建設業界における大きな課題のひとつとなっています。
4. GXの実施に向けた課題と展望
ここでは、建設業界がGXを実行するうえで直面している主な課題と、それらを乗り越えた先に見えてくる未来の姿について整理します。脱炭素化を進めるためには、コストや人材の問題をはじめとする複数の壁がありますが、それを克服することで得られるメリットも大きく、技術の進化とともに大きな変革が期待されています。
4.1. 建設業界が直面する課題
建設GXを進めるうえで、最初に立ちはだかるのはコストの問題です。ZEBやZEHの実現、省エネ設備の導入、ICT建機の活用といった取り組みには初期投資が必要となるため、特に中小企業にとっては資金面の負担が大きくなりやすいのが実情です。短期的にはコスト増となる可能性があることから、慎重な判断が求められます。
また、LCA(ライフサイクルアセスメント)を用いて建物の環境負荷を評価するには、専門的な知識と経験が不可欠です。これまでの慣習的な施工管理や設計手法だけでは対応が難しく、新しい技術や概念を習得する必要があります。とくに中小企業では、こうした技術に精通した人材が不足しているケースが多く、教育や研修の機会が限られている点も課題となっています。
さらに、再生可能エネルギーの導入にあたっては、地域ごとの電力インフラや制度の違いにも注意が必要です。たとえば、太陽光発電を設置しても、自治体によって補助制度や電力の買い取り条件が異なるため、スムーズな導入や運用が難しいことがあります。こうした制度面のばらつきも、GXの推進を複雑にしています。
加えて、GXを効果的に進めるにはサプライチェーン全体での連携が欠かせません。建材メーカー、設計事務所、施工会社といった関係者が共通の目標と認識を持つことが重要ですが、現場ではその理解に差があり、情報共有が円滑に進まないことも多いのが現実です。業種間での認識のギャップが、GXの進行を妨げる一因となっています。
※再生可能エネルギーの導入や環境関連制度は、地域によって条件が異なる場合があります。具体的な対応には地域の条例や制度の確認が必要です。
4.2. GXの未来に向けた展望
一方で、こうした課題を乗り越えることができれば、建設業界は大きな進化を遂げる可能性を秘めています。たとえば、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展によって、BIMやCIMのデータを活用したエネルギー管理の自動化が進み、省エネ設計のノウハウが業界全体で共有されるようになると、より効率的で持続可能な建設が実現できるようになるでしょう。
また、AIやドローン技術の導入によって、現場作業の省力化が進み、人手不足の解消にも寄与すると期待されています。これにより、建設現場でのCO₂排出量を着実に削減できるだけでなく、建物の運用段階においても再生可能エネルギーの活用が進み、ライフサイクル全体での環境負荷低減が実現します。
さらに、GXに積極的に取り組む企業は、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても高く評価され、投資家や顧客からの信頼を得やすくなります。企業イメージの向上にもつながり、結果的に新しい取引先の獲得や、優秀な人材の採用など、さまざまなプラスの効果が期待できるでしょう。
こうした未来像は、決して一部の先進企業だけの話ではありません。むしろ、GXは業界全体の構造を変革する動きであり、今後は中小企業や地域の建設会社もその流れに加わることが求められています。GXはもはや選択肢ではなく、持続可能な社会づくりに向けた不可欠な取り組みであり、その波に乗ることこそが、次世代の建設業の成長戦略となるのです。
5. 企業に見られる建設GXの取り組み例
建設業界においてGXをどのように進めるかは、企業の規模や方針によってさまざまです。ここでは、大手から中小まで、GXに関する代表的な取り組みの傾向やよく見られる方向性を紹介します。一例として参考にし、自社での取り組みのヒントにしていただければと思います。
※ここで紹介している内容は一部企業の取り組み傾向に基づいた例であり、すべての企業に当てはまるわけではありません。あくまで参考情報としてご活用ください。
5.1. 日本企業におけるGX推進の傾向
大手ゼネコンでは、GX推進に向けて専任部署を設け、設計・施工段階からCO₂排出削減を意識したプロジェクトづくりを行うケースが増えています。たとえば、オフィスビルや商業施設をZEB化し、断熱性の高い構造や高効率の省エネ設備を取り入れる取り組みが進められていることが多いです。
また、ICT建機やAI技術を活用し、燃料の使用状況や稼働データを管理しながら施工を行う動きも見られます。こうした取り組みは、省エネや環境対策だけでなく、施工の効率化や人手不足への対応にもつながると期待されています。
都市開発の分野では、再生可能エネルギーを地域単位で供給するようなスマートシティ型の開発計画に、建設業が関与するケースも見られます。こうしたGX関連のプロジェクトは、国や自治体による補助制度とも連動し、企業がGXへ取り組みやすい環境が整えられてきています。
中小企業においても、規模に応じてGXに着手するケースが増えています。たとえば、LED照明の導入や省エネ設備の更新、再生資材の活用といった身近なレベルから始める動きが多く、外部の専門家と協力して補助金を活用する例も見られます。こうした地道な取り組みが、地域密着型の持続可能な建設スタイルにつながっています。
5.2. GXに積極的な企業に見られる主な取り組み
GXに積極的に取り組む企業の一部では、スマート建機やAI技術を活用し、施工現場のCO₂排出量をリアルタイムにモニタリングしようとする動きが見られます。たとえば、燃料使用量や稼働状況を共有プラットフォームで管理し、効率的な工程の見直しや環境負荷の低減に活用されるケースもあります。
また、BIMやCIMと連携した社内ソフトを使い、設計段階からLCA(ライフサイクルアセスメント)を取り入れる企業もあります。このような手法では、使用する建材の環境性能を事前に比較検討できるため、建設後の省エネ運用にもつながりやすいとされています。
さらに、資材メーカーや設計事務所など、他業種との連携によってGXを推進しようとする動きも活発です。環境性能評価の基準を共通化することで、製品開発や調達の合理化が進み、ESG評価の向上や新たな取引の機会にもつながる可能性があります。
このように、GXを単なる環境対策ではなく、企業の成長戦略の一環として位置づける企業が増えており、今後は業種や地域を越えた協働もさらに広がると考えられます。
6. まとめ
建設業界におけるグリーントランスフォーメーション(GX)は、単なる環境対策にとどまらず、業界全体の構造や価値観を根本から見直す大きな転換点となっています。省エネ技術や再生可能エネルギーの活用を通じて、地球環境への負荷を減らしながら、よりスマートで効率的な建設のあり方が求められています。
※本記事は2025年7月時点の情報に基づいています。法制度や支援内容は今後変更される可能性があります。最新の情報は、各省庁や自治体の公式サイトをご確認ください。
6.1. 建設GXがもたらす業界の変革と持続可能な未来への道筋
建設GXの推進によって、CO₂排出削減の実現だけでなく、生産性の向上や品質の安定化、さらにはコスト削減といった経営面での効果も期待されています。BIMやCIM、ICT建機、AIなどのデジタル技術を活用することで、施工工程の可視化や最適化が進み、建設現場はより柔軟で持続可能な環境へと進化しています。
また、国や自治体のカーボンニュートラル政策とも連動し、補助金や優遇措置を活用することで、企業がGXに取り組みやすい土壌も整いつつあります。こうした取り組みを通じて、サプライチェーン全体の連携が促され、建設業界全体にイノベーションの波が広がっているのです。
GXを推進することは、地球環境の保全に貢献するだけでなく、企業の信頼性やブランド価値を高め、長期的な競争力の強化にも直結します。持続可能な建設を実現することは、次の世代によりよい社会を残すことにもつながる、極めて重要な使命と言えるでしょう。
6.2. 読者へのメッセージ:GXへの取り組みの重要性と参加の呼びかけ
GXは一部の先進企業だけが取り組むものではなく、建設業界に関わるすべての人に関係する共通のテーマです。企業規模の大小を問わず、それぞれができる範囲からGXを始めることが、社会全体の変化を後押しする力になります。
たとえば、省エネ型の機器を導入したり、社内にGX担当を設けて情報を共有したり、国の補助制度を活用して脱炭素化の一歩を踏み出すことも大切な取り組みの一つです。また、他の業種や地域との連携を深めることで、より効果的なGX推進が可能になります。
今、建設業界は大きな転換期を迎えています。GXという新たな潮流に取り組むことで、自社の成長と社会貢献の両立を実現し、より持続可能な未来を築いていくことができるはずです。変化の担い手となるのは、この記事を読んでくださっている皆さん一人ひとりです。
今こそ、自らの仕事や現場を見直し、GXに向けた一歩を踏み出すときです。私たち一人ひとりの行動が、建設業の未来、そして地球の未来を変えていく力になるのです。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
GX(グリーン・トランスフォーメーション) (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/index.html
環境:グリーンインフラ推進戦略 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000017.html
脱炭素社会の実現に向けて~基礎編~(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/zeb/news/files/20220125_document4.pdf
GXリーグ公式WEBサイト
建築:建築GX・DX推進事業について – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000201.html