SOLIDWORKS入門|JIS材料データの基本とダウンロード方法をやさしく解説
1. はじめに
製品設計や機械設計を行ううえで欠かせないのが、設計ソフトに登録する「材料データ」です。とくにSOLIDWORKSを使う場合、正しい材料特性を設定していなければ、質量計算や応力解析といったシミュレーションの結果に大きな誤差が生じる可能性があります。
国内向けの製品設計では、日本産業規格(JIS)の材料を扱う機会が多く、JISに準拠したデータをSOLIDWORKSに取り込んでおくことは、解析精度を高めるだけでなく設計効率を上げるためにも重要です。
本記事では、SOLIDWORKS初心者の方を対象に、JIS材料データの基本から入手方法、さらに設計や解析にどう活用できるかをやさしく解説します。これからJIS材料データを導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
2. SOLIDWORKSとJIS材料データの基本
2.1. SOLIDWORKSの役割と重要性
SOLIDWORKSは、3次元のパーツやアセンブリを作成できる代表的なCADソフトウェアです。単に形状を設計するだけでなく、応力解析や熱解析、振動解析といった多様なシミュレーション機能(SOLIDWORKS Simulation)を備えているため、設計から製造まで幅広い分野で活用されています。
CAD設計の現場で求められるのは、美しい形状を描くことだけではありません。実際の材料特性を反映させることで、質量計算の精度を高めたり、応力解析の結果をより正確にしたりすることができます。したがって、設計段階で適切な材料を選び、SOLIDWORKSのマテリアル設定に正しく登録することは、最終的な製品の品質を大きく左右する重要な工程です。
さらに、日本国内向けの製品ではJIS規格に準拠した材料を使用するケースが多く見られます。しかし、SOLIDWORKSの標準ライブラリにはJIS材料データが含まれていないこともあり、そのままでは十分に対応できません。そこで、JIS材料データを追加・導入することで、解析の精度が向上し、設計作業そのものも効率化できるのです。
2.2. JIS材料データの概要とその必要性
JIS材料データとは、日本産業規格(JIS)に基づいて定められた各種材料の物性値をまとめたデータを指します。例えば、構造用鋼材のSS400や機械構造用炭素鋼のS45C、そしてステンレス鋼の代表格であるSUS304など、日本の工業分野で頻繁に使われる材料規格が幅広く網羅されています。
これらのデータをSOLIDWORKSに登録しておけば、設計者は国内規格に即した材料特性をそのまま活用できます。強度、硬度、密度といった数値をCAD上で正確に反映できるため、シミュレーション結果も実際の使用環境に近づけることが可能です。特に国内の製造業では、JISの材料名が図面や部品表にそのまま表記される場合が多く、チーム内や取引先との共通言語としても大きな役割を果たします。
逆に、JISデータが不足していると、ASTMなど海外規格の代替データを使わざるを得なくなります。しかしその場合、設計解析の正確さが損なわれ、最終的な品質や安全性に影響するリスクがあります。こうした問題を避けるためにも、JIS材料データの追加はSOLIDWORKSを使い始めたばかりの入門者にとっても早い段階で理解しておきたい重要なポイントといえるでしょう。
3. JIS材料データの基本知識
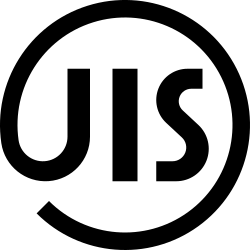
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E6%A0%BC
3.1. JIS規格の理解
JIS規格とは、日本国内で流通する工業製品や材料の品質や安全性を確保するために定められた標準規格のことです。アルファベットと数字の組み合わせによって表される材料記号で管理されており、鋼材やステンレス鋼をはじめとして幅広い分野に対応しています。
SOLIDWORKSを学び始めた段階でも、この規格を意識しておくと、後工程での解析や品質保証に役立ちます。JIS規格は国内市場における事実上の標準となっているため、設計図面や検討資料に材料名が記載されていた場合でも、すぐに理解して対応できるというメリットがあります。
たとえば、JIS規格で広く知られるSS400を例にとると、「SS」はStructural Steel(構造用鋼材)を意味し、一般構造用圧延鋼材を指します。そして「400」は引張強さの下限値(MPa)を示しています。このように規格記号を理解しておくと、図面に記載された材料名を見ただけで特性を把握できるため、設計解析の流れもスムーズになります。
3.2. 代表的なJIS材料とその特性
JIS材料の中で特に使用頻度が高いのがSS400、S45C、そしてSUS304です。SS400は汎用性が高く、加工性や溶接性に優れるため、建築から機械部品まで幅広い分野で利用されています。S45Cは炭素量が比較的多く、強度や硬さに優れていることから、シャフトやギアなど機械要素に多用される鋼材です。SUS304はステンレス鋼の代表的な材質で、耐食性や耐久性に優れているため、食品機器や医療機器などの衛生性が求められる分野で広く活用されています。
これらの材料特性を理解しておけば、設計時に用途や環境に合わせた最適な材料を選択できます。SOLIDWORKSで材料設定を行う際には、密度やヤング率、降伏点(塑性変形が始まる応力)、さらには引張強さ(最大応力)といった個別の特性値を正確に入力することが求められます。あらかじめJIS材料データを追加しておくことで、必要な物性値を参照しながら、より精度の高い解析を実現できるのです。
さらに、一度登録した材料データはライブラリとして保存しておけるため、次回以降の設計で繰り返し利用できます。これにより、同じ材料を使う別プロジェクトや異なる部品設計でも効率よく作業を進められるようになり、結果として設計全体の生産性向上につながります。
4. JIS材料データのダウンロード方法
4.1. 信頼できるダウンロードソース
JIS材料データを利用するには、まず信頼できる入手先を見つけることが重要です。具体的には、各種メーカーが公式に公開しているPDFの技術資料や、SOLIDWORKSユーザーコミュニティで共有されているライブラリなどがあります。さらに、SOLIDWORKS公式が提供する「Materials Web Portal」から直接 .sldmat ファイルを取得する方法もあり、この場合は有効なサブスクリプション契約が必要で、Simulationのライセンス形態によって利用範囲が変わります。加えて、大学や公的研究機関が公開している材料データベースを活用できることもあり、これらは信頼性の高い情報源として特に有効です。
データをダウンロードするときには、ファイル形式がSOLIDWORKSに対応しているかを必ず確認しましょう。とくに .sldmat 形式で提供されているデータは、そのままSOLIDWORKSのマテリアルライブラリに読み込める可能性が高く、最も扱いやすい形式です。一方で、ExcelやCSVといった形式で配布されている場合も少なくありません。その場合は、手動で入力するか、変換ツールを利用してデータを取り込むのが一般的です。
また、市販されている有料の材料データベースも存在し、これらは詳細で信頼性の高いデータを提供してくれます。まずは無料のリソースで試してみるのが良いですが、正確な物性値が設計の信頼性を高めることを考えると、有料データベースも十分に投資価値のある選択肢といえるでしょう。
4.2. ダウンロードとファイル形式の理解
JIS材料データを入手する際には、提供元がどのようなファイル形式をサポートしているのかを確認しておくことが大切です。最も推奨されるのは、SOLIDWORKSにそのままインポートできる .sldmat ファイルですが、配布元によってはXMLやテキスト、Excel/CSVといった形式で提供されるケースもあります。
SOLIDWORKSでは .sldmat ファイルをスムーズに取り込める仕組みが整っているため、まずはこの形式を優先的に探すと効率的です。それ以外の形式でしか入手できない場合は、Excelデータをダウンロードし、Material Editor画面に数値を一つひとつ入力する方法もあります。慣れるまでは多少手間に感じますが、確実に材料プロパティを登録できる点は大きなメリットです。
さらに、ファイルをダウンロードした後は、必ずウイルススキャンやセキュリティチェックを行いましょう。信頼できる公式サイトから入手したデータであっても、企業の設計部門では安全管理が非常に重視されるため、確認を怠らないことが重要です。
5. SOLIDWORKSでのJIS材料データの導入手順
5.1. 材料データベースへの追加方法
ダウンロードしたJIS材料データをSOLIDWORKSに取り込むには、まず「Material」の設定画面を開く必要があります。具体的には、メニューバーから [Tools] > [Options] を選択し、[System Options] 内の [File Locations] に進む方法のほか、パーツの材料設定画面から直接「編集」をクリックする方法など、いくつかのアクセス経路があります。
そこから「カスタム材料」や 「新しいライブラリ(New Library)」 を作成し、取得した .sldmat ファイルなどを割り当てます。ファイルを整理する際は、フォルダ名やファイル名に「JIS」といった識別しやすいラベルを付けておくと後から探しやすく便利です。
なお、追加作業の際には誤って既存のデフォルトファイルを上書きしてしまわないよう注意が必要です。オリジナルデータのバックアップを必ず取っておけば、万が一トラブルが起きても元の状態にすぐ戻すことができるため安心です。
5.2. カスタム材料データベースの作成
会社やプロジェクトによって使用するJIS材料が限られている場合は、独自のカスタム材料データベースを作るのが効果的です。たとえば、使用頻度の高いSS400・S45C・SUS304などの主要材料だけをまとめたフォルダを用意しておけば、新人エンジニアやチームメンバーも迷わず選択でき、作業効率が大幅に向上します。
SOLIDWORKSのマテリアルタブで「新しいライブラリを作成」を選び、そこにダウンロードしたファイルを保存するのが基本的な手順です。このとき、カテゴリーを「Carbon Steel」「Stainless Steel」などに分けて整理しておくと、後から検索しやすく、設計作業のスピードアップにも役立ちます。
また、カスタムデータベースは社内ルールを反映できる点もメリットです。例えば、単位系をSI単位に統一しておくことで、重量計算や応力解析で混乱が起こりにくくなります。特にミリメートルやグラムを基準に統一しておくと、設計チーム全体での整合性が確保できるでしょう。
5.3. インポート後の確認作業
JIS材料データを追加した後は、必ず動作確認を行いましょう。まずは平板や簡単なブロックモデルを作成し、カスタム材料を適用して質量計算を実行します。ここで想定どおりの値が表示されれば、正しく設定されていると判断できます。
加えて、応力解析や熱解析など簡易的なシミュレーションを行ってみるのも有効です。ヤング率などの物性値が正しく反映されていれば、シミュレーション結果が正常に出力されるはずです。もしエラーが表示された場合は、入力値に誤りがないか、あるいは材料設定が欠けていないかを再確認してください。
さらに、カスタムライブラリをチーム全体で利用する場合は、ネットワークドライブやクラウドストレージに保存して一元管理すると効率的です。全員が同じ材料データベースを参照できることで、情報のばらつきを防ぎ、設計作業全体の効率化と品質向上につながります。
6. 実践:よく使用されるJIS材料の設定例
6.1. SS400の設定
まず最初に、JIS規格の中でも最も一般的に使われる材料の一つであるSS400を設定してみましょう。SS400は建築分野や一般機械用途で幅広く採用される普通鋼材で、板厚や形状に関わらず扱いやすく、加工や溶接のしやすさも特徴です。
SOLIDWORKSのMaterialsタブで「新規材料」を選択し、名称に「SS400」と入力します。その後、密度を約7.85 g/cm³、ヤング率を約200 GPaといった代表的な参考値を登録します。降伏点や引張強度などの数値は、必ず製品仕様やJIS規格表を確認し、実際のデータを基に設定することが推奨されます。
設定が終わったら、試しに簡単なモデルへ「SS400」を適用して質量計算や強度解析を行いましょう。得られた結果が想定値から大きく外れていれば、単位系や小数点精度に誤りがないか確認し、必要に応じて修正します。
6.2. S45Cの設定
次に、機械構造用炭素鋼であるS45Cを設定します。S45Cは炭素量が約0.45%含まれており、熱処理後に高い強度と靭性を発揮する材料です。シャフトやギアのように強い応力がかかる部品に幅広く使用されています。
設定の手順はSS400と同じです。名称を「S45C」と入力し、密度は7.85 g/cm³前後、ヤング率は約200 GPaを目安に登録します。さらに、焼入れや焼戻しといった熱処理を考慮した解析を行う場合には、その条件に応じた変化値を追加で登録しておくと、SOLIDWORKS Simulationでより実際に近い挙動を再現できます。
また、S45Cは仕上げ状態や熱処理方法によって機械的特性が変化するため、用途に応じて複数のバリエーションを作成しておくのも有効です。例えば「S45C-焼入れ」「S45C-焼戻し」といったラベルを材料名に付けて区別すれば、設計時に迷うことなく選択できるでしょう。
6.3. SUS304の設定
最後に、ステンレス鋼の代表格であるSUS304を設定してみましょう。SUS304は耐食性に優れ、食品設備や医療機器、さらに建築装飾品など、多種多様な分野で利用されています。化学的に安定して錆びにくく、美しい外観を保ちやすい点も大きな特徴です。
設定方法は他の鋼材と同様で、名称を「SUS304」とし、密度を約7.93 g/cm³、ヤング率を約193 GPaの参考値として登録します。ステンレス鋼では特に溶接や加工条件による強度変化を把握することが重要であり、解析を行う際には熱伝導率や比熱などの物理特性も正確に入力しておくと、より信頼性の高い結果を得られます。
設定を終えた後は、腐食環境を想定したケースでの利用も考慮し、耐久試験の補正値などを追加データとして登録しておくと効果的です。こうした情報を材料データベースに盛り込んでおけば、長期的な製品寿命の予測や耐久性評価にも役立ちます。
7. 材料データの活用方法
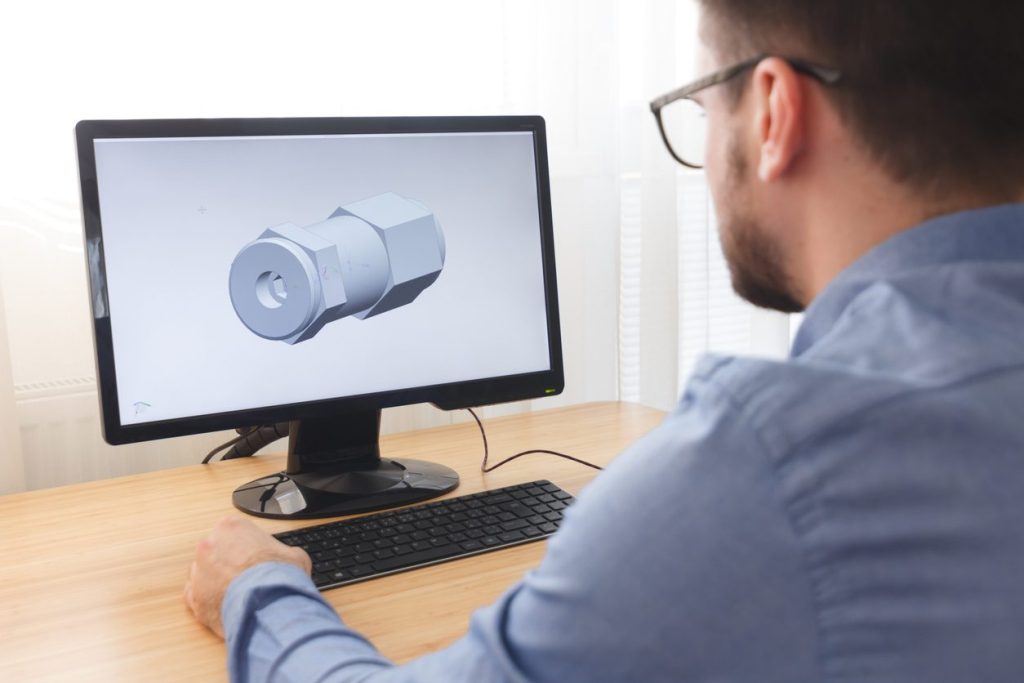
7.1. 設計検討での活用
SOLIDWORKSを学び始めた段階で材料データベースを整備しておくと、設計解析の効果をより大きく引き出すことができます。たとえば、部品の重量バランスを確認したり、荷重が集中する箇所を解析したりする際、JIS材料データを反映した正確な質量計算や応力解析を行うことで、製品寿命を延ばし、安全性を高めることが可能になります。
また、CAD設計では部品形状の変更によって応力分布が大きく変わる場合があります。あらかじめJIS規格に基づいた材料データを取り込んでモデルを最適化すれば、必要以上の肉厚を削減でき、軽量化やコスト削減にもつながります。
このように材料特性を正しく設定することは、設計の初期段階から非常に大きな意味を持ちます。コスト面だけでなく、性能や耐久性といった要素のバランスを取る上で欠かせない工程であり、「どの材料を選ぶべきか」を判断するための有力な手がかりとなるのです。
7.2. 図面作成での活用
SOLIDWORKSでは、3Dモデルから2D図面を自動生成することができます。その際に活用できるのが 「Link to Property」機能($PRP, $PRPSHEET) です。この機能を利用すれば、モデルに設定した材料名をそのまま図面に自動反映でき、JIS材料データベースが正しく登録されていれば「SS400」や「S45C」といった規格名が自動的に表示されます。その結果、図面作成の効率と正確性が大幅に向上します。
特に複数人で設計を進める場合、材料記号の表記を統一できることは大きなメリットです。工場やサプライヤーに図面を渡す際にも、国内規格に準じた明確な情報を伝達できるため、解釈の違いによるミスを防ぐ効果があります。
さらに、部品表(BOM)の作成や品番管理にもJIS材料データは役立ちます。同じ材料を使った部品を複数まとめる場合でも、自動的に「どの材料がどれだけ必要か」を一括表示できるため、在庫管理や発注業務を効率化できるのです。
7.3. コスト計算への活用
材料データの価値は、設計解析や図面作成にとどまりません。製品コストを算出する際にも大いに役立ちます。特に重量を基準に見積もる案件が多い場合、SOLIDWORKSで計算された質量データをそのまま活用することで、材料費の概算をスピーディに算出できます。
例えば、同じ機能を持つ部品をSS400からS45Cに切り替えた場合、単価や重量の違いから生じるコスト変化を即座に比較できます。これにより、設計段階で製品全体の価格競争力を検討する際に柔軟に対応できるのです。
また、材料重量は輸送費の算出にも直結するため、正確なデータは物流コストの見積もりにも欠かせません。さらに、射出成形品や複合材料など他のJIS規格を含むさまざまな材料と比較することで、製品全体のコストコントロールに幅広く貢献できます。
8. トラブルシューティング
8.1. よくある問題と解決方法
まず一つ目に多いのは、材料データが反映されず、SOLIDWORKS上で「不明な材料」と表示されてしまうトラブルです。これは追加ファイルの保存場所やフォルダ設定が間違っている場合によく発生します。解決するには、ファイルロケーションの設定を開き、「材料データベース」のディレクトリが正しく指定されているかを確認しましょう。
二つ目によく見られるのは、ユーザーが手動で入力した数値の誤りです。ヤング率や密度などの数値は、小数点以下の桁がずれるだけでも解析結果に大きな影響を与えます。疑わしい場合は材料プロパティを再確認し、JIS規格や信頼できる資料を参照して正しい値に修正してください。
三つ目は、異なるSOLIDWORKSバージョン間で材料データが正常に受け渡せないケースです。ファイル形式の違いによって互換性の問題が生じることがあるため、異なる環境で開く際には、可能な限り最新形式で保存・読み込みを行うことをおすすめします。
8.2. 材料データの検証方法
ダウンロードした材料データが正しい数値を持っているかを検証する作業も欠かせません。最も基本的な方法は、JISハンドブックや公的な資料と照らし合わせて、密度やヤング率といった主要な物性値を確認することです。
さらに一歩進んだ方法として、簡易的な応力解析を実施し、理論値とおおむね一致する結果が得られるかどうかを確かめるのも有効です。例えば、引張試験のシミュレーションを行い、大きな差異がないかを確認すれば、データの信頼性を判断できます。
もし公式資料とも整合しない場合は、配布元のデータ自体に誤りがある可能性があります。そのようなときは、SOLIDWORKSユーザーコミュニティや専門家に相談する、あるいは別の情報ソースを探すなど、正確なデータを入手する工夫が求められます。
9. 応用編:カスタム材料の作成
9.1. 独自材料データの作成手順
革新的な製品開発や特殊な用途の部品を設計する場合、標準のJIS材料データだけでは十分に対応できないことがあります。そのようなときは、独自のカスタム材料データを作成するのが有効です。例えば、複合材料や特殊なコーティングを施した金属などは、既存の規格には収まらない特性を持つため、自分でデータを整える必要があります。
SOLIDWORKSの材料エディタを利用して新しいエントリを作成し、必要なパラメータを一つひとつ入力していきます。入力すべき項目はヤング率や密度だけではなく、熱膨張係数やポアソン比など解析内容に応じたデータを含めることが重要です。
このとき、テストサンプルから得た実測データや、製造メーカーが提供する技術資料をもとに数値を登録するのが基本となります。特に実測データを基にしたカスタム材料は、解析の精度を高め、より現実的なシミュレーション結果を得るために大きく役立ちます。
9.2. 材料ライブラリの管理とバックアップ
カスタム材料やJIS材料データベースを継続的に活用していくためには、定期的なバックアップやバージョン管理が欠かせません。複数人で利用している環境では、誰かがデータを更新した瞬間に他のユーザーの環境で不整合が起きる可能性があるため、管理体制を整えておく必要があります。
そのためには、チーム全体でルールを定め、ライブラリを更新する際には必ず履歴を残す、またネットワークドライブで共有するなどの仕組みを導入することが望ましいです。こうしたルール化によって、材料プロパティに関するエラーを減らし、SOLIDWORKSのマテリアルデータを重要な情報資産として安全に管理できます。
さらに、SOLIDWORKSユーザーコミュニティでは、実際の運用事例や効率的な管理方法が紹介されることもあります。定期的にコミュニティの情報をチェックし、自社の運用に役立つ方法があれば積極的に取り入れることで、よりスムーズで信頼性の高いデータ管理が実現できるでしょう。
10. まとめ
本記事では、SOLIDWORKSを使い始めた方を対象に、JIS材料データの基礎からダウンロード方法、Material Databaseへの追加手順、さらにカスタム材料の作成方法までを体系的に紹介しました。
国内規格であるJIS材料データを正しく導入することで、質量計算や応力解析といったシミュレーションの精度が大幅に向上し、CAD設計全体の品質を高めることができます。特に、SS400・S45C・SUS304といった代表的な材料を揃えておくだけでも、日常的な設計業務で大きな効果を発揮するでしょう。
今後、SOLIDWORKSの操作やチュートリアルをさらに進めていく中で、設計者はJIS材料データベースを活用することで、より高度なシミュレーションやコスト最適化にも対応できるようになります。
ぜひ本記事を参考に、自分のプロジェクト環境に合わせてSOLIDWORKSのライブラリをカスタマイズしてみてください。材料データを正しく扱うことは、効率的で信頼性の高い製品開発につながる第一歩です。ご自身の設計スタイルに合ったデータ活用を実践し、より良い設計成果へとつなげていきましょう。
建築・土木業向け BIM/CIMの導入方法から活用までがトータルで理解できる ホワイトペーパー配布中!
❶BIM/CIMの概要と重要性
❷BIM/CIM導入までの流れ
❸BIM/CIM導入でよくある失敗と課題
❹BIM活用を進めるためのポイント
についてまとめたホワイトペーパーを配布中

<参考文献>
3次元設計と製品開発ソリューション
SOLIDWORKS Materials Web Portal – 2025 – SOLIDWORKS Connected ヘルプ
https://help.solidworks.com/2025/japanese/SWConnected/cworks/c_sw_materials_web_portal.htm
JISC 日本産業標準調査会
日本規格協会 JSA Group Webdesk












